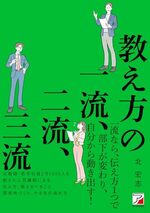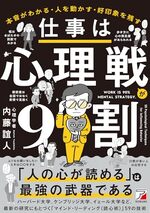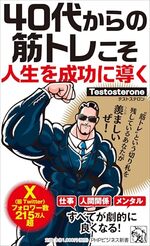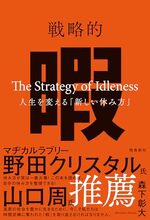プレイングマネジャーの「仕事の任せ方」大全

プレイングマネジャーの「仕事の任せ方」大全
著者

著者
加藤定一(かとう ていいち)
プライマリ・パートナーズ代表。研修講師/組織コンサルタント。
世界的たばこメーカーのフィリップ モリス ジャパンおよびその前身企業に32年間勤務。 営業部門・営業企画部門での経験を経て、営業組織開発チームに異動し、約11年間にわたり営業組織を中心とした人材育成に従事。新入社員育成、営業所長研修、課題解決営業研修、コーチング研修など、多岐にわたる研修の開発・実施を担当し、育成を手がける。
組織開発の領域では、営業員コンテスト制度の設計、eラーニングの導入、社内マネジャー層へのコーチング制度導入など、多くのプロジェクトをリード。特に、加熱式たばこ「IQOS」日本市場導入時には、営業員向けの包括的研修プログラムを開発し、円滑な市場定着に貢献した。
こうした経験を通じて、「楽しくない仕事は存在しない。本気で取り組めば、大抵の仕事は楽しくなる」ということを確信。より多くのビジネスパーソンに「本気で働くことの楽しさ」を伝えるため、2018年に独立し、人材育成支援事業「プライマリ・パートナーズ」を設立。企業研修講師・組織コンサルタントとして、リーダーシップ、営業スキル、コーチング、プレゼンテーション、理念浸透などを専門分野とし、大手清掃機器メーカー、大手住宅設備メーカー、大手エネルギー供給企業などに独自の研修を展開している。
本書の原点ともいえる「仕事の任せ方研修」は、ケルヒャージャパン株式会社のマネジメント研修やLIXILの代理店向け研修をはじめ、多くのビジネスパーソンが受講し、高い評価を得ている。
プライマリ・パートナーズ代表。研修講師/組織コンサルタント。
世界的たばこメーカーのフィリップ モリス ジャパンおよびその前身企業に32年間勤務。 営業部門・営業企画部門での経験を経て、営業組織開発チームに異動し、約11年間にわたり営業組織を中心とした人材育成に従事。新入社員育成、営業所長研修、課題解決営業研修、コーチング研修など、多岐にわたる研修の開発・実施を担当し、育成を手がける。
組織開発の領域では、営業員コンテスト制度の設計、eラーニングの導入、社内マネジャー層へのコーチング制度導入など、多くのプロジェクトをリード。特に、加熱式たばこ「IQOS」日本市場導入時には、営業員向けの包括的研修プログラムを開発し、円滑な市場定着に貢献した。
こうした経験を通じて、「楽しくない仕事は存在しない。本気で取り組めば、大抵の仕事は楽しくなる」ということを確信。より多くのビジネスパーソンに「本気で働くことの楽しさ」を伝えるため、2018年に独立し、人材育成支援事業「プライマリ・パートナーズ」を設立。企業研修講師・組織コンサルタントとして、リーダーシップ、営業スキル、コーチング、プレゼンテーション、理念浸透などを専門分野とし、大手清掃機器メーカー、大手住宅設備メーカー、大手エネルギー供給企業などに独自の研修を展開している。
本書の原点ともいえる「仕事の任せ方研修」は、ケルヒャージャパン株式会社のマネジメント研修やLIXILの代理店向け研修をはじめ、多くのビジネスパーソンが受講し、高い評価を得ている。
本書の要点
- 要点1自分の業務を「緊急度」と「重要度」の2軸で分類して生まれる4種類の仕事のうち、部下に任せるべき仕事は、「重要で緊急な仕事」と「緊急だが重要ではない仕事」の中にある。
- 要点2部下に仕事を任せる際は、13の項目を記載した「戦略的業務指示書」を作成する。その目的は、部下の育成である。
- 要点3部下が成長するかどうかは、仕事を任せた後の上司の関わり方による。「問題解決支援コーチング」を展開しながら、業務遂行の状況を的確に把握し、必要な場合は介入し、部下の業務完遂をサポートしよう。
- 要点4業務遂行後は、必ず評価面談を行うべき。この面談こそが、部下を動機づけ、成長させる最重要アクションであり、これによって「部下を育成する戦略的業務指示」が完成することとなる。
要約
任せる仕事を決める
仕事を分類する
部下に仕事を任せるにあたっては、まず自分の業務を「緊急度」と「重要度」の2軸で分析する必要がある。仕事の種類によって適切な任せ方は異なるうえ、そもそも部下に任せる必要がない、あるいは任せられない仕事も存在するからだ。
第1領域は、重要で緊急な仕事。締め切り直前の仕事、クレーム対応、差し迫った問題への対処などが該当する。
第2領域は、重要だが緊急ではない仕事。戦略立案、部下育成、業務改善など、将来への投資となる業務であり、上司自身が時間を割くべきだ。
第3領域は、緊急だが重要ではない仕事。重要でない会議や断りきれない依頼への対応など、他者都合で発生した業務がここに含まれる。
第4領域は、重要でも緊急でもない仕事。不要な書類整理や形だけの業務報告書作成など、成果や成長にほとんど寄与しない無駄な業務であり、部下に任せる対象外とすべきである。
次項では、第1領域および第3領域の仕事の任せ方を見ていく。
第1領域の業務の任せ方

Yagi-Studio/gettyimages
第1領域の「重要で緊急な仕事」は、「重大問題の解決業務」と「間に合わせ業務」の2つに分類できる。
まず「重大問題の解決業務」とは、顧客からのクレームや重要設備の故障といった、突発的に発生した重大な問題や危機への対応業務である。迅速な解決が求められ、失敗が許されないため、マネジャー自身が対応するケースが多いだろう。
とはいえ、この種の業務は部下の成長に直結することが多いので、上司の立場でなければ対応できない場面を除き、積極的に部下に任せていきたい。
次に「間に合わせ業務」とは、先延ばしを続けた結果、期限が迫って慌てて対応する業務を指す。このような仕事に必要なのは自己管理の徹底であり、部下に任せるものではない。
第3領域の業務の任せ方
第3領域の「緊急だが重要ではない仕事」は、「急な要望への対応」「定型・定例業務」「付帯業務」の3つに分類できる。
まず「急な要望への対応」は、他者からの突発的な依頼や問い合わせへの対応である。あなたにとっては価値の低い雑務に見えるかもしれないが、部下にとっては「成長機会」となりうる。その業務が部下の成長につながることとその理由を明確に伝えつつ、どんどん任せていこう。
次に「定型・定例業務」は、価値の少ない定例会議への参加や定型の報告書作成などが該当する。可能であれば廃止や簡素化を検討すべきだが、それが難しい場合は、各業務を実行することによる「成長機会」を伝えつつ、部下に任せたい。
最後の「付帯業務」は、会議室の手配など、業務本体に付随する些末な作業である。こうした業務は、指示ではなく協力依頼という形で部下の力を借りよう。
【必読ポイント!】 仕事を任せる
戦略的業務指示書に記載する13の項目
本書は、部下への仕事の任せ方として、部下の育成を目的とした「戦略的業務指示」を提案している。

この続きを見るには...
残り2874/4056文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.06.25
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約