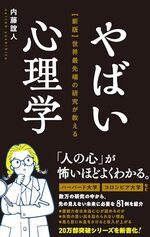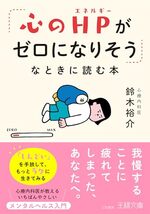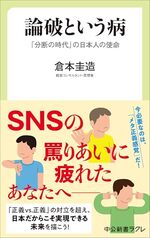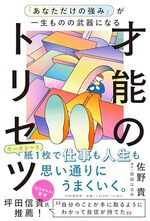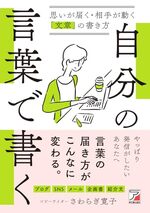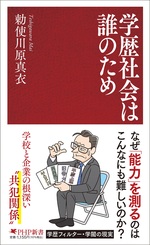なぜ私たちは、仕事が嫌いになるのか。
ハイパフォーマーの隠された真実


著者
相原孝夫(あいはら たかお)
人事・組織コンサルタント。株式会社HRアドバンテージ代表取締役社長。早稲田大学大学院社会科学研究科博士前期課程修了。マーサージャパン株式会社代表取締役副社長を経て現職。人材の評価・選抜・育成および組織開発に関わる企業支援を専門とする。経営アカデミー(日本生産性本部)、日経ビジネススクールほかでの講演等多数。主な著書に、『会社人生は「評判」で決まる』『ハイパフォーマー 彼らの法則』『仕事ができる人はなぜモチベーションにこだわらないのか』『職場の「感情」論』などがある。
人事・組織コンサルタント。株式会社HRアドバンテージ代表取締役社長。早稲田大学大学院社会科学研究科博士前期課程修了。マーサージャパン株式会社代表取締役副社長を経て現職。人材の評価・選抜・育成および組織開発に関わる企業支援を専門とする。経営アカデミー(日本生産性本部)、日経ビジネススクールほかでの講演等多数。主な著書に、『会社人生は「評判」で決まる』『ハイパフォーマー 彼らの法則』『仕事ができる人はなぜモチベーションにこだわらないのか』『職場の「感情」論』などがある。
本書の要点
- 要点1ウェルビーイングは、ポジティブな感情、エンゲージメント、良好な人間関係、生きる意味の探求、達成感という5つの要素から成る。仕事でパフォーマンスを高めることが、人生全体のウェルビーイングに直結する。
- 要点2「幸せな労働」を可能にする3つの条件は、自由裁量・強みの発揮・成果の認識(自他ともに)である。ハイパフォーマーになれば、これらは自然と満たされていく。
- 要点3ハイパフォーマーに共通するのは、失敗から学ぶ姿勢と、身近な人を支援しようとする姿勢である。
要約
【必読ポイント!】 仕事とウェルビーイングの深い関係
企業がウェルビーイングに注目する理由

recep-bg/gettyimages
近年、「ウェルビーイング(Well-being)」という概念が注目を集めている。世界保健機関(WHO)は、これを「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と定義している。従来、国家の豊かさを測る指標としてはGDP(国内総生産)が用いられてきたが、GDPでは捉えきれない生活の質や人々の幸福感を映す新たな尺度として、各国政府や国際機関がウェルビーイングへの関心を強めているのだ。
企業もまた、ウェルビーイングに注目している。日本では楽天グループ、ロート製薬、アシックス、味の素などが、従業員のウェルビーイング向上に向けた取り組みを進めている。
企業が従業員のウェルビーイングを高めることによって得られる利点は大きく2つある。第一に、心身ともに健康な従業員が増えれば、一人ひとりのモチベーションが向上し、企業としての生産性・業績アップが見込める点。第二に、幸福度の高まりが会社への帰属意識を強め、離職防止につながる点である。
では、日本ではどれほどの人々がウェルビーイングを実感しているのだろうか。パーソル総合研究所による国際比較調査(2022年)では、「はたらくことを通じて、幸せを感じている」と答えた日本人は49.1%にとどまり、調査対象となった18カ国・地域の中で最も低い結果となった。
ウェルビーイングの中核に位置し、企業への「愛着」や「思い入れ」を意味する「エンゲージメント」に関しても、日本の水準は低い。アメリカのギャラップ社による調査(2023年)では、日本の従業員エンゲージメントはOECD加盟国中で最下位となり、4年連続で過去最低を更新している。
なぜ従業員のウェルビーイングは高まらないのか
企業がさまざまな施策を講じているにもかかわらず、なぜ従業員のウェルビーイングは高まらないのか。この疑問を解き明かすために、著者は「幸福で生産的な働き手理論(HPWT=The Happy-Productive Worker Thesis)」をめぐる議論を紹介する。
HPWTとは、「より幸せな労働者は、より優れた労働者である」という、数十年にわたって研究されてきた仮説である。2019年、これを批判的に検証したスペインの研究者らは、労働者を次の4類型に分類した。
(1)幸福で生産的
(2)幸福で非生産的
(3)不幸で非生産的
(4)不幸で生産的
すると、HPWTが前提とする「幸福で生産的」と「不幸で非生産的」な労働者は全体の一部に過ぎず、実際には「不幸で生産的」あるいは「幸福で非生産的」な労働者が多数を占めていたという。
この結果をふまえ、研究者らは職場における幸福を、「ヘドニック(hedonic)」と「ユーダイモニック(eudaimonic)」という異なる2つの軸で測定する必要性を提起した。ヘドニックは「快楽性」、ユーダイモニックは「有意義性」を指す。
一般にウェルビーイングが語られる際に念頭に置かれているのは、短期的な快適さに基づくヘドニック的幸福である。一方で、ユーダイモニック的幸福とは、より長期的な充足感や生きがいを意味する。アリストテレスが「真の幸福とは、徳のある人生を生き、価値ある行為によって得られる」と述べているように、長期的視点からのウェルビーイングを見過ごしてはならないのだ。
「不幸で生産的」な労働者は、快楽的な側面では満たされていないが、困難な状況のなかで努力を重ね、意義や充実感を見出している可能性がある。逆に、「幸福で非生産的」な労働者は、快適な職場環境にあるものの、達成感や目的意識には乏しいかもしれない。いわば、居心地のよい環境でぬくぬく過ごしているような状態である。
ゆえに企業は、「現在の快適さ」と「将来的な充実感」の双方を意識し、短期的・長期的両面からウェルビーイングを支える取り組みを検討すべきといえるだろう。

この続きを見るには...
残り2832/4463文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.08.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約