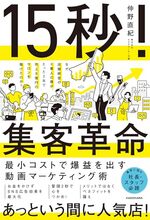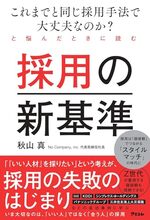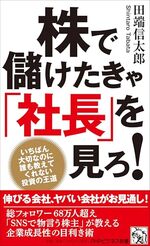経営者のための正しい多角化論
世界が評価するコングロマリットプレミアム
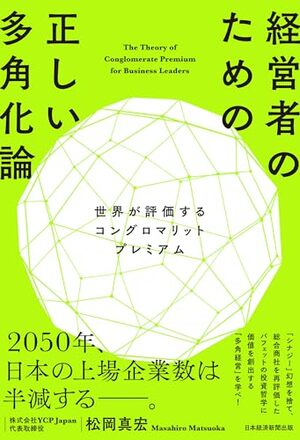
著者
松岡真宏(まつおかま さひろ)
株式会社YCP Japan 代表取締役
東京大学経済学部卒。野村総合研究所やUBS証券で小売・流通セクターの証券アナリストとして活動後、産業再生機構を経て、独立系コンサルティング会社を共同創業し、東証プライム上場企業へと成長させた。2025年1月より現職。カネボウ、ダイエー、アルピコホールディングスなど、再建案件を中心に10社以上の取締役に就任した経験を有する。『持たざる経営の虚実』『宅配がなくなる日』『時間資本主義の時代』(いずれも日本経済新聞出版)など著書多数。
株式会社YCP Japan 代表取締役
東京大学経済学部卒。野村総合研究所やUBS証券で小売・流通セクターの証券アナリストとして活動後、産業再生機構を経て、独立系コンサルティング会社を共同創業し、東証プライム上場企業へと成長させた。2025年1月より現職。カネボウ、ダイエー、アルピコホールディングスなど、再建案件を中心に10社以上の取締役に就任した経験を有する。『持たざる経営の虚実』『宅配がなくなる日』『時間資本主義の時代』(いずれも日本経済新聞出版)など著書多数。
本書の要点
- 要点1コングロマリットは、株価やビジネスを押し下げるようなディスカウント要因ではない。不確実性が増す現在は、むしろ株価や業容を押し上げるプレミアム要因である。
- 要点2バブル崩壊後の日本の経営者は利益減少を恐れ、設備投資を過少にし、人件費を必要最小限にした。今後の日本企業は、売上高伸長の戦略を強化すべきである。
- 要点3アメリカでも欧州でも、コングロマリットが経済を牽引している。
- 要点4日本企業は「選択と集中」をやめ、積極的に多角化を推進するべきだ。
要約
なぜバフェットは日本の商社に本格投資したのか
投資の神様が認めた「日本型コングロマリット」
2020年8月31日、“投資の神様”ウォーレン・バフェットによる日本の商社株投資が報じられた。自身の投資会社「バークシャー・ハザウェイ」が、関東財務局に複数の大量保有報告書を提出したのである。バフェットは子会社を通じて、五大商社株(三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅)の発行済み株式の5%超を取得した。
これまで日本では、商社のビジネスモデルは評判が芳しくなかった。事業があまりにも多岐にわたり、外部から見てわかりにくいというのがその理由である。株価もその影響で割安に放置されている(コングロマリットディスカウント)と言われてきた。
ところが、バフェットは、日本の商社が「世界中で合弁会社を作っている」ことを高く評価し、それらが「将来、相互に理解をもたらす機会があると望んでいる」とコメントした。つまり、コングロマリットや多角化に将来性を見出しているということだ。
バフェットの投資は「商社株は価値がある」というシグナルと受け取られ、他の投資家たちも商社投資を再評価し始めた。実際、商社の代表的企業、三菱商事の株価はバフェットによる投資が明らかになってから、4倍以上に跳ね上がった。
「コングロマリット」とは何か
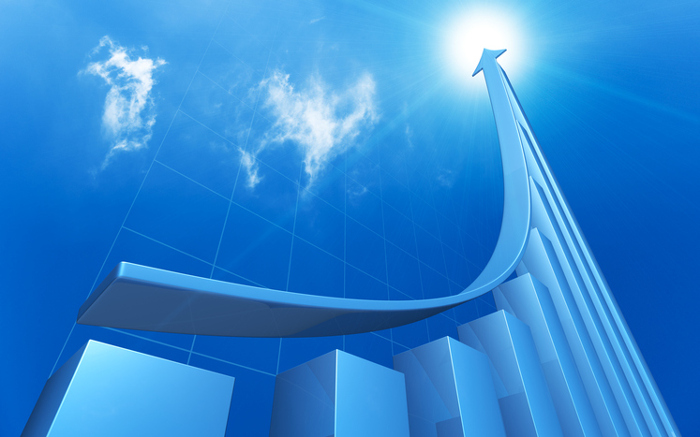
2ndpic/gettyimages
「コングロマリット」とは、複数の異なる事業を抱える企業を指す経済用語である。日本語訳にすると「複合企業体」となる。
混同されやすいものに「コンツェルン」があるが、これは子会社・グループ会社を通じて、「同一産業の独占」を目的とした企業グループのことである。一方、コングロマリットは「複数の異なる事業」を所有することで、事業リスクの分散や収益の安定化を可能とする仕組みだ。総合商社、総合小売、総合電機など「総合」と付くものは、すべてコングロマリットの一種である。

この続きを見るには...
残り3758/4538文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.09.20
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約