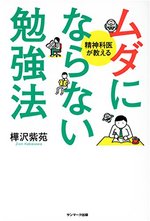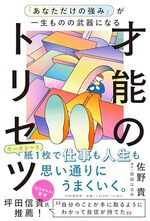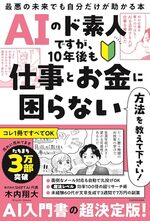読書脳
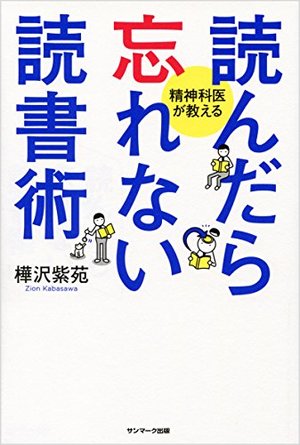
読書脳
著者
著者
樺沢紫苑(かばさわ しおん)
精神科医、作家。1965年札幌生まれ。札幌医科大学医学部卒。2004年から米国シカゴのイリノイ大学精神科に3年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。「情報発信によるメンタル疾患の予防」をビジョンとし、YouTube(62万人)、X(26万人)、メールマガジン(12万人)など累計100万フォロワーに情報発信をしている。著書55冊、累計発行部数260万部のベストセラー作家。シリーズ累計100万部突破の『アウトプット大全』(サンクチュアリ出版)をはじめ、『記憶脳』、『勉強脳』(サンマーク出版)、『神・時間術』(大和書房)、『ストレスフリー超大全』(ダイヤモンド社)など話題書多数。
精神科医、作家。1965年札幌生まれ。札幌医科大学医学部卒。2004年から米国シカゴのイリノイ大学精神科に3年間留学。帰国後、樺沢心理学研究所を設立。「情報発信によるメンタル疾患の予防」をビジョンとし、YouTube(62万人)、X(26万人)、メールマガジン(12万人)など累計100万フォロワーに情報発信をしている。著書55冊、累計発行部数260万部のベストセラー作家。シリーズ累計100万部突破の『アウトプット大全』(サンクチュアリ出版)をはじめ、『記憶脳』、『勉強脳』(サンマーク出版)、『神・時間術』(大和書房)、『ストレスフリー超大全』(ダイヤモンド社)など話題書多数。
本書の要点
- 要点1読書の目的は「自己成長」であり、そのためには、内容を記憶し、知識として定着させる必要がある。
- 要点2「何度もアウトプットされる情報」と「心が動いた出来事」は記憶されやすい。
- 要点315分程度のスキマ時間を繰り返し活用することで、記憶力の高い状態での読書時間を確保できる。
- 要点4「議論できる水準」になるまで理解するように「深く読む」ことが、読書の必要条件である。
- 要点5「好きな著者」に会い、その人となりを知ることで、本の内容をより深く理解できるようになる。
要約
なぜ読書は必要なのか
「結晶化された知識」を得られるのが本
ネット、テレビ、新聞、雑誌、週刊誌などで得られる内容の大部分は「情報」である。一方、著者が情報を分析し、整理し、体系化してくれている「本」から得られるのは、「知識」である。「情報」は「事実」「結果」「事象」であり、1年たったら古くなるが、「知識」はそれらの積み重ねから得られる「エッセンス」であるため、10年たっても古くならない。つまり、実践可能、応用可能で、10年たっても風化することのない「結晶化された知識」を得られるのが「本」である。
読書によって得られること
読書により、先人の試行錯誤の結果を参考にして、その知恵を借用することが可能になるため、時間の無駄を減らすことができるし、自分一人では乗り越えられない壁も乗り越えることができる。仕事力を高め、人生の選択肢を増やし、心配や悩みを解消することができるのだ。さらには、文章力を高めることや、脳を鍛えることもできる。読書により、脳が活性化し、脳のパフォーマンスが高まることや、言語情報に触れると不安が解消されることが、脳科学研究により示されている。
読書の最終目的は「自己成長」だが、読書の動機は「楽しいから」

jovan_epn/gettyimages
「考え方」だけでなく実際に自分の「行動」が変化し、自分をとりまく現実が少しでも良くなるような読書をすべきである。1週間前に読んだ本なのに、人に内容を説明できないような読み方では、「自己成長」することは不可能である。本書の目的は「読書脳」を身につけることで、自己成長を加速させ、あなたの現実を変えることである。
ただし、読書の動機は「楽しいから」であって、「自己成長のため」であってはならない。「自己成長のため」が動機の場合、結果は1、2ヶ月では出ないため逆にストレスになってしまい、記憶を強化する脳内物質ドーパミンは分泌されない。ただ楽しみながら読むだけで、ドーパミンが分泌されて、記憶にも残り、自己成長につながるのである。
精神科医の読書術、3つの基本原則
記憶に残る読書術
「何度も利用される情報」と「心が動いた出来事」は忘れにくい。脳科学的には、「最初のインプットから7~10日以内に3~4回アウトプットする」というのが最も効果的な記憶術である。私が行っているアウトプットは次の4つであるが、1週間以内にその中の3つを行えば、行わないときと比べて圧倒的に記憶に残る。
1.本を読みながら、メモをとる、マーカーでラインを引く。
2.本の内容を人に話す。本を人に勧める。
3.本の感想や気づき、名言をFacebookやX(旧Twitter)でシェアする。
4.Facebookやメルマガに書評、レビューを書く。
心が動いた出来事が強烈に記憶されるのは、喜怒哀楽にともなって、記憶力を増強する脳内物質が大量に分泌されるからである。記憶力のアップが科学的なデータにより確認されている脳内物質には、不安、恐怖にともなって分泌されるアドレナリン・ノルアドレナリン、ワクワクしたときに分泌されるドーパミン、最高の幸福感に包まれたときに分泌されるエンドルフィン、愛情やスキンシップに関連して分泌されるオキシトシンなどがある。これらを意識的に分泌させることで、本の内容を鮮烈に、そして長期間記憶することができる。
スキマ時間読書術
ほとんどのサラリーマンは、通勤時間、移動時間、約束の待ち時間などを合計すると、1日2時間、1ヶ月で60時間程度のスキマ時間があるはずだ。これを読書に使えば、読書のスピードが遅い人でも、月10冊は読むことが可能である。著者は、電車の待ち時間も、ランチで食事が出てくるまでの待ち時間も、本を出して読書をするという。座れる場所ではノートパソコンを開いて仕事をするが、立っている場所ではほぼ読書している。
また、「今日1日でこの本を読む!」と目標設定をして、制限時間を決めることで、緊迫感が出るので集中力が高まり、ドーパミンやノルアドレナリンなど記憶に関係する脳内物質が分泌され、読んだ内容が記憶に残りやすくなる。
深読のススメ

miniseries/gettyimages
本から学びと気づきを得て、「議論できる水準」にまで内容をきちんと理解するように「深く読む」読み方に、「深読(しんどく)」という新しい言葉を使うことを提案したい。飲み会で1冊の本についてみんなで10~20分話して、大いに盛り上がることができるのなら、「議論できる水準」といってよいだろう。「感想や意見を述べられない」ということは、言い換えると「アウトプットできない」、「自分の行動に影響を及ぼさない」ということであり、本を読んでいる意味がない。つまり、「深読」は読書の必要条件である。「深読」できるようになってから、「速読」「多読」を目指せばいい。
【必読ポイント!】 精神科医の読書術、2つのキーワード
本を読みながらアウトプットせよ
本を読みながら、「気に入った一節に蛍光マーカーでラインを引く」「気づきや疑問点をボールペンで本の余白にドンドン書き込みをする」ことで、最初のアウトプットを同時にしていく。脳の中で「字を読む作業」と「手にペンを持って線を引く作業」は全く別の領域で行われており、お互いに連携し共同作業を行うため、ラインを引くことで間違いなく脳が活性化されるのである。
重要なことでも、自分が既に知っていること、自分にとって「当たり前」のことは、ラインを引かず、「自己成長につながる新しい発見」や「自己成長に役立ちそうな言葉」があれば、どんどんラインを引いていく。また、最も簡単なアウトプットは「話す」「勧める」である。その際、「おもしろい」「ためになった」を連呼してもだめで、具体的にどこがためになったのか、本の内容を要約しながら、相手に伝えることが重要である。
スキマ時間を活用せよ
15分という時間は、脳科学的に見ても「極めて集中した仕事ができる時間のブロック」である。高い集中力が維持できる限界が15分、普通の集中力が維持できる限界が45分といわれている。また、何かの作業を行う場合、その集中力は、初めと終わりで特に強くなることが知られており、心理学ではそれぞれ「初頭努力」「終末努力」と呼ばれている。
15分で本を読むと、「初頭努力」で5分、「終末努力」で5分の合計10分、これを4回繰り返すと、60分中40分までもが「記憶力の高い状態での読書時間」になる。一方で60分連続の読書をすると、「初頭努力」で5分、「終末努力」で5分の合計10分しか「記憶力の高い状態での読書時間」がないことになる。「15分程度のスキマ時間読書」の繰り返しでも、連続読書以上の効果が得られるのである。
寝る前の読書もお勧め

bee32/gettyimages
スキマ時間以外に読書の時間を確保するとすれば、「寝る前」がお勧めである。ある研究では、睡眠前の読書は、音楽鑑賞やその他のリラックス法と比べても、最も高いリラックス効果が得られると報告されている。また、寝る前に勉強すると、寝ている間には新しいインプットがなされないので、「記憶の衝突」が起こらず、頭の中の整理が進み、記憶しやすいといわれている。
湯川秀樹やエジソンなども、「次に目が覚めたときには、問題の解決方法を思いついている」と深く念じて眠りにつくと朝にひらめきが起きやすいという「追想法」を活用していたといわれている。読書に限らず、寝る前に情報のインプットをしたり、懸案事項についての書類や資料などに目を通しておいたりすると、朝起きたときに意外な着想を得ることができる。
精神科医の読書術 超実践編
まず目的地を把握する
本を読み始める前に、「目的地」と「行き方」を決めるために、パラパラ読みをする。つまり、全体を把握して、その本を読む目的を設定し、「速読」で読むか「精読」で読むかを決めるのである。それにより、本を読む速さもアップし、その本からの学習効果も高まる。また「この本から何を学びたいか」が明確になっている場合は、知りたいことが何章に書かれているのか目星をつけて、その「結論」が書かれていそうなところに、いきなりワープするような読み方がお勧めである。そのページを読んでさらに知りたいと感じたところ、深掘りしたいところ、疑問に感じたところがあれば、再度目次などで目星をつけて、そのページにワープして読んでいく。ここまで5分もかからない。最初の5分は記憶に残りやすいので、本の最も重要な部分が忘れにくくなる。まず、ワクワクするような自分の知的好奇心を先に満たすことでドーパミンが分泌され、記憶に残りやすくなるのだ。
「ギリギリ」「ワクワク」を活かす
人間の脳は、「自分の能力よりも少し難しい課題」に取り組んでいるときに、最も活性化する。読書の難易度は、「本の内容」と「本を読むスピード」について設定できるので、ビジネス書や実用書を読む場合は、適度にタイムプレッシャーをかけて、「ギリギリ」の難易度に調整することで、記憶と学びを最大化できる。先述のようにドーパミンは「目標設定する」ことで分泌されるが、さらに「適切な難易度」にすることで、よりたくさん分泌されるのである。
また、ワクワク感に包まれて本を買ったのに、1週間たってから改めて読もうと思ったら、ワクワクしないという経験はないだろうか。1週間後には、もう興味、関心が失われている、つまり、ドーパミンが出ていないのである。「おもしろそう!」と思って本を買ったなら、買った直後からすぐに読み始めるべきである。
著者に会いに行って勉強する

miya227/gettyimages
「好きな著者」ができたなら、セミナーや講演会に参加し、その著者に直接会うのがお勧めである。直接会うことで、言葉を超えた理解、心と心の対話が可能になり、本の内容を何倍も深く理解できるようになるし、「著者の人となり」を理解できるようになる。そして、その著者をより「好き」になるはずである。
「読書」というのはインプットの入り口であり、その著者からの学びの入り口でもある。好きな本をたくさん読み、講演会に参加して著者に会う中で、「自分もこんな人になりたい」という敬意が生まれてくる。そうなると、「好きな著者」からあなたの「メンター」になるかもしれない。メンターに何度も会うと、実際に自分もメンターに近づいていく。それは心理学でいうところの「モデリング」である。尊敬する人の本を読むだけでも「モデリング」は起こるが、実際に「会う」ことによって、その「モデリング」の効果は何十倍にも高まる。

この続きを見るには...
残り0/4253文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.08.08
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約