「成長実感」のない会社は「選ばれる会社」になれない人事プロフェッショナルに聞く、「自律型人材が育つ企業」の共通項
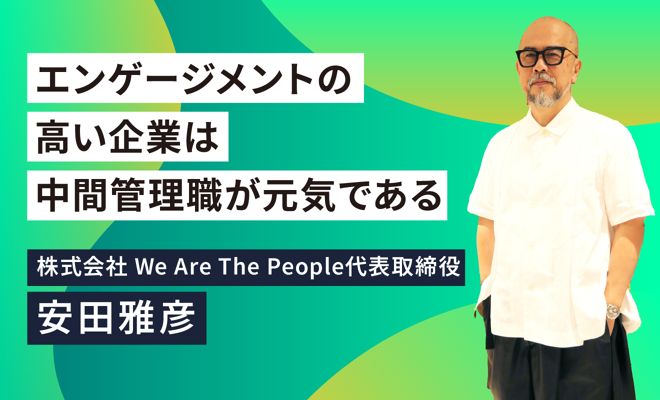
ジョンソン・エンド・ジョンソンなどの外資系企業の人事職を経て、ラッシュジャパンで人事統括責任者を務めてきた安田雅彦さん。2021年に株式会社 We Are The Peopleを起業し、さまざまな経営者や人事の課題に寄り添ってきました。そんな安田さんは2024年7月、株式会社フライヤーの社外取締役に就任されました。
今回は、「自律型人材育成」が進まない企業の真の課題とその解決策をお聞きします。
「コミュニティ・ラーニング」に可能性を感じた
── 安田さんがフライヤーの社外取締役に就任されるにあたっての想いを聞かせていただけますか。
社外取締役就任をお受けしたいと思ったのは、人と組織に約30年間関わってきた経験が、フライヤーのよりよいサービス提供にあたって活きるのではないかと思ったためです。もともとフライヤーとの出会いは、僕がラッシュジャパンの人事統括責任者をやめて、自身の会社(株式会社 We Are The People)に専念する頃でした。読書コミュニティflier book laboの講師として関わるなかで、「コミュニティ・ラーニング」という概念に初めてふれ、大きな可能性を感じていたんです。
社内研修教育というと、階層別研修に代表されるように、似た属性の人が一方的に受講させられるような意味合いがあります。一方、コミュニティ・ラーニングは、属性を問わず自ら学ぶ意志のある人が集まってともに学んでいくという、内発的な動機に根差したスタイルです。「学ぶ人の意志」がしっかりあるため、学びの効果が断然違うと実感しました。
さらに、flier book laboにとどまらず、フライヤーのサービス全体が自律的な学びや成長を促そうとしているのが伝わってきました。特に2024年5月にリリースされたflier成長組織ナビは、組織の成長の可視化だけでなく、働く人の成長実感を高める仕組みづくりにフォーカスしていて、よいプロダクトだなと思っていますね。
これまで人事の方の話を聞くなかで、従業員が抱く不満は主に次の3つに集約されていると考えています。それは「給与に不満があること」「経営のビジョンが見えないこと」「成長実感が得られないこと」。このうち3つめの成長実感は非常に大事です。なぜなら、ビジネスを通じて世の中に価値を提供するという本質を追求している企業はみな、従業員が成長実感を得られ、エンゲージメントが高いからです。
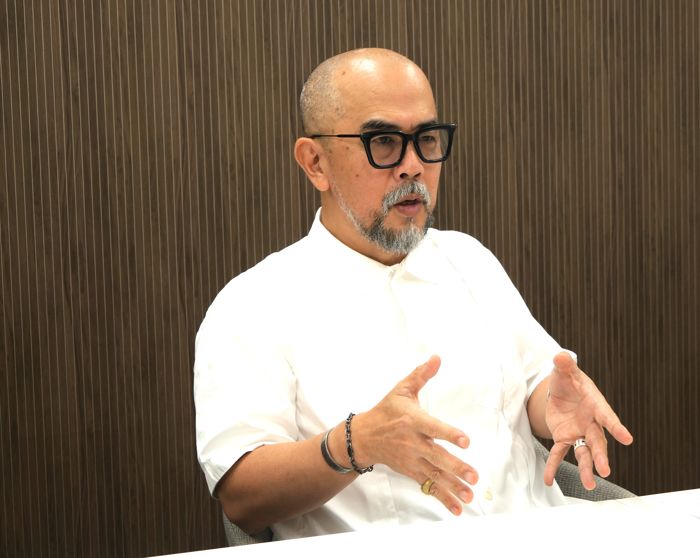
なぜ、社員の「成長実感」がますます重要になるのか?
── 成長実感を持てない企業の課題の本質は何だとお考えですか。
課題は、マネジメントの概念が日本企業にきちんと浸透していないこと。本来、人的資本経営は組織にとって当たり前の概念です。人を「駒」ではなく「資本」とみなし、その力を活かしてビジネスの成長と価値創出を図ることは、松下幸之助さんが経営されていた時代から大事といわれてきました。
にもかかわらず、最近になって人的資本経営が声高に叫ばれているのは、日本企業の多くがそれを実践できていなかったから。たとえば人事異動は、適切なリソース配分の一環であって、人材育成の名目は後づけです。本人が嫌な仕事でも、家族と離れて転勤することになっても、命じられた部署で働くことになる。これが成立していたのは、終身雇用と年功序列制度が機能していたから。社員には「やがては出世するし、定年後は退職金がもらえて辻褄があう。だからいまは頑張れ」などと我慢を強いることができた。ところが、いまや一社で定年まで勤め上げようと決めている社員は数少なく、こうしたロジックは通用しなくなっています。
そうなると、社員がいまこの瞬間に、目の前の仕事に夢中になれるか、仕事が生み出す価値に共感できるかどうかが、ますます重要になるのです。「自社のビジネスが成長したら、こんな景色が見られるし、こんな価値を世の中にもたらすことができる」という、企業のビジョンやパーパス(存在意義)を提示できてはじめて、社員に「選ばれる会社」になります。

「自律型人材の育成」が進まない真の課題とは?
── 人的資本経営とその可視化が重要性を増すなか、人事の方が「自律型人材の育成」「学びの組織文化づくり」を進めるうえでの課題は何でしょうか。
課題は主に2つあります。1つめは、経営陣と人事とで、人材育成の現状に対する解像度にギャップがあること。人事の方からはこんな相談をよく受けます。「従業員のエンゲージメント向上にバリューの浸透が必要だと経営陣に説得するためにアドバイスがほしい」というのです。これは、経営陣が課題の切迫感を認識できていないことの現れです。この認識のすり合わせに対しては、flier成長組織ナビが、組織の理想と現状のギャップを可視化し、そこに対処する必要性を伝える解決策になるのでは、と感じています。
もう1つの課題は、人事施策を主導する現場の中間管理職に元気がないこと。「管理職は罰ゲーム」といわれるほど、めざす人も少ないのが現状です。そんななか、いかにして中間管理職が高いエンゲージメントを保てるようにするかは、日本企業の重要な課題になっています。

中間管理職のエンゲージメント向上と育成がカギ
── 中間管理職が高いエンゲージメントを保ち、実績を出している企業の共通項はありますか。
共通項は、マネージャーに適切な責任と権限を与え、マネージャーの処遇をよくしているという点です。日本企業では、マネージャーとそうでない人を「役割の違い」だとし、マネージャーの地位を下げる風潮があります。さらには、部下のいない専門職とほぼ同じ待遇ということさえある。こうした状態では、誰も部下のマネジメントなどというハードルが高い職務を避けるようになり、結果的に組織全体のマネジメント能力が下がってしまいます。
まずは、マネージャーの処遇をよくすること。ただし、マネージャーも適性を毎年評価され、2、3年後も成果を出せなかったら役職からはずされる――。そうしたフェアな状況をつくることが必要です。そのためには、自社のマネージャーがどんな役割を果たすべきかを明確に打ち出し、評価と結びつけることが欠かせません。
中間管理職は、上司にあたる上級管理職から質の高い1on1やフィードバックをきちんと受けないといけません。僕は、トップマネジメントのコミュニケーションの質こそが、その企業における「マネジメントの学校」と呼べるほど高いものであるべきだと常々思っています。社長と副社長、社長と執行役員の間でも1on1やフィードバックは必要ですし、むしろ上位層になるほどマネジメントの質が高く求められるべきです。
── 社員の学び続ける意欲が育つのを促すために、人事や中間管理職に求められる役割とは何でしょうか。
人事の方からは「育成の手ごたえがない」という悩みを聞きます。社員が真剣に学び、それを現場で活かせているのか、不安を抱えているのです。それに対して人事に求められる役割は、企業と個人とで、研修などの学びの機会が「何のためにあるのか」を合意できているようにすることです。
組織は、パーパスという存在意義に基づいて、世の中に価値を創出する存在です。そのために組織として必要な能力やスキルのうち、足りないものを補うために、社員が一人ひとり成長する必要があります。社員の成長をドライブするためには、「自社のビジネスを通じてこんなことを実現したい、だからこの部分で成長していこう」などと、個人の実現したいことと組織のパーパスとの重なりを思い描けていないといけない。だからこそ、企業は将来どんなビジョンを実現したいのかを日頃から発信し、それと矛盾のないビジネスを展開することが求められます。
私がいたジョンソン・エンド・ジョンソンもラッシュジャパンも、組織としての行動指針が徹底され、あらゆる意思決定と紐づいていました。いずれの企業も、長い歴史を経て、自社の価値観に対する社員の共通理解こそがビジネスの成長に重要だと心得ていました。
たとえばジョンソン・エンド・ジョンソンでは、個々人がクレド(信条)に沿って行動しているか、チーム内にクレドが浸透しているかが定点観測されていた。もちろん、リーダーたちも、クレドが自分たちの仕事に反映できているかどうかの議論には、労力を惜しみませんでした。こうしてクレドが判断の拠りどころになっていると、社員は迷いがなくなり、自律的に行動できるんです。

まず、フライヤーの社員がミッションを体現しようとしているか?
── flier businessも社員の方々が自律的に学べるよう、自らの興味をもとに本の要約を通じて世界を広げてほしい、という願いのもとに生まれたサービスです。導入した企業さまが、さらに意義を感じてもらうために、どんなことができるとお考えですか。期待している点を教えてください。
期待するのは、フライヤーが自分たちの掲げるミッションの領域において最先端をいく企業になることです。フライヤーのミッションステートメントには、こんな一節があります。「ヒラメキがさまざまな場で生まれ、互いに影響し合うことでイノベーションが生まれる。フライヤーはその背中を押すサービスをめざしていく」。フライヤー内でもヒラメキがさまざまな場で生まれて、社員同士が互いに影響し合ってイノベーションをめざしているのか。「この分野においては、私たちは日本一」と言い切れるかだと思うんですね。
ラッシュの時代に知って大好きになった言葉に、「ブランドは人がつくる」というものがあります。フライヤーのブランドバリューを高めることは社外取締役の責務でもありますが、ブランドバリューとは、まさに働く一人ひとりなんですね。だから、フライヤーの社員が「ヒラメキ溢れる世界をつくる」というミッションに心から共感し、そのミッションを体現しようとしているかが問われます。
「ディレクション」ではなく「インスピレーション」を
── ヒラメキを生み出したいという思いで働いていても、はたして「自分が体現できているか」と問われると自信を持ち切れていない社員には、どんな関わりをしていくとよいですか。
インスピレーションを与える機会を増やすことです。社員がブランドバリューを体現する人材であるために、会社がとにかくインスパイアすることが大事だと思います。
たとえばラッシュジャパンでは、年に4回グローバルショップマネージャーミーティングが開催され、全世界980店舗もの店長を全員イギリスに集めていました。ラッシュはお客様への価値を訴求する場として店舗を一番大事にしているので、それを率いる店長たちにインスピレーションを与えることを重視してきた。その場では、ラッシュがめざすオーガニックとは何か、世の中のどんな社会課題解決に寄与していきたいか、といったテーマが話されるんです。これは特殊な例かもしれません。でも、決して「こう考えなさい、こうしなさい」とディレクション(指示)を与えるのではなく、「自分たちのブランドバリューとは何か」を問うようなインスピレーションを与えることで、社員は自らその問いに向き合うようになります。
フライヤーには、色々な挑戦をしてほしいと思うんですよ。ラッシュでは「境界線に挑む」という言葉が飛び交っていました。それは前例のない領域を開拓していくこと、最先端をいくことだと捉えています。
マーケットよりも先を行き、固定観念にとらわれず、ヒラメキを次々に形にしていき挑戦を楽しんでいく。それを一人ひとりが実践していれば、自然とそのブランドバリューが戦略にもプロダクトにもにじみ出るはずです。

安田 雅彦(やすだ まさひこ)
1989年に南山大学卒業後、西友にて人事採用・教育訓練を担当、子会社出向の後に同社を退社し、2001年よりグッチグループジャパン(現ケリングジャパン)にて人事企画・能力開発・事業部担当人事など人事部門全般を経験。2008年からはジョンソン・エンド・ジョンソンにてHR Business Partnerを務め、組織人事やTalent Managementのフレーム運用、M&Aなどをリードした。2013年にアストラゼネカへ転じた後に、2015年からラッシュジャパンの人事統括責任者 Head of Peopleに就任。2021年7月末に同社を退社し、人事・組織コンサルティング事業を主とする株式会社 We Are The People ( https://wearethepeople.jp )を起業。2024年7月より株式会社フライヤーの社外取締役に就任。

