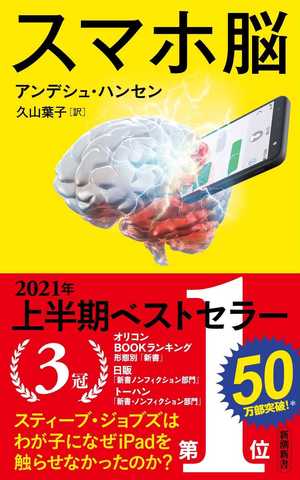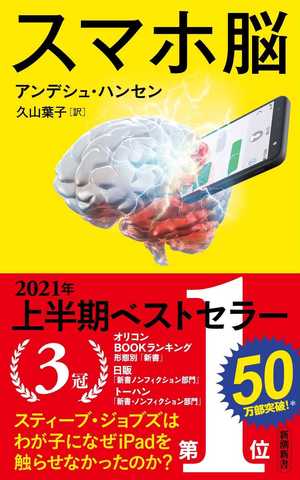【書店員のイチオシ】その中毒性、知ってますか? 『スマホ脳』【ブックスタマのイチオシ】
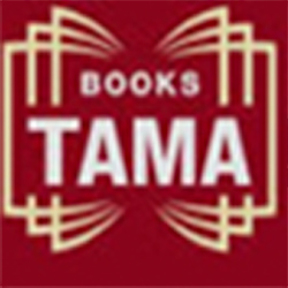
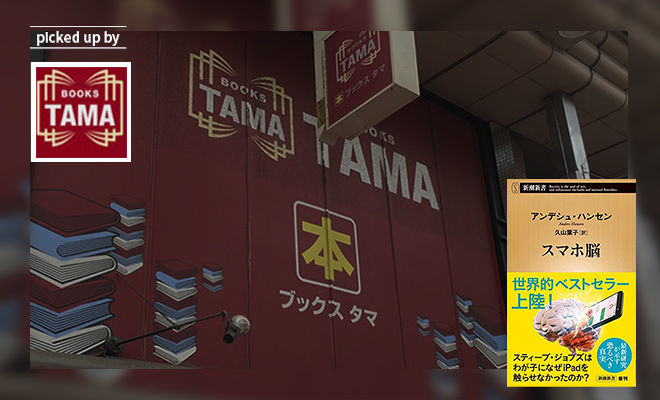
ネット社会になって本離れが進んだと言われていますが実際は考えられているほど本を読む人は減っていないと思います。書店が減っているのは、どちらかというと雑誌が売れなくなった影響が大きいです。
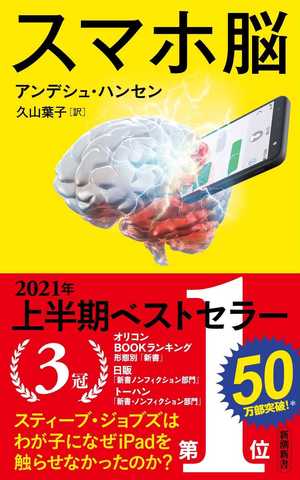
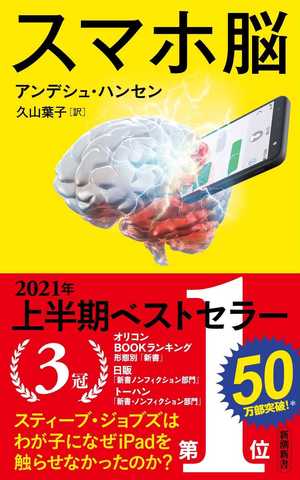
しかし、教科書が100%デジタル化されたら、本当に本を読む人が激減するかも知れません。デジタル教科書の何が問題なのか、この本に書かれています。スマホには中毒性があって、長時間使う割には、ひとつのことを集中して考える時間は短いです。長期記憶を養成するには脳が学ぶことに集中する必要があって、紙に書かれたもので学んだ方が、デジタルデバイスよりずっと集中できるそうです。 スマホを使われたことのある方なら、実感されているのではないでしょうか。
人間は10万年前にサバンナで生き残るために必要だった性質を、今でも引き継いでいるのだそうです。原始時代には人類は栄養のある甘い木の実を見つけた時は、脳にドーパミンが分泌され、その実を食べれるだけ食べて、食料が手に入らない時のために備えていました。現代社会は食べ物にあふれていて、飢えるようなことはありませんが、それでも人間は昔の習性を引きずっていて、カロリーの高い食品を食べすぎてしまい、肥満になってしまうのです。
スマホに中毒性があるのも同じ理屈で、原始時代には人類は常に危険に囲まれていたのでいろいろなことに注意を払わなくてはならなかったので、新しいことを学ぶと脳にドーパミンが分泌されるように進化しました。スマホのプッシュ機能やメールの着信音は、人間にとっては新たな変化として認識され、ドーパミンを分泌させ、快感に感じられるようになったのです。
中毒性のほかに特筆すべきは、スマホとうつの関係性です。デジタルデバイスはストレス状態を長期間持続させるので、世界各地でうつとの関連性が指摘されています。スマホによって脳が興奮状態になると、睡眠不足になり、記憶の長期保存にも支障をきたします。
スティーブ・ジョブズをはじめとするIT企業のトップは、子供にスマホを触らせる時間を制限しているといいます。デジタルデバイスに精通する彼らがなぜ子供にその使用を制限させるのか、この本を読むと理解できると思います。デジタル教科書の是非を議論する上で、多くの人に読んでいただきたい本です。