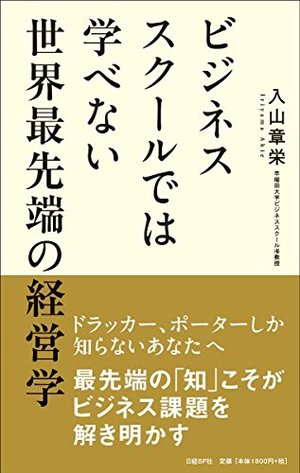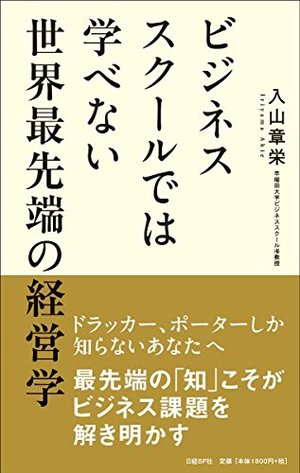世界最先端の経営理論に迫るドラッカー、ポーターだけじゃない!

今回登場するのは、2015年12月に『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』(日経BP社)を上梓された入山 章栄さん。 三菱総合研究所を経て、米ピッツバーグ大学経営大学院の博士号を取得し、米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールのアシスタント・プロフェッサーに就任。2013年から早稲田大学ビジネススクール准教授を務めておられます。 著書『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)がベストセラーとなり、現在は『ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー』誌にて「世界標準の経営理論」を連載中。 世界標準かつ最先端の経営学の知見をビジネスパーソンに伝える第一人者の入山さん。ビジネスパーソンに役立つ経営理論や注目テーマ、そして入山さんの愛読書についてお話を伺いました。
ビジネスパーソンの課題解決で、世界最先端の経営理論がヒントになる
── 入山さんは著書を通じて最先端の経営学の知見をビジネスパーソンに伝えていらっしゃいますが、そういうことをされている日本の経営学者は意外に少ないですよね。こうした方向へ進まれたきっかけは何でしたか。
入山 章栄さん(以下、入山):日本の経営学は、良くも悪くも海外から閉じられているんですよね。日本の経営学者はとても優秀だと思うのです。ただ、国際学会に出て行って、そこでトップジャーナルに論文を載せるという方が多くないのが現状です。したがって、なかなか海外の経営学の先端の知見が日本に入ってきません。一方でアメリカなど欧米の経営学たちも問題があると私は思っていて、学者たちは研究者としては一流なのですが、逆に言えばまさに研究一筋で、名だたる学会誌への論文の寄稿に忙殺されてすぎています。結果として、ビジネスパーソンへその知見が還元されないのです。
たとえば、アカデミックの世界では超有名なコロンビア大学のブルース・コグートなどが発展させたリアル・オプション戦略も、日本ではあまり認知されていません。日本の経営者やビジネスパーソンも、最先端の経営学の知見にある程度ふれておけば、ビジネスの課題を解決するヒントが得られるかもしれません。「世界最先端の経営学の理論を日本に伝えないともったいない」と考えるようになったのです。
そこで3年前、日本で知られていない世界の経営学の知見を紹介しようと、『世界の経営学者はいま何を考えているのか』を上梓するに至りました。


── 『世界の経営学者はいま何を考えているのか』を読んで、アメリカと日本の経営学のとらえ方の違いに驚きました。今回、『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』を執筆された経緯はどういうものだったのでしょうか。
入山:帰国後、早稲田大学ビジネススクールで教鞭をとるようになり、様々な分野の第一線で活躍する経営者やビジネスパーソンにお会いする中で、「イノベーションにつながるアイデアを生みだす組織のつくり方がわからない」「ダイバーシティが組織に浸透しない」といった、彼らが現実に悩んでいることが見えてきました。中にはビジネス書でドラッカーやポーターと言った既存の経営学を学んでいる方もいるのですが、それだけでは目の前の壁を打破できていないのです。彼らの悩みを解決に至るはかわかりませんが、その考えを助ける「思考の軸」という位置づけで、世界の経営学の研究成果を伝えられないかと考えたのです。
ちょうどその頃、日経ビジネスオンラインで連載していた記事に、予想外に大きな反響をいただくことが何度もありました。「世界の経営学者はドラッカーを読まない」などと書いたら、これがセンセーショナルだったようです。連載は最初の数回で終える予定でしたが、編集から「これだけ人気があるのだし、ぜひ続けてください!」と言われ、想像以上の長期連載になりました。こうした記事の集大成として、『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』の書籍化が実現したんです。
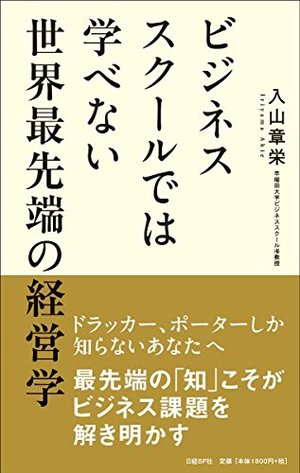
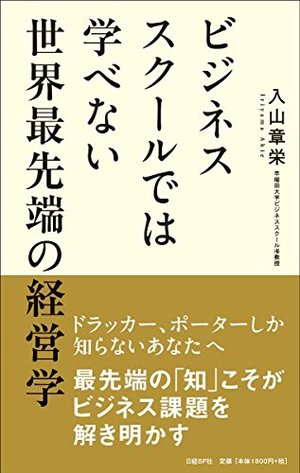
入山:私は幸いなことに、学者の仕事も、メディアでの連載も対談も、好きな仕事ばかりさせてもらっています。特に経営者の方々との対談は本当に勉強になります。色々な経験や苦労を乗り越えて今の地位を築かれた経営者ばかりだから、おっしゃっている言葉の重みが違うんですよね。彼らの経営の現場に即した経験則が、経営学の研究成果ともあっていることも多く、新たな発見を得られるのが非常に面白いですね。
正直なところ、私の場合、連載や本を執筆しているのも、人の役に立ちたいというよりは、純粋に「興味があることを知りたい・表現したい」という思いのほうが強いです。もちろん読者から「あの記事が面白かった、役に立った」などと感想をいただくと嬉しいのですが、自分自身が興味のあること、面白いと感じることを発信するのが好きなんでしょうね。
日本のダイバーシティ議論は的外れ?!
── 『ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学』では、「『チャラ男』と『根回しオヤジ』こそが最強のコンビである」、「組織の学習力を高めるには、『タバコ部屋』が欠かせない」など、目から鱗なテーマの連続でした。こうしたテーマをどのように選ばれたのですか。
入山:「ダイバーシティ」とか「リーダーシップ」とか、日本のビジネスパーソンが関心を持っていて、かつバズワードになっているテーマをあえて選びました。
このネタ探しが、なかなか大変で。経営学の知見を紹介するからには、まさに「目から鱗」感がないと読んでもらえないですよね。そこで、ビジネスパーソンがこれまで考えたことがなかったトピックや、うっすら考えていたことがきちんと言語化され、整理されるようなビジネスのトピックをひねり出し続けたわけです。編集から、「新しいネタはないの?」と叱咤激励されながら(笑)経営学の膨大な論文の中からトピックとマッチする論文を見つけ出すのは苦労しました。
── たしかに想像しただけで尋常でなく大変な印象です。中でも特に入山先生の目を引いたテーマは何でしたか。
入山:例えば、ダイバーシティです。ダイバーシティには、性別、国籍、年齢など目に見える属性が多様化する「デモグラフィー型」と、能力や経験など目に見えない価値が多様化する「タスク型」の二種類があります。経営学の研究によると、タスク型ダイバーシティをもつ組織は、それが組織全体のパフォーマンスにプラスに機能する。しかし、デモグラフィー型ダイバーシティは組織にとってプラスにならないどころか、逆にマイナスの効果をもたらす可能性もあるということがわかっています。今の日本では、デモグラフィー型とタスク型がごちゃまぜになって、「女性管理職を30%にまで引き上げる」などと議論されていますよね。でも、経営学の世界ではすでにどんなダイバーシティが組織にプラスの影響をもたらすかという答えが、ほぼ出ている。この研究成果を活用すれば、真に成果を得られるダイバーシティ経営に近づけるかもしれません。
「経営学は使えない」と言う人がいますが、経営学を学んだからといって実際の経営の「答え」がすぐに見つかるわけはありません。経営学はあくまで、経営を考えるときの「思考の軸」。経営学の知見は、ビジネスで直面する課題を考える際のあくまで一つの軸として使うべきでしょう。
入山さんの「競争しない競争戦略」
── 実際の経営に対する答えではなく、思考の軸ですか。入山さんの本は、経営学に対する見方を変革されたのですね。
入山:変革というほどのことはしていませんが、ビジネスパーソンの経営学に対する見方が、少しずつ変わっていけばいいなと思っています。
私は人と同じことはしたくなくないタイプです。経済学から経営学に移ったのも、欧米で経済学の博士号を取る日本人は多いのですが、当時、経営学ではほとんどいなかったというのが理由の一つです。実は現在も、海外で経営学の博士号を取って教員経験のある日本人が極めて少ないのが現状です。
今となっては、こうしたキャリアがアドバンテージになっていると思います。今後は、世界の先端の経営学に本気で取り組む日本人の研究者がもっと増えていってほしいですね。
── 「人と同じことはしたくない」という考え方は、小さい頃からされていたんですか。
入山:そうですね。競争を避けていたのかもしれませんけどね。早稲田大学ビジネススクールの同僚の山田英夫先生が書かれた『競争しない競争戦略』みたいな。「敵がたくさんいるところで競争するのは勝ち目がないから、なるべく敵がいない分野を探す」。これは競争に勝つための基本の一つですよね。
今思い返してみると、例えば子どもの頃にサッカーをやるときは、必ずゴールキーパーをやっていました。フィールドプレイヤーだと、運動神経がずば抜けて良い子がボールをずっと持っていて、他はボールをほとんどさわれずに終わってしまう。でも、ゴールキーパーは一人しかいないからボールにさわれるし、絶対得点シーンにからむ。おまけにゴールを食い止めたあかつきには、脚光を浴びられるという役回りですよね。こんな風に、「人と違うことがしたい」という感覚は小さい頃からずっとあったように思います。
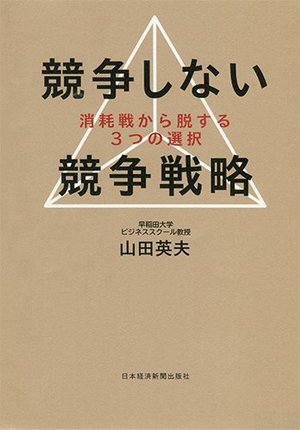
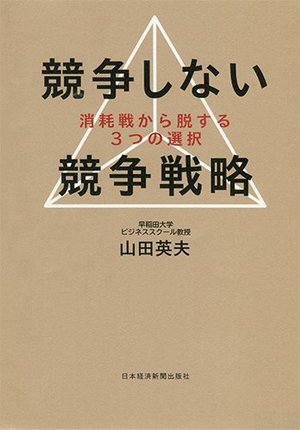
『ハーバード・ビジネス・レビュー』の連載は『HUNTER×HUNTER』のオマージュだった?!
── 入山さんは本もよく読まれていたんですか。
入山:よく読んでいましたね。特に推理小説が好きです。実は、ビジネス書はあまり読まなくて(笑)。もちろん書評を書いたり監訳をしたり対談相手の方のことをリサーチしたりするためには読みますが、それ以外は読まない。「ビジネス書を書いておきながら、何言ってるんだ」とお叱りを受けそうですが……。
あと、ビジネス書を読むときって、脳みそを使うでしょう? 私は読書ではなるべく頭を使いたくないんです。推理小説の読み方も少し変わっていて、途中で推理することはありません。推理小説を読むのは好きなんですが、真犯人が誰かには興味がないんですよね(笑) 例えば、アガサ・クリスティの『オリエント急行殺人事件』とか好きなのですが、ただ小説の世界に流れる雰囲気に浸るのが好きなんですよね。
── それは意外ですね! 他にも好きな推理小説ってありますか。
入山:綾辻行人さんや有栖川有栖さんなどの新本格派ミステリーもよく読みます。本格派の先駆けである、綾辻さんの『十角館の殺人』を読んだときは、本当に衝撃を受けましたね。作者たちは「犯人をあてられるならあててみろ」と挑戦状を読者に突き付けてきますが、僕にとってはそんなのどうでもよくて(笑)
一番気になるのは、最後のどんでん返しが、「いかに予想外か」どうか。誰も想像できないような強烈なオチが用意されていて、「こうきたか!」と予想を裏切られるのが面白いんです。もし食いっぱぐれしないくらいお金に余裕ができたら、学者の仕事を辞めて、推理小説を書いてもいいかもとすら思います。「えっ、あれ全部伏線だったの?」と思われるような小説を書いてみたいなあ。
私にとって、推理小説は気分転換のためのもの。森博嗣さんの『すべてがFになる』や、内田康夫さんの浅見光彦シリーズは素晴らしい。内田康夫さんは天才ですね。まあ、あれをミステリーと言うかは微妙なところですが、でもあんなにリラックスして読めるミステリーを書ける人はなかなかいないでしょう。内田さんは、プロットも最初に決めずに執筆して、途中でふいに犯人や結末が浮かんでくるらしいのです。なんてクレイジーな人だと思いましたね。
── 入山さんが「この人、クレイジーだな」って思うのはどんな方ですか。
入山:漫画『HUNTER×HUNTER』の作者、冨樫義博さんは天才中の天才ですね。おそらく彼はプロットを考えずに描き出し、気づいたらものすごい伏線が張り巡らされていて、頭の中に、極めて完成度の高いストーリーができているんだと思います。中でもキメラアント編は、もはや伝説と言ってよいほどの完成度。
他にすごいなと思うのは、『進撃の巨人』の作者、諫山創さん。彼はきっと私たちの想像を裏切るゴールを最初に決めて描いているのではないかと踏んでいます。緻密に計算して大作を生み出すという点で、冨樫さんとはある意味、真逆な天才でしょう。
実は私が『ハーバード・ビジネス・レビュー』の連載でめざしているのは、『HUNTER×HUNTER』のキメラアント編なんですよ。あの天才的な伏線とカタルシスで読者を唸らせられるような構想に憧れて書いているんです。実際、私の連載でもたとえば第19回目(3月10日発売号)で取り上げた「ダイナミック・ケイパビリティ—」というテーマは、連載で第18回目までに登場した理論を総動員しないとわからない仕掛けになっています。
── そんな構想があったんですね! 19回目を読むのが楽しみです。何より入山さんがこんなに漫画に精通されていることに驚きです。
入山:実は少女漫画もすごく好きなんですよね。少年漫画の連載は週刊誌だから、毎号、人気がないと掲載打ち切りになってしまう。だから毎週「強い敵を倒し続ける」といった展開がどんどん変化するストーリーになりがちです。ですが、少女漫画は月刊誌だから、編集部も比較的長い目で見てくれるので、読みごたえのある大河ドラマの名作が生まれやすい。
一番好きなのは、日渡早紀さんの『ぼくの地球を守って』という作品です。あんなに壮大なスケールで読みごたえのある大河ドラマはなかなかないと思います。水木杏子さん、いがらしゆみこさんの『キャンディ・キャンディ』も傑作。結末にあのどんでん返しが用意されているって、すごいですよね。
つい漫画の話になると熱が入って、止まりません(笑)
── 入山さんのお話を聴いていると、書店の漫画コーナーに駆け込みたくなりました……!(笑)
今、注目のデザイン思考の可能性とは?
── 入山さんは『21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由』の著者、佐宗邦威さんとの対談で、「デザイン思考」に着目されているとおっしゃっていました。その理由は何ですか。
入山:今の経営学は、特定の側面から物事を見て、細かく分解していく「還元主義」に立っています。リーダーシップやダイバーシティといった個々のテーマについては議論されていますが、それらをまとめ上げる経営学の理論はまだ存在していないんですよ。
もちろん、分解して要素を理解することは非常に重要です。「木を見て森を見ず」はダメですが、「木を見ないで森だけ見よう」としても本質は見抜けません。だから、MBAの授業で経営理論や理論に基づいた分析ツールを駆使して、部分を分析したり、それをまとめあげるケーススタディーをすることには意義があると思います。
そのうえで、さらに俯瞰的に森を見る視点を持つために、デザイン思考が有用なツールになるかもしれない、と私は考えています。デザイン思考は、デザイナーが元々ゼロからイチを生み出すために実践していた思考法。リサーチ、分析、統合、プロトタイピングなどのモードを何度も行き来しながら、複数の要素を「一つのデザインとしてまとめあげる」手法です。最近、スタンフォード大学やマサチューセッツ工科大学(MIT)などのビジネススクールとデザインスクールの連携が進んでいるのは、ビジネススクールが「経営のデザイン」を求めるために知を探求していると受け取ることもできます。両者の連携で、「部分の科学」と「全体のデザイン思考」が融合すれば、新たな知見が誕生するかもしれません。今後の動きが楽しみですね。
── 部分を分析する経営学と、全体をまとめ上げるデザイン思考の融合は、大きな可能性を秘めているのですね。貴重なお話をありがとうございました!