好奇心のチカラ
大ヒット映画・ドラマの製作者に学ぶ成功の秘訣
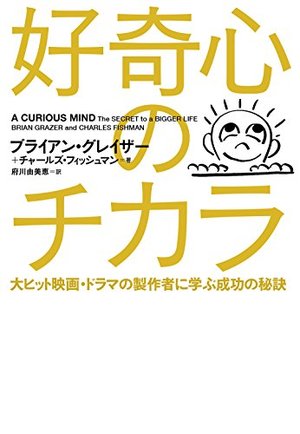
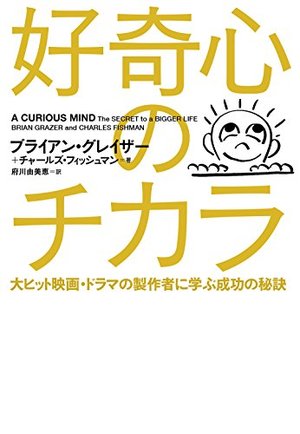
著者
ブライアン・ グレイザー (Brian Grazer)
『ビューティフル・マインド』『アポロ13』『スプラッシュ』『ブル~ス一家は大暴走!』『24 -TWENTY FOUR- 』『8 Miles』『Empire 成功の代償』 『J・エドガー』などのプロデューサー。製作した映画やテレビドラマで、43のアカデミー賞、149のエミー賞にノミネートされている。2007年には、タイム誌の選ぶ世界で最も影響力を持つ100人のひとりに名を連ねた。
チャールズ・ フィッシュマン (Charles Fishman)
『ウォルマートに吞みこまれる世界』(ダイヤモンド社)、『The Big Thirst』などで知られる作家。ビジネス・ジャーナリズムの最高賞とされるジェラルド・ローブ賞を3度受賞している。
府川由美恵(訳)
明星大学通信教育部教育心理コース卒。主な訳に『アイスウィンド・サーガ』シリーズ、『物語の法則』(以上KADOKAWA)、『脳が読みたくなるストーリーの書き方』(フィルムアート社)、『上海ファクター』『黙示』(以上早川書房)など。
『ビューティフル・マインド』『アポロ13』『スプラッシュ』『ブル~ス一家は大暴走!』『24 -TWENTY FOUR- 』『8 Miles』『Empire 成功の代償』 『J・エドガー』などのプロデューサー。製作した映画やテレビドラマで、43のアカデミー賞、149のエミー賞にノミネートされている。2007年には、タイム誌の選ぶ世界で最も影響力を持つ100人のひとりに名を連ねた。
チャールズ・ フィッシュマン (Charles Fishman)
『ウォルマートに吞みこまれる世界』(ダイヤモンド社)、『The Big Thirst』などで知られる作家。ビジネス・ジャーナリズムの最高賞とされるジェラルド・ローブ賞を3度受賞している。
府川由美恵(訳)
明星大学通信教育部教育心理コース卒。主な訳に『アイスウィンド・サーガ』シリーズ、『物語の法則』(以上KADOKAWA)、『脳が読みたくなるストーリーの書き方』(フィルムアート社)、『上海ファクター』『黙示』(以上早川書房)など。
本書の要点
- 要点1拒否されることが多い世の中で自分のしたいことをするには、何年かかっても最後までやりとげる粘り強さが必要だ。粘り強さは好奇心から得られるものの価値を高めてくれる。
- 要点2関係者全員で同じ目的や目標意識をもたなければ物事はうまく進まない。成功するには意識のすり合わせが大切である。
- 要点3指示されるよりも、何をするか自分で選びたいと思うのが人間の性質だ。指示をするのではなく、好奇心をもって質問することのほうが、うまく人をマネジメントできる。
要約
敏腕プロデューサーになるまで
きっかけは好奇心だった
大学を卒業した著者は、ロースクール進学までの長い休みにするアルバイトをどう探そうか考えていた。すると、不意に窓の外から今日付けでワーナー・ブラザーズの法律事務員を辞める人の話が聞こえてきた。
著者がすぐさまオフィスに電話をかけると、翌日の15時に面接に呼ばれた。その面接の15分後には法律事務員のアルバイトとして採用されていた。
世界が開かれた瞬間

Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock
法律事務員としての業務は書類を届けることだった。実働は1日1時間程度なのに8時間の時給がもらえる、簡単だがつまらない仕事だった。だが、書類が1970年代のハリウッドにその名を轟かす大物に宛てたものだと気づいてからは、仕事がおもしろいと感じるようになった。
しかし、当然のことながら、一介の法律事務員がハリウッドの著名人に直接会えるわけがない。たいていの場合は、彼らに雇われたアシスタントやドアマンが書類の受けとり人だったからだ。
著者は、どうにかして大物に会えないかと考えた。そこで、「書類を宛名の人に届けたことを自分で確認しなければならない」という、もっともらしい口実をつけた。すると、アシスタントやドアマンは納得し、部屋の中に入れてくれた。
こうして著者は大物たちと会話ができるようになった。ただ、大物たちと会うからといって、仕事をくれと頼んだりすることはしなかった。意見を聞いたり、将来の仕事についてアドバイスをもらったりするだけだった。
間もなくして、著者はロースクールよりも映画ビジネスの方がおもしろいと思うようになった。結局、著者はロースクールに行くのを辞め、1年間ワーナー・ブラザーズの法律事務員として働くことを選んだ。それがすべての始まりだった。
【必読ポイント!】 好奇心の価値を高める
拒絶されてもめげない精神力を

BrianAJackson/iStock/Thinkstock
28歳になった著者は、人魚が陸に上がったら何が起きるのかということに強く興味を惹かれ、このアイデアを軸に映画のストーリーをつくろうと思った。ところが、共同経営者のロン・ハワードを含めて、誰もがこのアイデア に「ノー」をつきつけてきた。いくら売り込みをしても映画のスポンサーはつかず、相手にもされなかった。
それでも著者は、自分以外の人が何を拒否しているのかを粘り強く考え続けた。辿り着いたのは、

この続きを見るには...
残り3419/4374文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.07.09
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











