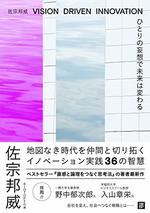うしろめたさの人類学

うしろめたさの人類学
著者
著者
松村圭一郎(まつむら けいいちろう)
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有や分配、貧困と開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『文化人類学 ブックガイドシリーズ基本の30冊』(人文書院)がある。
1975年、熊本生まれ。京都大学総合人間学部卒。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。岡山大学大学院社会文化科学研究科/岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。エチオピアの農村や中東の都市でフィールドワークを続け、富の所有や分配、貧困と開発援助、海外出稼ぎなどについて研究。著書に『所有と分配の人類学』(世界思想社)、『文化人類学 ブックガイドシリーズ基本の30冊』(人文書院)がある。
本書の要点
- 要点1私たち日本人は、感情に振り回されにくい「交換」のモードに慣れ親しむことで、自分より弱い立場の人への共感という「うしろめたさ」を覆い隠している。
- 要点2表向きは境界があるように見える社会も、すべて裏でつながっている。「わたし-あなた」の関係における選択が、やがて経済や感情、国家や社会などのつながりを形づくっていく。
- 要点3世界を変えるための秘策や革命的手法はない。個々人が世の中の不均衡を自覚し、どう行動するかを考える。そうした日々の積み重ねが、少しずつ世界を変える。
要約
人類学のまなざし
エチオピアから日本を見る

benedek/gettyimages
文化人類学は、他者の姿をみつめ、世界の別の姿を描く学問だ。著者は20年近くエチオピアに携わるなかで、大声で叫んだり、裸同然で歩き回っていたりする人によく出くわした。エチオピアの地方には精神を病んだ人が入院できる医療施設がなく、町の中で「ふつう」に生きているのだという。著者が調査した村にも精神を病んだ青年がいたが、村人たちは彼の問題を知ったうえで、寛容な態度をとっていた。数年後に青年は、畑作業などを手伝いながら自活できるまでになった。
精神を病んだり、元に戻ったりする状態を、エチオピアの人々は日常のこととして経験している。一方で日本では、精神を病んだ人は家族や病院に押し付けられ、多くの人たちが関わる必要のない場所にいる。そうして他者と関わらないことで、「ふつう」の人間像、「ふつう」の世界の姿が維持される。「ふつう」とは当たり前に見えて、実はその傍らにいる他者によってつくられるものなのである。
構築人類学
構築主義とは、ものごとには最初から本質的な性質などはなく、さまざまな作用のなかでそう構築されてきたと捉える視点である。たとえば「ジェンダー」や「ストレス」はここ最近構築された概念だが、既存の価値観や社会制度に揺さぶりをかけている。
このように構築主義は、既存の秩序や体制を批判するのに有効だ。とはいえその核心は、「批判」そのものにはないと著者は指摘する。いまの世の中に息苦しさや違和感を覚える人にとって重要なのは、身の回りのことが構築されているものだとわかれば、再構築が可能になるということだ。「ものごとは構築されたものにすぎないから正当性はない」という考え方から、「構築できるなら、どのように再構築するべきか」という問いへ転換するのが、著者の提唱する構築人類学の指針である。
社会の成り立ち
経済

hadynyah/gettyimages
店で商品を購入するときは、金銭と交換する。しかしバレンタインにチョコレートを贈るとき、対価はその場では支払われない。
私たちは人とモノのやりとりを行うとき、経済/非経済を区別するという「きまり」を維持している。経済と非経済の区別は、思いや感情をモノのやりとりに付加したり、除去したりするための装置だ。こうした区別は、人と人との関係を意味づける役割を果たしている。たとえば母親が子どもに料理をつくったり、子どもが母の日に花を贈ったりする行為は、脱経済化されることで、愛情によって結ばれた関係が強調される。家族であれば愛にあふれているわけではなく、それは脱感情化された経済との対比によって成り立っているというわけだ。
エチオピアを訪れた多くの日本人は、物乞いの多さに困惑し、彼らにせがまれたとき、たいてい「なにもあげない」ことを選ぶ。一方でエチオピアの人々は、よく物乞いにお金を渡している。

この続きを見るには...
残り3445/4607文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.02.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約