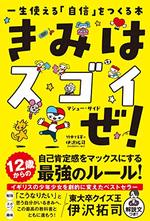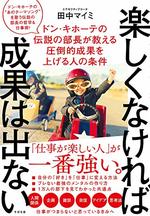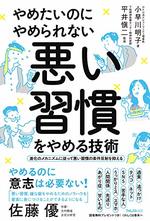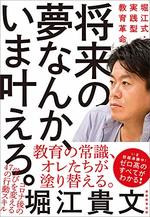記憶力日本チャンピオンの
超効率 すごい記憶術
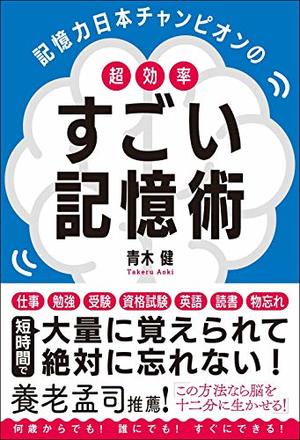
著者
青木健(あおき たける)
Brain Sports Academy代表/日本メモリースポーツ協会会長
記憶力日本チャンピオン。世界記憶力グランドマスター。大学4年時に記憶力日本選手権大会で優勝し、日本チャンピオンに。その後、様々な国際大会で好成績を収める。大学卒業後、株式会社福音館書店を経て記憶術やメモリースポーツ、ルービックキューブなど脳のスポーツを教えるスクールBrain Sports Academyを設立。
Brain Sports Academy代表/日本メモリースポーツ協会会長
記憶力日本チャンピオン。世界記憶力グランドマスター。大学4年時に記憶力日本選手権大会で優勝し、日本チャンピオンに。その後、様々な国際大会で好成績を収める。大学卒業後、株式会社福音館書店を経て記憶術やメモリースポーツ、ルービックキューブなど脳のスポーツを教えるスクールBrain Sports Academyを設立。
本書の要点
- 要点1記憶は覚える力(インプットする力)と思い出す力(アウトプットする力)が合わさって初めて成立する。
- 要点2記憶したいものをほかの事柄と関連させて覚えると、忘れづらくなる。また、ビジュアル的にイメージするようにするとさらに効果的だ。
- 要点3ストーリー法は覚えたいものをつなげて物語として記憶するテクニックである。非現実的なストーリーにすると記憶に残りやすくなる。
- 要点4場所法は頭の中で思い浮かべた場所に、覚えたいものを置いて記憶する記憶術である。ストーリー法よりもインプット時間を短縮できる。
要約
記憶と人の関係
人間は忘れる生き物

metamorworks/gettyimages
人間は忘れる生き物である。記憶力が悪い、すぐに忘れてしまう、そんな悩みを抱えている人も少なくないだろう。しかし、もともと人間は本能的に「忘れる」という能力を身につけている。もし体験や感情を忘れられなければ、ネガティブな感情をずっと引きずってしまうことになる。記憶と向き合う上では、「忘れるのは自然」という立場にたつと気持ちが楽になる。
記憶力は「覚える力(インプットする力)」と「思い出す力(アウトプットする力)」から成る。たとえば、学校で「来週テストをやるから、〇ページにある英単語を覚えてくるように」といわれたとしよう。その時、知らない単語をインプットし、テスト本番でアウトプットすることになる。つまり本番で思い出せなければ意味がない。このように、記憶はインプットとアウトプットが合わさって初めて成立する。
記憶と感情の関係
大人は子供に比べて記憶力が劣ると考えている人が多い。だが、実は決してそんなことはない。たしかに物事を単純に記憶する力は、子供のほうがよい傾向にある。というのも、子供は生きている時間が短いぶん、未知なるものに遭遇すると、感情が揺さぶられやすい。そのため物事が記憶に残りやすくなる。だが、大人の場合は、これまでの経験と紐付けて記憶したり、別の事柄と関連付けて覚えたりすることは子供よりも得意だ。
記憶力を発揮するためのミソは、「自分の知っているものや経験に関連付けて記憶すること」である。くわえて、関連して記憶する場合、意図的にオーバーなイメージをすると感情の変化が生じて記憶に残りやすくなる。
記憶力は心理状態に左右される。緊張やイライラなど精神が不安定な状態では気が散り、記憶力は低下する。「どうせ私は覚えられない」と思い込んでいると、記憶力が阻害されてしまう。感情のよしあしで記憶量が変わるのだ。
記憶力を高めるための準備運動
記憶のパフォーマンスを向上させるためには、「簡単な計算」や「音読」が有効だ。このとき、だらだらやるのではなく、時間を計ってタイムリミットを意識すると、さらに集中モードに入りやすい。また、有酸素運動をすることで記憶力が高まるという研究結果も出ている。記憶する前には、10~30分程度ウォーキングをすると集中しやすくなるというわけだ。
【必読ポイント!】 すごい記憶術
ストーリー法
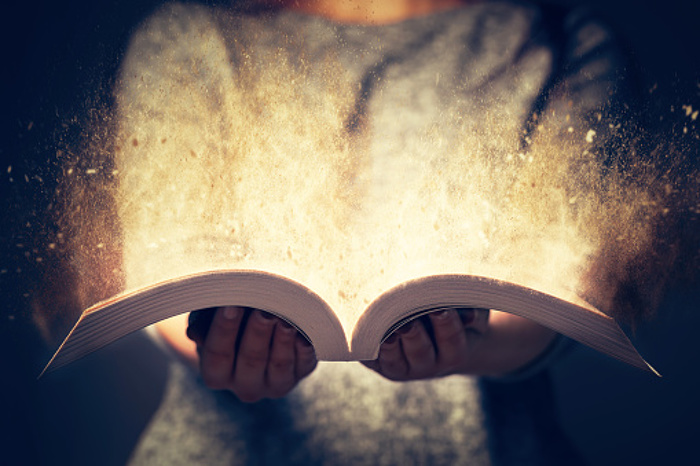
NiseriN/gettyimages
ここからは具体的なテクニックの話に入る。最初に紹介する記憶法は「ストーリー法」だ。ストーリー法とは、物語を自作して記憶する方法である。
たとえば、「電話」「時計」「ギター」「猫」「てんとう虫」という単語を覚えたいとしよう。単純にそれぞれを独立した単語として覚えてもよい。だが、それぞれの単語を関連付けてストーリーにすると、より記憶に残りやすくなる。「黒電話が鳴ると、時計がすごい速さで動き出し、そうしたら空からギターが降ってきて、猫に当たると、猫は口からてんとう虫を吐き出した」といった具合だ。
ポイントは、感情を揺さぶるためにも、できるだけ非現実的なストーリーをつくることだ。さらに、単語を丁寧に「絵としてイメージ」するとよい。このストーリー法であれば、1個の物語で最大10個程度の単語を覚えられるだろう。
場所法

mykeyruna/gettyimages
つづいて紹介するのは「場所法」である。メモリースポーツのアスリートのほとんどが使っているテクニックで、ストーリー法よりも実用性が高い。具体的には、自分の家、会社、よく行くコンビニなど、身近な場所を想像する。そして頭の中で、その場所の各所に覚えたいものを一つ一つ置いていくのだ。

この続きを見るには...
残り1561/3031文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.11.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約