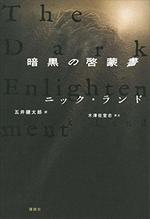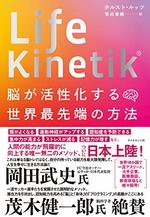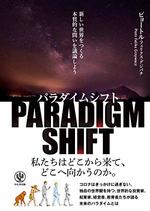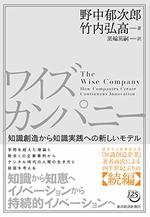ビジネスの未来
エコノミーにヒューマニティを取り戻す
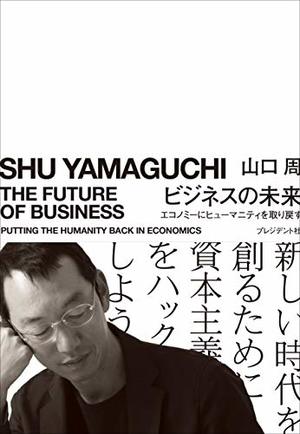
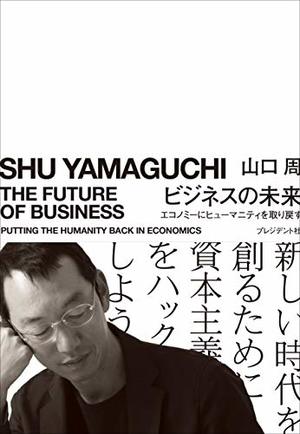
著者
山口周(やまぐち しゅう)
1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『劣化するオッサン社会の処方箋』『世界で最もイノベーティブな組織の作り方』『外資系コンサルの知的生産術』『グーグルに勝つ広告モデル』(岡本一郎名義)(以上、光文社新書)、『外資系コンサルのスライド作成術』(東洋経済新報社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』『ニュータイプの時代』(ともにダイヤモンド社)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)など。神奈川県葉山町に在住。
1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。慶應義塾大学文学部哲学科、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『劣化するオッサン社会の処方箋』『世界で最もイノベーティブな組織の作り方』『外資系コンサルの知的生産術』『グーグルに勝つ広告モデル』(岡本一郎名義)(以上、光文社新書)、『外資系コンサルのスライド作成術』(東洋経済新報社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』『ニュータイプの時代』(ともにダイヤモンド社)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)など。神奈川県葉山町に在住。
本書の要点
- 要点1私たちの社会は、「物質的不足の解消」というビジネスの使命をほぼ達成し、文明化の先の「高原社会」へ向かっている。
- 要点2市場原理には経済合理性が働くため、問題の難易度と問題の普遍性が限界曲線の内側にある社会課題しか解決できない。外側にある問題の解決には、「人間性に根ざした衝動」が必要だ。
- 要点3経済成長のない高原社会では、「消費」はより「応援」に近いものになっていく。
- 要点4高原社会には、ユニバーサル・ベーシック・インカムの導入が必要だ。経済的懸念が払拭されれば、私たちの幸せに貢献しない仕事は淘汰されていく。
要約
文明化の終焉の時代
ビジネスのミッションはすでに達成されている
「ビジネスはその歴史的使命をすでに終えているのではないか?」
本書は、この疑問に端を発する。ビジネスのミッションとは、「経済とテクノロジーの力によって物質的貧困を社会からなくす」ことだ。パナソニック(旧・松下電器産業)の創業者である松下幸之助翁の言葉を借りるなら、「生活物資を無尽蔵に提供して貧を除くこと」が「生産者の使命」である。
私たちは、この物質的不足の解消という本懐をすでに遂げている。「消費の非物質化」という現象はその必然なる結果であり、「文明化の終焉」の時代を表している。経済の低成長をしきりに憂う声が聞こえるが、それは国家主義的なノスタルジーにすぎない。私たちはいま、人類の偉業を喜び、次世代社会のあり方を問う曲がり角に立っている。
無限の成長を求めるビジネスは破綻する

gremlin/gettyimages
私たちの社会は「物質的貧困」をほぼ解消し、安全、便利、快適さを手に入れた。そしていま、「成熟の明るい高原」に向かっている。文明化が完成すればビジネスは停滞する。しかしそれを悲しむ必要はない。
「世界価値観調査」における日本の「生活満足度」を見ると、1981〜1984年と2010年とでは、後者のほうがスコアは高い。同調査における「幸福度」でも同じ傾向が表れている。
ここで注目すべき点は、バブル経済の前夜よりも、経済成長がすでに過去のものとなった時期のほうが、人々は幸福を感じているという点だ。この結果を素直に解釈するならば、生活満足度と幸福度の向上において、経済成長にもはや大きな意味はないことになる。
売上や利益を伸ばすためのマーケティングは、「物質的不満・不足の解消」という使命の終了を先延ばしにする延命措置にすぎない。「無限の成長を求めるビジネス」には、早晩破綻が訪れることになるだろう。
「無限の成長」という考えはファンタジー
世界のGDP成長率の変遷を振り返ると、およそ半世紀前にピークを迎えて以来、長期的な下降トレンドにあるのが一目瞭然だ。世界がゼロ成長へ収斂していくのが不可避だというのは、すでに多くの経済学者たちが指摘していることでもある。
これに対して、GDPは無形資産を無視しており、実態を表していないとの反論もあるだろう。しかしGDPは、もともと各国の統計担当者によって恣意的に作られた数値であり、計算方法を変更して多少数値が水増しされたとて意味はない。モノにあふれた現代社会で、「どれだけのモノをつくり出したのか?」という指標を高い水準に保つには、モノを浪費して惜しげなく捨てることが美徳の社会にするしかないが、私たちはそんな社会を望んではいないだろう。
経済は無限に成長するという考え方は非科学的であり、ファンタジーだ。信仰の類といっても過言ではない。
かつての経済成長こそ異常事態

da-kuk/gettyimages
先進国の労働生産性上昇率もまた、1960年代をピークに低下の一途をたどっている。1960年代と言えば、携帯電話もメールもコンピュータも表計算ソフトもない、電話や電報、郵便を通信手段として用いていた時代である。そんな時代よりテクノロジーが発達した2000年代以降のほうが、労働生産性上昇率は低いのだ。
この点に関して、ノースウェスタン大学経済学教授のロバート・ゴードンは、1960年代の高い成長率や生産性こそが未曾有の事態であり、その後の低下トレンドは「正常な状態」に戻っているだけだと述べている。もしこの指摘が正しいならば、企業が掲げた高い成長目標に向かって心身をすり減らしながら働くことは、「正常な状態」への回帰を阻む行為であり、不毛としか言いようがない。
真の問題は「経済成長しない」ことにあらず
世界人口が増加すると、本当に需要は増加するだろうか。国連の最新データは2100年までの人口増加を予測しているが、問題は「増加率」にある。

この続きを見るには...
残り3087/4669文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.01.27
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約