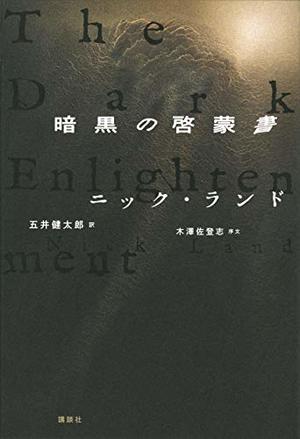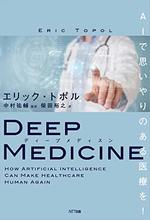暗黒の啓蒙書
著者
ニック・ランド(Nick Land)
1962年、イギリス生まれ。初期にはバタイユを専攻。ドゥルーズ+ガタリの研究を経て、90年代中頃にはウォーリック大学の講師として「サイバネティック文化研究ユニット(Cybernetic Culture Research Unit: CCRU)」を設立。大陸哲学に留まらず、SFやオカルティズム、クラブカルチャーなどの横断的な研究に従事する。「暗黒啓蒙」なるプロジェクトを通して、「新反動主義」に理論的フレームを提供し、のちの「思弁的転回」や「加速主義」、「オルタナ右翼」に思想的インスピレーションを与えた。著書に“The Thirst for Annihilation: Georges Bataille and Virulent Nihilism”, “Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007”などがある。
1962年、イギリス生まれ。初期にはバタイユを専攻。ドゥルーズ+ガタリの研究を経て、90年代中頃にはウォーリック大学の講師として「サイバネティック文化研究ユニット(Cybernetic Culture Research Unit: CCRU)」を設立。大陸哲学に留まらず、SFやオカルティズム、クラブカルチャーなどの横断的な研究に従事する。「暗黒啓蒙」なるプロジェクトを通して、「新反動主義」に理論的フレームを提供し、のちの「思弁的転回」や「加速主義」、「オルタナ右翼」に思想的インスピレーションを与えた。著書に“The Thirst for Annihilation: Georges Bataille and Virulent Nihilism”, “Fanged Noumena: Collected Writings 1987-2007”などがある。
本書の要点
- 要点1民主主義は自由を根絶させる。自由を志向するリバタリアンたちは、民主主義的な〈声〉ではなく〈出口〉をオルタナティブなものとして求める。
- 要点2ピューリタンをルーツに持つアメリカのリベラルな支配層である〈大聖堂〉は、民主主義や普遍主義を宗教的なものとして全世界に広めた。そこに疑問を投げかけようものならば、政治的不正さの思想犯の嫌疑をかけられ、異端として扱われてしまう。
- 要点3人種差別を認めない〈大聖堂〉のリベラルな教義に対して、白人たちの逃避という現実が生じている。未来に対しては分離という展望しかない。
要約
自由な〈出口〉を求めて
民主主義からの〈出口〉

Alexmumu/gettyimages
啓蒙とは一つの状態であるだけでなく、ある出来事、プロセスを指す。具体的には、18世紀のヨーロッパ北部に生じた歴史的な出来事にたいする呼び名だ。「ルネサンス」「産業革命」とも呼ばれるが、近代の起源と本質をはっきりととらえたものとして、啓蒙はその「真の名前」とされるべき有力な候補であろう。
啓蒙は、プロセスそれ自体にたいして正当性を与える性格を持つ。したがって、退行的であったり、反動的であったりするような「暗黒の啓蒙」などと言い出すことは、語の本質にかかわるような矛盾になりかねない。啓蒙された状態になるということは、なんらかの導きを受けいれ、したがうことを意味するのである。暗黒の時代につづいて、啓蒙がもたらされる。この進展はあきらかに、一つのモデルとなるようなものなのである。
ひとたびなんらかの真理が啓蒙され、それが自明のものと見なされると、もはや後戻りはありえないことになる。保守主義は矛盾した立場にあるものとして非難される。
しかし、2009年4月に開かれたピーター・ティールらリバタリアン思想家たちの討議では、民主主義的な政治にたいする幻滅が率直に表明された。リバタリアンたちは次第に、人が「彼らに注意を向ける」かどうか気にかけるのをやめはじめている。まったく別のもの、出口(イグジット)を探しはじめているのだ。リバタリアン的な声(ヴォイス)が民主主義のなかでかき消されるのは構造的に避けられない。「声」とは民主主義それ自体のことであり、民衆の意志を代表するものとされ、声を聞き届けさせることが政治である。世界を覆い尽くすこの大衆の喧騒に、リバタリアンがなにかをつけ加えようとなんの意味もない。〈平等〉対〈自由〉ではなく〈声〉に対する〈出口〉こそが目下高まりつつあるオルタナティブであり、リバタリアンたちは声なき戦いを選択しているといえよう。
かれらのような筋金入りの新反動主義者からすれば、民主主義とは絶望そのものであることになる。そこから逃れていくことは、ほとんど至上命令のようなものなのだ。
新反動主義が目指すところ

KL Yuen/gettyimages
民主主義にたいするオルタナティブは本当に存在しないのだろうか。社会において主権が実現している状態である国家は、消しさることができない。それでも、民主主義を取り除くことはできる。国家を形式化してしまうのだ。これは、新反動主義の最シンパであるメンシウス・モールドバグが「新官房学」(ネオカメラリズム)と呼ぶアプローチだ。
国家は市民に「属している」のだという民主主義的な神話を打ち砕くために、資本家が誰に対して賄賂を支払っているのかを見極める必要がある。この資本主義的な政治形態において真に権力を持つに至った支配的存在は〈大聖堂〉(カテドラル)と呼ばれ、民主主義による汚職の領域を形成している。この政治権力を形式化することで、民主主義における賄賂が「企業としての政府」(ガヴ‐コープ)において株式の保有に転換されるのだ。そうなると国家の所有者は、企業としての政府のCEOを任命して、合理的な企業経営を行う。国家の関心事は長期的な株主価値の最大化として形式化されるため、住民は政治に対して興味を抱く必要がなくなる。企業としての政府が住民の支払う税にふさわしい価値を提供できない場合、住民は自らの税を別の場所に移すことができる。したがって、より魅力的で住民を惹きつけられるような国の運営をするようになるだろう。そこに声などいらない。ただ自由な出口だけがあるのだ。
民主主義と普遍主義への宗教的な信仰
民主主義は自由を食らう
民主主義は自由にとって致命的な脅威をもたらし、やがて確実に根絶させるだろう。

この続きを見るには...
残り2765/4292文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.01.20
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright© 2021 Nick Land All Rights Reserved.
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はNick Land氏および株式会社フライヤーに帰属し、事前にNick Land氏および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright© 2021 Nick Land All Rights Reserved.
本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はNick Land氏および株式会社フライヤーに帰属し、事前にNick Land氏および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約