40歳で何者にもなれなかったぼくらはどう生きるか
中年以降のキャリア論
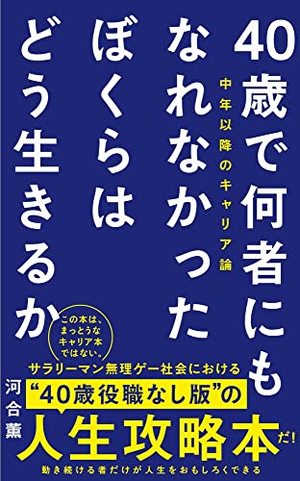
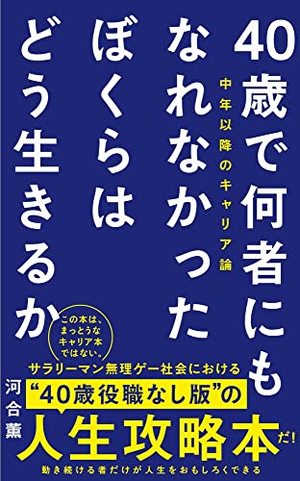
著者
河合薫(かわい かおる)
健康社会学者(Ph.D.)
千葉大学教育学部を卒業後、全日本空輸(ANA)に入社。気象予報士第1号としてテレビ朝日系「ニュースステーション」などに出演。
2007年、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。
産業ストレスやポジティブ心理学など健康生成論の視点から「人間の生きる力」に着目した調査研究を幅広く進めている。また、働く人々のインタビューをフィールドワークとし、その数は900人を超える。
著書に『残念な職場』(PHP新書)、『定年後からの孤独入門』(SB新書)、『50歳の壁 誰にも言えない本音』(MdN新書)など多数。
健康社会学者(Ph.D.)
千葉大学教育学部を卒業後、全日本空輸(ANA)に入社。気象予報士第1号としてテレビ朝日系「ニュースステーション」などに出演。
2007年、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。
産業ストレスやポジティブ心理学など健康生成論の視点から「人間の生きる力」に着目した調査研究を幅広く進めている。また、働く人々のインタビューをフィールドワークとし、その数は900人を超える。
著書に『残念な職場』(PHP新書)、『定年後からの孤独入門』(SB新書)、『50歳の壁 誰にも言えない本音』(MdN新書)など多数。
本書の要点
- 要点1他者から羨望の目で見られたり、スポットライトを浴びたりした瞬間、「何者かになった気分」という勘違いが始まる。外的な力である地位や立場は、自分の信念を忘れさせてしまう。
- 要点2根拠なき楽観には注意しなければならない。人間の生きる力は、ありのままの厳しい現実を受け入れてこそ引き出される。自分を最後まで信じて悩み抜くことが生命力の源である。
- 要点3社会的動物である人間は、他者に頼ったり頼られたりしながら、「強い自己」を確立する。世間の評価に惑わされずに「強い自己」を作ることで、成熟した大人になる。
要約
氷河期世代の矛盾
何者かになるという勘違い
他者や社会の評価がどうあろうと、自分が何者かを決めるのは自分自身である。しかし、他者と協働することで生き残ってきた人間は、なんとかして他人から評価されたいと思うものである。他者から羨望の目で見られたり、スポットライトを浴びたりした瞬間、「何者かになった気分」という勘違いが始まる。
とりわけ競争を強いられる会社においては、勝者が「権力」を得る以上、勘違いが起こりやすいと著者は指摘する。上に行くほど“オレ様度”が上がり、自分の知識が「すべて」となって、時間と成長を止める「ジジイの壁」を築いてしまう。これはある年齢の男性に限った話ではなく、「組織内で権力を持ち、その権力を組織のためではなく『自分のため』に使う人たち」が、保身のために築き上げる壁を指す。「権力がもたらす絶対感」に酔いしれた結果だ。
社内競争に勝ち続け、大企業の部長などの地位を得た「スーパー昭和おじさん」は特に問題だと著者は書く。自分の生き方に絶対的な自信があり、既得権益のために異物である女性や若者を排除する。そうして「何者かになったと錯覚したら終わり」だ。地位や立場は、自分の「信念」を忘れさせてしまう。だからこそ、「何者にもなれなかった」という嘆きは「正しい」のだ。
つじつまが合わない社会

byryo/gettyimages
大手薬品関連会社に勤める42歳の男性は、「『君たちが社会に出るときは、学歴が関係ない社会になる』と言われ続けた」と語る。しかしながら入社した会社で5歳も下の後輩にキャリアを追い越された。その後輩は元々その会社で強いK大の出身であったことから、「K大以上じゃないと上にいけない」という現実がショックだったという。
社会学者である橋本健二の分析によれば、新中間階級出身者たちが当たり前に大学に進学できたのは、「恵まれた家庭環境の下に育ったから」で、「能力的に優れていたからではない」と指摘している。
また、90年代の契約社員は、「資格とスキルさえあれば1億円プレーヤー」になれる自由な働き方の存在として期待された。しかしリーマンショック以降多くの仕事の単価が暴落、テクノロジーの発展も相まって「人」のコストは激減した。契約社員の「自由」は「不安」に変わり、むしろ正社員を夢見るようになる。2021年には「大人になったらなりたい職業ランキング」で「会社員」が1位になった。子どもたちは「成績で優劣をつけない教育」を推奨されているにもかかわらず、いい大学を目指して誰かと競争させられるという矛盾を抱えている。
終戦後、虚脱と絶望に襲われる日本において、従業員と家族を路頭に迷わせないように企業は「長期雇用」という哲学を推進した。この経営者の覚悟のおかげでがんばる「会社人間」が生まれ、日本は1968年には国民総生産で米国に次ぐ世界第2位の経済大国となる。
しかし1980年代にホワイトカラーとブルーカラーの所得格差が拡大に転じると、学歴や性別、身分などによる格差社会に突入する。バブルが崩壊した1990年代以降、リストラと成果主義によって人を切り捨て、金の亡者となった経営者たちがスーパー昭和おじさんである。「何者かになった」と自覚した瞬間、「ありのまま」を見つめることをやめ、「変わる勇気」と誠実さ、愚直さを失ってしまったのだ。
体育会系最後の世代
階層主義

tadamichi/gettyimages
映画『ハンナ・アーレント』の中で、主人公アーレントはナチスの親衛隊将校アイヒマンの裁判を傍聴し、考え抜いた結果一つの考察にたどり着く。「善を為すとも悪を為すとも決められない人間こそが最大の悪を為し得る=悪の陳腐さ」というものだ。
アーレントはアイヒマンがヒトラーに従ったとは明言せず、「ヒトラーが気にいるであろう過激な行動や発言」に毒されていたことを見抜いていた。人は絶対的権力者の考えや心情を内面化しがちなのは、会社組織においても同様である。日本は「階層主義」が世界的にも強いとされており、部下が上司に楯突くことは許されない。そうして「考える」ことをやめてしまう。

この続きを見るには...
残り3092/4744文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.10.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











