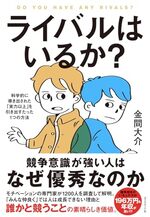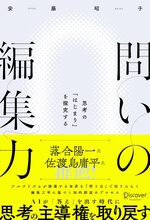AIにはない「思考力」の身につけ方
ことばの学びはなぜ大切なのか?
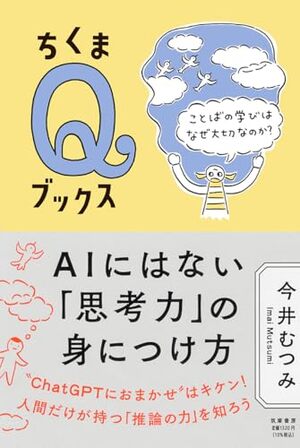
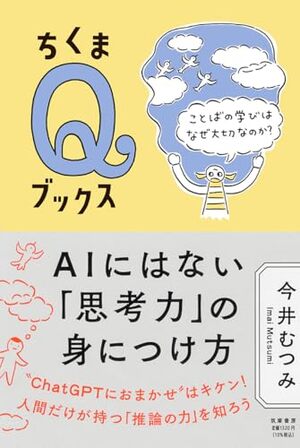
著者
今井むつみ(いまい むつみ)
慶應義塾大学環境情報学部教授。1994年ノースウエスタン大学心理学博士。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。学力不振で苦しむ子どもたちの学力困難の原因を見えるようにするツール(たつじんテスト)や学習補助教材の開発にも取り組んでいる。著書に、『言語の本質』(共著、中公新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)、『親子で育てる ことば力と思考力』(筑摩書房)、『言葉をおぼえるしくみ』(共著、ちくま学芸文庫)、『ことばの学習のパラドックス』(ちくま学芸文庫)、『ことばと思考』『学びとは何か』『英語独習法』『学力喪失』(以上、岩波新書)、『算数文章題が解けない子どもたち』(岩波書店)ほか多数。
慶應義塾大学環境情報学部教授。1994年ノースウエスタン大学心理学博士。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。学力不振で苦しむ子どもたちの学力困難の原因を見えるようにするツール(たつじんテスト)や学習補助教材の開発にも取り組んでいる。著書に、『言語の本質』(共著、中公新書)、『ことばの発達の謎を解く』(ちくまプリマー新書)、『親子で育てる ことば力と思考力』(筑摩書房)、『言葉をおぼえるしくみ』(共著、ちくま学芸文庫)、『ことばの学習のパラドックス』(ちくま学芸文庫)、『ことばと思考』『学びとは何か』『英語独習法』『学力喪失』(以上、岩波新書)、『算数文章題が解けない子どもたち』(岩波書店)ほか多数。
本書の要点
- 要点1「ことばの力」と「考える力」は右足と左足のように、互いに支え合いながら成長していく関係にある。
- 要点2人間は幼児の頃から、「アブダクション推論」と呼ばれる高度な推論能力を活用して言語を習得している。
- 要点3推論を働かせるためには、知っている情報をすぐに取り出せる「情報処理能力」と、意図的に必要な情報のみに注目することで思考をコントロールする「実行機能」が不可欠である。
- 要点4生成AIは身体を持たず、直観が働かない。身体感覚に根ざした直観は、人間だけが持つ能力である。
要約
あなたはことばを、どう覚えてきたか
ことばが指し示す範囲を探す

kuppa_rock/gettyimages
私たちは赤ちゃんのころ、誰からも強制されることなく、また教わることもないのに、母語を習得してきた。母語の習得は、言語のルール自体を探りながら覚えるというきわめて難しいプロセスだ。
たとえば、大人が白くて耳の長いウサギを指して「ウサギさんだよ」と赤ちゃんに教えたとする。しかしそれだけでは、ウサギという言葉が指し示す範囲を伝えることはできない。茶色のウサギ、小さなウサギ、耳の垂れたウサギ、これらも全部「ウサギ」と呼べるが、白いネコやハムスターは「ウサギ」ではない。言葉を本当に理解するには、その言葉が指し示す意味範囲を把握していなければならないのだ。
子どもが知らない架空の動物に名前をつけて、それと同じ種類の動物を子どもに選んでもらうという実験では、子どもはモノの名前を形に注目して覚えていることが示されている。形が似たものに同じ名前がつくという推論をしたり、知っている単語の知識から新しい単語の意味を探ったりと、子どもはさまざまな工夫をしながら知らないことばの意味を探り、覚えていっている。
子どもはことばを考えて使うことで、問題解決をする名人だ。ある3歳くらいの子どもは、イチゴを食べるときに「イチゴのしょうゆをちょうだい」と言ったそうだ。その子は、イチゴをおいしくするものが欲しいが、その名前がわからない。そこで「食べ物にかけておいしくするもの」である「しょうゆ」を「カテゴリー」として使い、コンデンスミルクもまた「しょうゆ」と言えるのではないかと考えたのだ。
形に注目したり、モノとモノの間の関係性を探ったり、文法を分析したり、読み方を発見したり、範囲を広げたり、逆に狭めたり、私たちは母語を使いこなせるようになるためにたくさんの試行錯誤をしてきたのだ。これだけで、ちょっと自分が誇らしくならないだろうか。
【必読ポイント!】 問題解決に必要な「推論」の力
生まれながらに持っている高度な力「アブダクション推論」
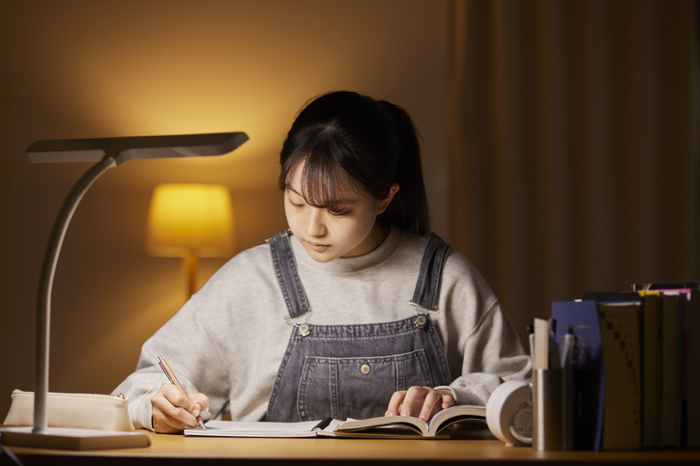
west/gettyimages
「ことばの力」は、「考える力=思考力」とも密接な関係を持っている。ことばの力と考える力は、ちょうど右足と左足のようなものだ。片方が前に出れば、もう片方がそれを追い越すようにして前に出る。ことばの力が伸びれば考える力も伸び、考える力が伸びれば、ことばの力も自ずと伸びていく。

この続きを見るには...
残り1867/2839文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.02.01
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約