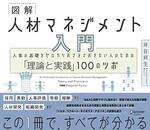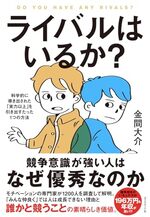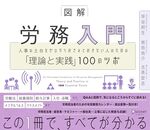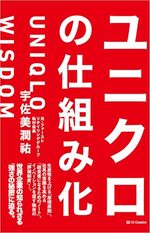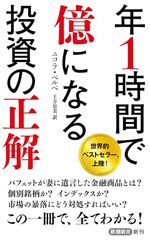最新のHRテクノロジーを活用した
人的資本経営時代の持続可能な働き方
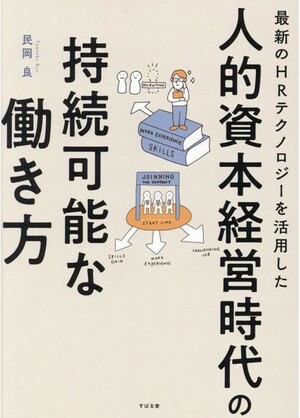
著者
民岡良(たみおか りょう)
株式会社SP総研 代表取締役
人事ソリューション・エヴァンジェリスト
1996年慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本オラクルにてERPシステムの教育事業に従事。SAPジャパンにおいては人事管理システム(SAP ERP HCM)の導入、認定コンサルタント養成プログラムでの講師を担当。その後、人材エージェント業務を経て2016年に日本IBMに参画し、Kenexa / Watson Talentを活用したタレントマネジメント、採用・育成業務プロセス改革に従事。直近ではウイングアーク1stにて、日本企業の人事部におけるデータ活用ならびにジョブ定義、スキル・コンピテンシー定義を促進させるための啓蒙活動に従事したのち、2021年5月より現職。一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアムの理事も務め、「人的資本開示(ISO30414)」に関する取り組みについても造詣が深い。労政時報セミナー、HRカンファレンス等、登壇実績多数。
著書に、『HRテクノロジーで人事が変わる』(共著・労務行政)、『経営戦略としての人的資本開示』『戦略的人的資本の開示』(共著・両書とも日本能率協会マネジメントセンター)、『現代の人事の最新課題』(共著・税務経理協会)等がある。
株式会社SP総研 代表取締役
人事ソリューション・エヴァンジェリスト
1996年慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本オラクルにてERPシステムの教育事業に従事。SAPジャパンにおいては人事管理システム(SAP ERP HCM)の導入、認定コンサルタント養成プログラムでの講師を担当。その後、人材エージェント業務を経て2016年に日本IBMに参画し、Kenexa / Watson Talentを活用したタレントマネジメント、採用・育成業務プロセス改革に従事。直近ではウイングアーク1stにて、日本企業の人事部におけるデータ活用ならびにジョブ定義、スキル・コンピテンシー定義を促進させるための啓蒙活動に従事したのち、2021年5月より現職。一般社団法人HRテクノロジーコンソーシアムの理事も務め、「人的資本開示(ISO30414)」に関する取り組みについても造詣が深い。労政時報セミナー、HRカンファレンス等、登壇実績多数。
著書に、『HRテクノロジーで人事が変わる』(共著・労務行政)、『経営戦略としての人的資本開示』『戦略的人的資本の開示』(共著・両書とも日本能率協会マネジメントセンター)、『現代の人事の最新課題』(共著・税務経理協会)等がある。
本書の要点
- 要点1日本企業の人事部門は、「エクスペリエンスの創出」「人材獲得競争」といった課題に直面している。
- 要点2今後はHRテクノロジーを活用し、日本型経営のよい面を残しつつ、現代風にアップデートすることが求められる。その活用が期待されるのが「育成(人材開発)」領域だ。
- 要点3本書では「採用・配置」「人材開発」「組織開発」「勤怠・労務管理」などにおけるHRテクノロジーの活用について、その特徴を紹介していく。
要約
人事が直面する差し迫った課題
エクスペリエンスの創出、人材獲得競争
日本企業の人事部門が直面している課題として、著者は次の6つを挙げる。
1つ目の課題は「エクスペリエンス(=いい体験)の創出」だ。日本は他の先進国と比較して労働生産性が低く、その最大の要因は職務と人材のミスマッチにある。これに対処するには、採用プロセスにおける「応募者体験の向上」、入社後に求めるスキルと働き手が保有しているスキルのギャップを可視化して埋める「従業員体験の向上」が必要となる。
応募者体験や従業員体験の向上は、2つ目の課題である「人材獲得競争」にも有効だ。良質な応募者体験を提供できる企業は、応募者自身がそこで活躍するイメージを描きやすく、採用競争力が高まる。また、従業員体験を高いレベルで提供できれば、離職を防ぎやすくなる。
「アジャイル人事」として、意思決定のベースを築く

kazuma seki/gettyimages
3つ目の課題は「ビジネス環境の急激な変化」だ。これはチャンスにもなり得る。変化の波に乗ることで、誰もがビジネスを先導する「ディスラプター(破壊者)」になれるからだ。
激しい変化の中で、「アジャイル人事」の実践がますます必要となる。例えば、週に一度の1on1面談、行動変容を促す「リアルタイムフィードバック」、よい行動を互いに褒め合う「ピア・リコグニション」などである。

この続きを見るには...
残り4228/4785文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.02.09
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約