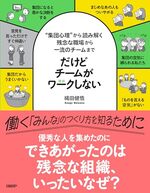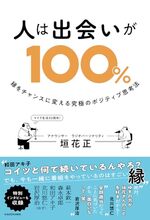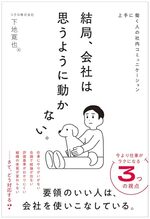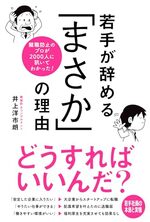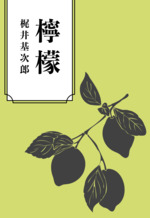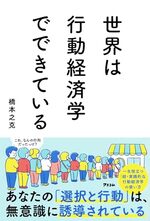読めば分かるは当たり前?
読解力の認知心理学
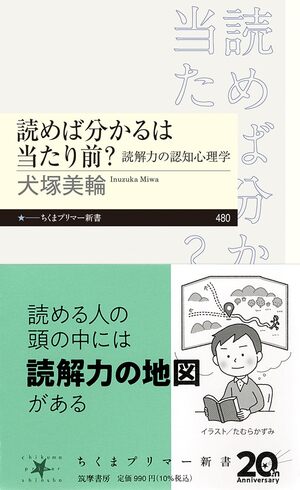
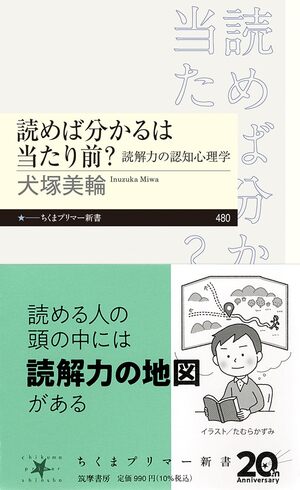
著者
犬塚美輪(いぬづか みわ)
東京都出身。東京大学教育学部・東京大学大学院教育学研究科で教育心理学を学び、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京大学先端科学技術研究センター研究員、大正大学を経て東京学芸大学教育学部准教授。研究テーマは、読み書きの心理プロセスと指導法開発。著書に『論理的読み書きの理論と実践』(北大路書房)、「生きる力を身につける——14歳からの読解力教室』(笠間書院)、『認知心理学の視点——頭の働きの科学』(サイエンス社)がある。
東京都出身。東京大学教育学部・東京大学大学院教育学研究科で教育心理学を学び、日本学術振興会特別研究員(PD)、東京大学先端科学技術研究センター研究員、大正大学を経て東京学芸大学教育学部准教授。研究テーマは、読み書きの心理プロセスと指導法開発。著書に『論理的読み書きの理論と実践』(北大路書房)、「生きる力を身につける——14歳からの読解力教室』(笠間書院)、『認知心理学の視点——頭の働きの科学』(サイエンス社)がある。
本書の要点
- 要点1読解には、第一の目的地である「表象構築」と、そこから枝分かれする第二の目的地である「心を動かす読解」と「批判的読解」の3つの目的地がある。
- 要点2表象構築に至るまでには、文字の同定、単語の同定、単語間の関連理解、文間の関連理解と、たくさんの山を越えなければならない。
- 要点3読解のための方略は「理解補償方略」「内容学習方略」「理解深化方略」の3つに整理できる。これらを念頭に、それぞれの読解方略がどこで役立ちそうか考えながら実践してみるといい。
要約
3つの読解
第一の目的地:「表象構築」

Yutthana Gaetgeaw/gettyimages
「読解力」は多様な概念であるが、本書はこれをざっくり3つに分けて整理し、目指すべき目的地の位置付けを確認していく。
3つの目的地のうち、第一の目的地は「表象構築」だ。心理学では理解するとはどういうことかを、「表象」という言葉を使って表している。「カレーライス」と聞けば頭の中に「カレーライス」が浮かぶように、文章を読んだとき、私たちは情報や物ごとを頭の中に再現し「表象」を作る。これを「表象構築」と呼ぶ。
表象構築には2つの異なるレベルがある。第一のレベルは、書いてある内容が整理されている「テキストベース」の理解だ。
もうひとつのレベルである「状況モデル」では、読み手がもともと知っていることを活用しながら、読んで推論した内容と組み合わせて「世界の再現」が行われる。たとえば「煩悩の数だけ鳴る寺の鐘の音」を聞いたという文章を読んで、「12月31日のことだ」と分かるのは「状況モデル」を作れたからだ。煩悩の数だけ鳴る鐘とは、除夜の鐘のことだということを知っていて、そのことに思い至れば、文中に日付の情報がなくても大晦日の出来事だと推察することができる。
読んだ内容を記憶し、別の場面で活用するためには、状況モデルの表象が必要となることが多い。だとすれば、読解の最初の目的地は、状況モデルの表象を構築することだといえる。読むことを通して自分の知識を拡張し、新たな状況下でその知識にアクセスできるように良いつながりを作っておくことが読解の第一の目的地だ。
第二の目的地:「心を動かす読解」「批判的読解」
第一の目的地である表象構築を経由して向かう第二の目的地には「心を動かす読解」と、あえて納得しないことを選ぶ「批判的読解」の2種類がある。どちらも「状況モデル」を構築する点は共通しているが、「心を動かす読解」と「批判的読解」では、そこに異なる要素を追加してバージョンアップしたモデルを作るという点が異なっている。

この続きを見るには...
残り4217/5034文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.18
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約