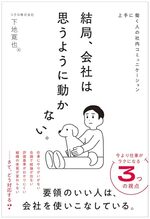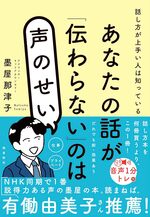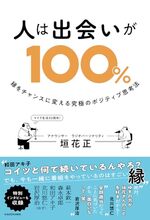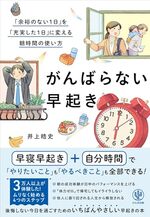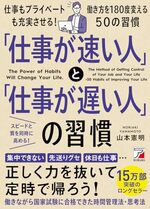世界は行動経済学でできている
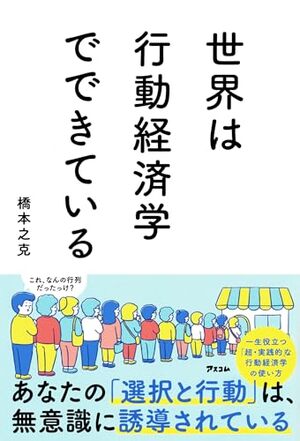
世界は行動経済学でできている
著者
著者
橋本之克(はしもと ゆきかつ)
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。
『世界最先端の研究が教える新事実行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
行動経済学コンサルタント/マーケティング&ブランディングディレクター
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。
『世界最先端の研究が教える新事実行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
本書の要点
- 要点1人は選択肢が多すぎると決断を先送りしがちになる。行動経済学ではこれを「決定麻痺」と呼ぶ。
- 要点2事前にそれを予見していたかのように思い、自分の考えが正しいと考えることは「後知恵バイアス」と呼ばれる。これは、実際に起きたことによって、自分の記憶が書き換えられ、「そうなるとわかっていた」と思いたがる傾向だ。
- 要点3「現在志向バイアス」により、人は先の利益よりも目の前の利益を優先しやすい。長期的な目標を達成するには、短いスパンで具体的な計画を立てることが有効だ。
- 要点4自分の意見が常識的で多数派だと思い込む傾向は、「フォールスコンセンサス効果」と呼ばれる。この心理を理解していないと、自覚のないまま横暴な態度をとってしまいかねない。
要約
【必読ポイント!】 誰もが相手を都合よく動かしたい
町中華は行動経済学のプロだった?
テレビ番組で「メニューが多すぎる中華料理店」が話題になったことがある。顧客のリクエストに応えたりしていくうちに、現在のメニューは400種以上にもなっているそうだ。一方で、創業時からの看板メニューは「ちゃんぽん」と決まっている。大量のメニューとおすすめの看板メニューの組み合わせは、実は行動経済学的に理にかなった戦略だ。
私たちは日常生活の中で、さまざまな条件を比較検討しながら決定をしている。しかし、選択肢が多すぎると、何を選べばいいかわからなくなり、決断を先送りするという選択をしがちになる。行動経済学では、選択肢が多すぎることでその選択を先送りすることや、選択すること自体をやめてしまうことを「決定麻痺」と呼ぶ。
ある研究によれば、人間は1日あたり最大で3万5000回もの意思決定をしている。決断することが多すぎて嫌になってしまう現象は「決断疲れ」と呼ばれ、「決定麻痺」の前段階として陥りがちな状態として知られている。
商品を売る企業にとっては、「決定麻痺」や「決定疲れ」を見越して、自分たちに有利な形で顧客に判断させることが大切だ。「メニューが多すぎる中華料理店」は、定番メニューで「決定麻痺」対策をしながら、大量のメニューの中から「選ぶ楽しみ」も提供している、かしこい戦略だといえる。
「とりあえず生ビール」に同意してしまうわけ

mapo/gettyimages
同僚や友人たちと居酒屋に入って飲み物を決めるとき、「とりあえず生ビールで」と言う人がいると、次々にみんなが生ビールを注文しはじめるという場面に出くわすことがあるはずだ。同様に職場の会議やミーティングで、誰かの意見に内心反対だったとしても、複数のメンバーが賛同しはじめたら、自分は反対だと言い出しづらく感じるかもしれない。集団の中で浮かないために意見が言えないという状況では、行動経済学でいう「同調効果」が働いていると考えられる。

この続きを見るには...
残り3745/4564文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約