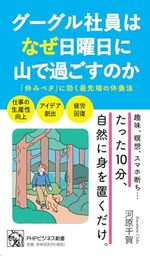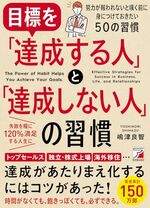なぜ倒産 運命の分かれ道
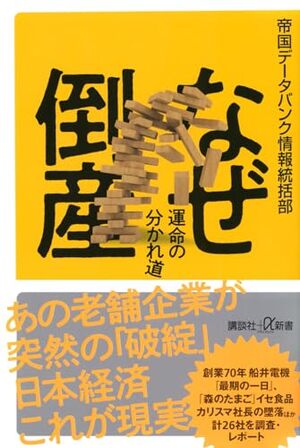
なぜ倒産 運命の分かれ道
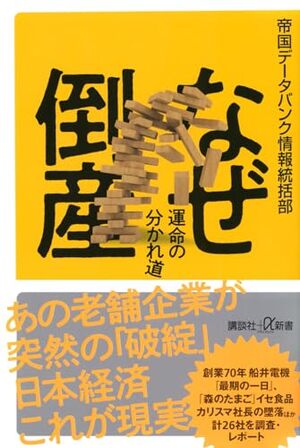
著者
帝国データバンク情報統括部(ていこくでーたばんくじょうほうとうかつぶ)
1900年創業、国内最大級の企業情報データベースを保有する民間信用調査会社。
中小企業の倒産が相次いだ1964年、大蔵省銀行局からの倒産情報の提供要請に応じる形で情報部を創設。2021年に情報統括部に改称。情報紙「帝国ニュース」の発行、「全国企業倒産集計」などを発表している。
1900年創業、国内最大級の企業情報データベースを保有する民間信用調査会社。
中小企業の倒産が相次いだ1964年、大蔵省銀行局からの倒産情報の提供要請に応じる形で情報部を創設。2021年に情報統括部に改称。情報紙「帝国ニュース」の発行、「全国企業倒産集計」などを発表している。
本書の要点
- 要点1コロナ禍における支援策によって、本来破綻していたはずの企業も延命できていたが、支援終了とともに物価、人件費が高騰したことも相まって資金繰りに行き詰まる企業が増えたため、倒産件数が増加した。
- 要点2アフターコロナの倒産は、リーマン・ショック時のような「不況型」ではなく、資金面や人材確保の面で企業間格差が広がったことが原因となっている。
- 要点3「ユニコーン」候補とされた企業や創業100年を超える老舗企業、大企業の事業を引き継いだ企業まで、経営環境の変化だけでなく、それぞれの個別の事情で倒産に至っており、一つひとつの事例を転ばぬ先の杖として学ぶことが大切だ。
要約
【必読ポイント!】 企業倒産増加の理由
アフターコロナの倒産の特徴

utah778/gettyimages
新型コロナウイルスのパンデミックは全世界の経済活動に大きな影響を及ぼしたが、日本では中小企業を中心としたきめ細やかな政府支援によって、企業の倒産は減少した。行動制限が撤廃されて経済活動が本格化すると、世界中でインフレが進み、日本でもバブル崩壊以後続いたデフレからの脱却が展望され、「物価上昇と賃上げの好循環が生まれる経営環境」が整いつつある。
しかし、中小・零細規模の企業倒産は増加に転じている。その理由として、次の3つが考えられる。
1つ目は、コロナ禍において実施された、政府系・民間金融機関による約45兆円の実質無利子・無担保のゼロ・ゼロ融資や、休業補償などの中小企業向け金融支援が順次縮小、終了したことである。コロナ禍に関連したこれら一連のサポートでなんとか破綻を免れていた企業が、売り上げの回復や返済計画の作成もできないまま行き詰まり、業績改善ができない状態で手元資金を使い果たすという事例が多く見られる。
2つ目は、支援終了とほぼ同時に本格化した物価高の影響による、企業収益の悪化である。ロシアのウクライナ侵攻による小麦粉、食用油の需給逼迫や、半導体不足によって、様々な分野でインフレ圧力が高まった。また、日米の金利差拡大による円安も輸入物価の上昇に拍車をかけた。物価上昇のペースに賃上げが追いついていないため、原材料価格の上昇に対する価格転嫁を進めるのも難しく、収益を改善できない企業が行き詰まってしまうのだ。
3つ目は、人手不足である。生産労働人口の減少が進む一方で、賃上げができないことによる人材流出や、後継者不足で、事業継続を断念するケースが増えている。アフターコロナの倒産増加は、資金面、人材確保の面で企業間格差が広がることで、さらに加速するだろう。これは、リーマン・ショック時における世界的な需要消失による「不況型倒産」とは違った性格のものである。
創業間もない企業から100年を超える企業まで、倒産に至るリスクは常に存在する。経済環境や、運・不運、わずかな経営判断のミスなど、それぞれ個別の原因で行き詰まってしまう。そうした事例をしっかりと理解し、転ばぬ先の杖とすることが大事だ。
新興企業の倒産と老舗企業の倒産
太陽光発電事業を手がける「ユニコーン」の墜落

rudall30/gettyimages
新電力向けシステム開発企業「パネイル」は、電力自由化時代のプラットフォームを提供する企業として、多くのメディアで取り上げられた期待のユニコーン候補だった。名越達彦社長は、学生時代に鳥人間コンテスト選手権大会で優勝を経験し、株式会社ディー・エヌ・エー入社後はモバゲーの立ち上げに携わったという、バイタリティのある人物である。

この続きを見るには...
残り3614/4742文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2025 帝国データバンク情報統括部 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は帝国データバンク情報統括部、株式会社フライヤーに帰属し、事前に帝国データバンク情報統括部、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2025 帝国データバンク情報統括部 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は帝国データバンク情報統括部、株式会社フライヤーに帰属し、事前に帝国データバンク情報統括部、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約





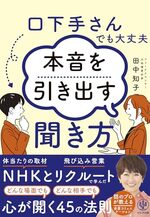

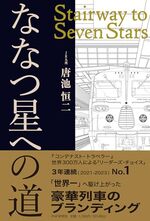
![[新装版]「やさしさ」と「冷たさ」の心理](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/4143_cover_150.jpg)