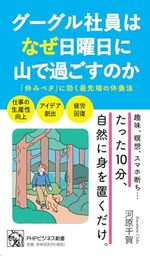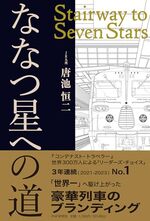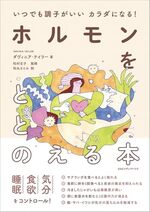[新装版]「やさしさ」と「冷たさ」の心理
![[新装版]「やさしさ」と「冷たさ」の心理](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/4143_cover_300.jpg)
[新装版]「やさしさ」と「冷たさ」の心理
著者
著者
加藤諦三(かとう たいぞう)
社会心理学者。早稲田大学名誉教授、元ハーヴァード大学ライシャワー研究所客員研究員。
1938年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科を経て、同大学院社会学研究科修士課程を修了。1973年以来、度々、ハーヴァード大学ライシャワー研究所客員研究員を務める。1977~2008年まで早稲田大学教授。日本精神衛生学会顧問。ラジオ番組「テレフォン人生相談」(ニッポン放送)では、半世紀以上レギュラーパーソナリティを務めている。2009年東京都功労者表彰、2016年瑞宝中綬章受章。『心の休ませ方』『自分に気づく心理学』(以上、PHP研究所)ほか、社会心理学に関する著書多数。
社会心理学者。早稲田大学名誉教授、元ハーヴァード大学ライシャワー研究所客員研究員。
1938年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科を経て、同大学院社会学研究科修士課程を修了。1973年以来、度々、ハーヴァード大学ライシャワー研究所客員研究員を務める。1977~2008年まで早稲田大学教授。日本精神衛生学会顧問。ラジオ番組「テレフォン人生相談」(ニッポン放送)では、半世紀以上レギュラーパーソナリティを務めている。2009年東京都功労者表彰、2016年瑞宝中綬章受章。『心の休ませ方』『自分に気づく心理学』(以上、PHP研究所)ほか、社会心理学に関する著書多数。
本書の要点
- 要点1子どもの頃に親から十分に愛されてきた人は、甘えの欲求が満たされている。一方で、親が甘えの欲求を満たす手段として子どもを利用してきた場合、その子は自身に罪悪感を抱くようになってしまう。
- 要点2自分に自信がない人は、自分のことを軽蔑する尊大な人と一体化することで安心感を得ようとする。尊大な人も一人で生きられないため、お互いに共棲することで心理的な安全を得ている。
- 要点3自分の周りに好意がないのではなく、自分に不安や葛藤があるがゆえに相手の好意を拒絶しているのだ。
要約
子どもの頃のトラブルに支配されてはいけない
不機嫌の理由

Vaselena/gettyimages
甘えている人は、周囲の人に対し、自分の望む反応をしてほしい、ほめてほしいなどの要求が多い。望む要求が得られなかった場合には、それをはっきりと言葉で伝えずに不機嫌になる。つまり、不機嫌な人は甘やかされたいのだ。満たされない甘えによって、感情を動かされているのである。
子どものころに親から十分に愛されてきた人は、甘えの欲求が満たされ、周囲と自分を信頼し、独り立ちできる。一方で、親自身の甘えの欲求を満たす手段として、子どもを利用することがある。子どもは一人で生きられない。親から拒否されないために、親の要求にこたえ、親が望むように自分を変えていく。子ども自身の甘えは、親が求める要求の邪魔だ。やがて、自分の中にある甘えを悪いものと考えるようになり、自分を罪悪視するようになってしまう。
そうして育った人は、心の底で「やさしさ」を求めているにもかかわらず、考えるのは自分を守ることばかりだ。やさしい人と冷たい人を見分けられず、自分の心の病を悪化させるような人とばかりつきあってしまう。
では、どんな人が「冷たい人」なのだろうか。
もし、相手から「冷たい」と言われれば、自信を失ってしまうはずだ。その「冷たい」と感じる基準は人によって異なるし、相手の甘えの欲求が原因となることもある。
たとえば、甘えの欲求を強く残した人が恋愛をした場合、親しくなるほど自分のわがままを出すようになる。そのわがままを受け入れない相手に対し、「冷たい」と言う。この相手が病人やお年寄りに心配りをしていたとしても関係ない。自分の欲望を満足させないことが「冷たい」のである。しかも、「自分の欲望の言いなりにならないことが原因」という自覚がない。本当にその相手のことを「生意気だ」と思っているのだ。
愛された経験が人生を左右する
人間にとって、自分が他人から好かれる存在である、自分には愛される価値があると感じることは、人生の幸不幸を左右してしまうほどの影響力を持つ。その根本にあるのが、小さい頃に「自分は愛される存在である」と感じられたかどうかだ。
親から「あなたは愛されている」「ここにいる権利がある」というメッセージを受け取ってきた人と、「あなたは望まれないのに生まれてきたのだから、ここにいられるためには、皆に気に入られる自分に変わらなければいけない」というメッセージを受け取ってきた人には、大きな差が生まれてしまう。
以下の言葉は、著者の研究してきた交流分析によく出てくる文言である。

この続きを見るには...
残り3575/4624文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.03.29
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約