テクニウム
テクノロジーはどこへ向かうのか?
著者
ケヴィン・ケリー (Kevin Kelly)
著述家、編集者。1984-90年、雑誌 Whole Earth Review の発行・編集を行う。1993年には雑誌Wiredを共同で設立。以後、1999年まで編集長を務める。現在は、毎月50万人のユニークビジターを持つウェブサイトCool Toolsを運営している。ハッカーズ・カンファレンスの共同設立者であり、先駆的なオンラインサービスWELLの設立にも携わる。著書『ニューエコノミー勝者の条件』(1999、ダイヤモンド社)『「複雑系」を超えて』(1999、アスキー)他。ホームページ http://kk.org/。
著述家、編集者。1984-90年、雑誌 Whole Earth Review の発行・編集を行う。1993年には雑誌Wiredを共同で設立。以後、1999年まで編集長を務める。現在は、毎月50万人のユニークビジターを持つウェブサイトCool Toolsを運営している。ハッカーズ・カンファレンスの共同設立者であり、先駆的なオンラインサービスWELLの設立にも携わる。著書『ニューエコノミー勝者の条件』(1999、ダイヤモンド社)『「複雑系」を超えて』(1999、アスキー)他。ホームページ http://kk.org/。
本書の要点
- 要点1テクニウムとは、自己強化・生成するシステムをもった、あらゆるテクノロジーの総称である。
- 要点2生物とテクニウムの最も大きな違いは、絶滅の有無にある。地球上から完全に消えさったテクノロジーはほとんど存在しない。
- 要点3テクノロジーの進化を遅らせることはできても、止めることは不可能だ。
- 要点4テクノロジーのもたらす結果を予防することはできない。そのことを受けいれ、自律共生できるよう努力していくべきだ。
要約
テクニウムとは何か
自己強化する創造システム

Yulia_Malinovskaya/iStock/Thinkstock
私たちはテクノロジーというと、ピカピカなガジェットを想像しがちだ。しかし広義の意味ではソフトウェア、絵画や文字、音楽、ダンス、詞や芸術一般といったものも、テクノロジーに含まれるべきである。
こうしたものは一般的に<文化>とも呼ばれているが、それでは意味する範囲が狭すぎる。テクノロジーの特徴は、さらに多くのテクノロジーを自己生成という方法で生み出すことであり、<文化>という言葉では、テクノロジーのそういったニュアンスをうまく伝えられない。
とはいえ、<テクノロジー>という言葉も不十分である。「バイオ・テクノロジー」や「デジタル・テクノロジー」、あるいは「石器時代のテクノロジー」という表現に見られるように、この言葉は個別の方法や装置を連想させてしまうからだ。
私たちの身の周りで起こっている、より大きくグローバル規模で相互に結ばれているテクノロジーのシステムをあらわす言葉として、本書では<テクニウム>という言葉を提唱する。ここにはありとあらゆる種類の文化、アート、社会組織、知的創造が含まれている。しかし最も重要なのは、「テクノロジーは自己強化する創造システムである」という主張がそこに組み込まれていることだ。テクノロジーの進歩は著しく、テクニウムは自らあるべき方向へ成熟していっている。つまり、そこには明らかに自律性が存在しているのだ。
テクニウムを創造したのは人間なのだから、コントロールするのも人間だと考える人は多い。しかしそれは誤りである。テクニウムのルーツは人間の知性だけにあるのではなく、古代の生命や他の自己組織化システムと深いところでつながっている。だからこそ、テクニウムも他の生命システムと同じく、自分自身を永続的に存在させようとするし、成長にともない、そうした要求は複雑性を増していく。
いまや自然にも匹敵する力をもったテクニウムにたいし、わたしたちがするべきことは、自然にたいする態度と同じような姿勢で向き合うことだ。つまり、コントロールしたり反発したりするのではなく、テクニウムの性質を学び、うまく協調していくのである。
テクニウムと生物は似ている
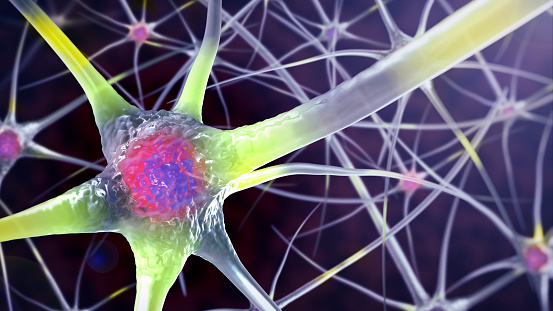
CreVis2/iStock/Thinkstock
地球上で今までに発見された生命の種類を図式化すると、6つの大部門にわかれる。それらはすべて共通の生化学的な設計図を有しており、今日まで進化を遂げてきた。その過程で、多くの生物は構造物を作ることを学び、自分の身体組織を超えた生活を営んできた。サンゴ虫におけるサンゴ礁、ハチにおけるハチの巣などはその典型例だ。
テクニウムも同様に、人間の身体が拡張したものだといえる。テクニウムの進化は生物の遺伝的な進化と似ており、共通点も多い。どちらの場合も、単純なものから複雑なものに、画一的なものから多様なものに、個人主義から相互主義に、エネルギー浪費型から高能率型へと進化してきている。そういう意味で、テクニウムは、生命の六界ではじまった情報の再編成をさらに推し進めた、第七界にあたる存在だと見なしてもよいだろう。
テクニウムと生命は何が違うのか
テクニウムは他の六界といくつか重要な点で異なっている。まず、テクニウムの種は地球上でもっとも短命だ。私たちが生みだしたものの寿命は、最も短命な生物にも及ばない。多くのデジタル・テクノロジーは個々のカゲロウの寿命にすらおよばないし、種としての比較など論外である。
また、計画性という観点でも両者は異なっている。自然の場合、あらかじめ進化の計画を練ることは不可能だ。羽毛の一部が翼として進化していったように、事前に意図しなかったにもかかわらず、別のかたちで用いられることも多い。これを生物学では外適応と呼ぶが、テクニウムの場合、この外適応が頻繁に起きる。イノベーションは、アイデアが系統樹を超えて拝借されたり、別の目的に適用されたりする過程で生まれるものだからだ。
さらに、生物の形質混合のほとんどが時間軸上の「縦軸」で発生している一方で、テクニウムの形質混合は文字どおり時間を超える。

この続きを見るには...
残り2429/4086文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.01.02
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約












