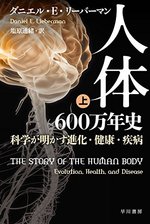資本主義はどう終わるのか
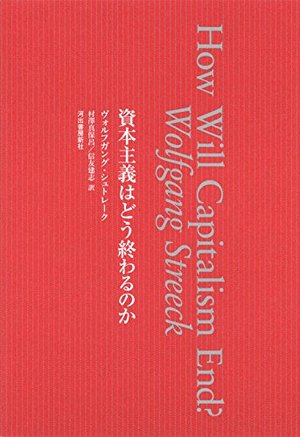
資本主義はどう終わるのか
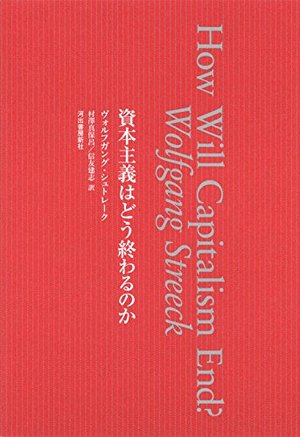
著者
ヴォルフガング・シュトレーク (Wolfgang Streeck)
1946年ドイツ生まれ。社会学者。95年よりケルンのマックス・プランク研究所(社会研究部門)所長、99年からはケルン大学教授を兼任。著書『時間稼ぎの資本主義』
1946年ドイツ生まれ。社会学者。95年よりケルンのマックス・プランク研究所(社会研究部門)所長、99年からはケルン大学教授を兼任。著書『時間稼ぎの資本主義』
本書の要点
- 要点11970年代のインフレ、1980年代の公的債務と民間債務の急増、2008年の金融市場の崩壊という一連の危機をとおして、資本主義と民主主義のペアは破局の道をたどった。
- 要点2戦後民主主義の標準モデルは、70年代をピークに解体された。戦後の成長が終わり、民主主義が担っていた市場経済の収益再配分が縮小すると、資本家たちは脱国家を求めた。ここから金融のグローバル化がはじまった。
- 要点3「民主制資本主義」には、市場と人民という2つの主権が存在するが、市場は人民より上に立つ。そのためリーダーたちにとっては、有権者より投資家との信頼関係のほうが重要である。
要約
資本主義の危機とトレンド
資本主義の危機理論

mmustafabozdemir/iStock/Thinkstock
資本主義は、初期から一貫して危機に瀕していた理論である。マルクスやケインズ、ポランニー、シュムペーターなど、時代や主張はそれぞれ異なれど、彼らは一様に資本主義の終焉を予期していた。
さらに2008年の大不況(グレート・リセッション)以降、資本主義の未来を案ずる批判的な議論が再燃した。たとえば5人の社会科学者によって著された『資本主義に未来はあるか?』という書物がある。全員の連名で書かれた部分を除けば、それぞれの見解は異なる。だが資本主義および資本主義社会が、重大な危機に瀕しているという点では同じだ。
著者によると、資本主義には治療不可能な病理が蓄積しているという。たしかに近代資本主義の歴史は危機の連続であり、それでもなんとか生き延びてきた。しかし現在は、多くの病理が一斉に悪化し、治療を要するも対策が尽きてしまっている状態だ。
一連の危機とグローバルトレンド
OECD諸国において、資本主義は3つの危機を経験した。すなわち1970年代のグローバルなインフレ、1980年代の公的債務の急増および民間債務の増加、そしてこれらが招いた2008年の金融市場の崩壊である。主要な資本主義国はどれもこの一連の危機をたどっており、1960年代末に戦後の経済成長が終わって以降、経済が安定したことは一度もない。
インフレや公的債務、民間債務の規制緩和は、資本家と労働者の対立への解決策だった。しかしのちに、それ自体が新たな問題と化した。インフレは失業を招き、増加する債務を危惧した債権者は、債務整理への圧力を強めた。そして公共投資の削減が、民間債務に総需要とのギャップの穴埋めをさせ、その莫大な民間債務はバブルの破綻とともに崩壊した。
1980年代にインフレが終わり、アメリカ合衆国主導で金融産業がグローバル化を進めると、近代資本主義の「租税国家」は「債務国家」へと移行。さらに1990年代半ばには、「財政再建国家」へと変容した。
この一連の危機と財政再建国家への移行には、成長鈍化、格差拡大、債務増大という3つの長期傾向が見られる。成長鈍化は格差を拡大し、それがまた成長の鈍化につながる。債務増大は金融危機の可能性を高め、金融セクターの過剰成長がさらに格差を増大させる。
これらは資本主義的システム全体に影響するグローバルトレンドであり、そこから抜け出すための打開策はいまだ見つかっていない。
【必読ポイント!】 資本主義と民主主義の破局
標準的民主主義モデルの解体

ilkercelik/iStock/Thinkstock
一連の危機をとおして、戦後の資本主義と民主主義のペアはゆっくりと破局へ向かった。それに伴い、分配をめぐる対立の舞台も移動した。
1970年代のインフレ時は、労働者への再分配を求めること、つまり労使関係が主な対立の場であった。1980年代になってインフレが終わると、今度は福祉国家のあり方をめぐる対立となり、舞台は選挙へと移行した。そして財政再建の局面で、人々の手持ち資金はクレジット(信用貸付)に依存するようになった。このような変遷は、新自由主義の世界的な広がりや、戦後民主主義の標準モデルの腐敗過程と重なっている。

この続きを見るには...
残り2013/3312文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.03.31
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約