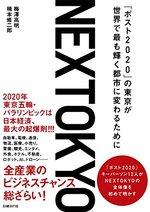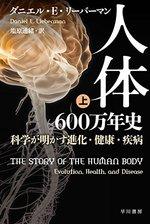デジタル革命と労働力の余剰
豊かな時代に下がる賃金
「どこもかしこもコンピュータ時代だ。だが生産性の統計数値にだけはコンピュータ時代が訪れていない」。これは、ノーベル賞経済学者、ロバート・ソローが1987年の論文に記した言葉だ。コンピュータはこの50年間、社会を根本から変える革命マシンと見なされてきたが、期待ほどの変革は生じていなかった。
しかし、いま、「デジタル革命」は、社会全体に大きな恩恵と破壊をもたらそうとしている。自動化、グローバル化、高スキル労働者の生産性向上。こうした3つの要因が重なり、労働力の余剰と賃金低下という現象が生じている。自動車産業は、もはや工業ではなくソフトウェアビジネスだ。製造ロボットが革新的な進化を遂げた結果、労働集約性は下がり続けており、大量雇用の場ではなくなった。
価値の比重は、労働者からロボットの制御コード、または、それを書く高スキルなエンジニアに移っている。現在起きているのは、低スキルの仕事の奪い合いである。大卒労働者が学歴に見合わない仕事に就き、低学歴の人々は、さらに給料の安い仕事を奪い合う状況に追いやられているのだ。
雇用のトリレンマ

雇用の機会は、仕事を自動化するテクノロジーと労働力の余剰によって大きく制約を受ける。将来は、高い生産性と高い給料、自動化に対する抵抗力、大量の労働者を雇用する可能性、という3つのうち、多くても2つしか満たせない、トリレンマ状態になる可能性が高い。
もちろん、Uberの運転手やWebを通じた単発の業務受託のように、テクノロジーが創出する雇用もあるだろう。しかし、破壊される雇用のほうが多いだろう。デジタル革命による労働力の余剰とはすなわち、労働力の希少性を激減させる現象である。同時に、労働者から、経済的報酬の分配を要求する交渉力や政治力を奪うという現象でもある。
賃金があまりに低い世界では、失業状態を選ぶ人が増える。働いて社会保障費を負担する人と、社会保障で生活する人が明確に分かれ、持てる者と持たざる者との政治的対立が激しくなるかもしれない。
【必読ポイント!】 デジタルエコノミーの力学
会社を動かすのは社内文化
「会社はなんのために存在するのか」。この質問に答えるのは意外に難しい。経済学者のロナルド・コースはこの質問に、どう答えたか。市場でのやりとりだけで目的を果たそうとすると、手間がかかりすぎるようになったとき、会社が組成される。彼はこうした答えを導き、ノーベル賞を受賞した。
しかし、コースの答えは完全なものではない。報酬と引き換えであっても、従業員が経営者の意のままに動くことなどありえないからだ。実際に会社を動かすのは、社内文化、別の言い方をすれば社内の情報処理メカニズムだ。
同じ会社にある程度の期間いれば、様々なものがどう噛み合って会社を動かしているのかが理解できる。経営学では「無形資産」とも呼ばれるこの社内文化が、企業の最も重要なテクノロジーになりつつある。どの情報が重要で、その情報を使って何をするか。この理解度が、とてつもない利益を上げる企業と倒産する企業を分かつといってよい。
21世紀のソーシャル・キャピタル

社内文化が会社の優劣を決めるのと同様に、会社の外にもそのような文化が存在する。著者はこれを「ソーシャル・キャピタル」と呼ぶ。