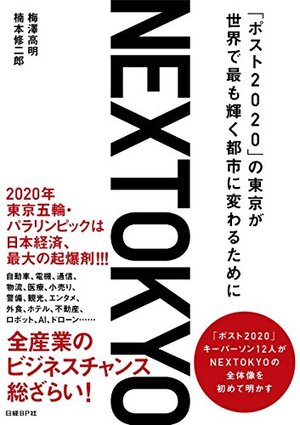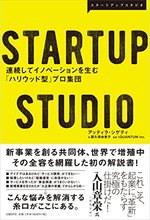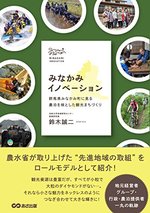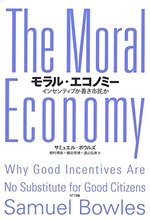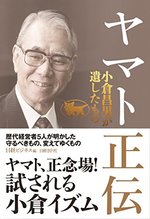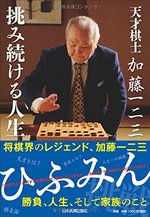NEXTOKYO
「ポスト2020」の東京が世界で最も輝く都市に変わるために
著者
梅澤 高明 (うめざわ たかあき)
A.T.カーニー日本法人会長。東京大学法学部卒、米マサチューセッツ工科大学(MIT)経営学修士。日産自動車を経て、A.T.カーニー入社。日米で20年に渡り、戦略・マーケティング・組織関連のコンサルティングを実施。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」コメンテーター。グロービス経営大学院客員教授。クールジャパン関連の政府委員会で委員を務め、戦略の立案・推進で政府を支援。
楠本 修二郎 (くすもと しゅうじろう)
カフェ・カンパニー代表取締役社長。早稲田大学政治経済学部卒業。リクルートコスモス、大前研一事務所を経て、2001年、現カフェ・カンパニーを設立。“コミュニティの創造”をテーマに約100店を運営するほか、商業施設などのプロデュースを手掛ける。クールジャパン関連の政府委員を歴任。一般社団法人東の食の会、一般財団法人NEXT WISDOM FOUNDATION、一般社団法人フード&エンターテインメント協会代表理事、東京発の収穫祭「東京ハーヴェスト」実行委員長。
A.T.カーニー日本法人会長。東京大学法学部卒、米マサチューセッツ工科大学(MIT)経営学修士。日産自動車を経て、A.T.カーニー入社。日米で20年に渡り、戦略・マーケティング・組織関連のコンサルティングを実施。テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」コメンテーター。グロービス経営大学院客員教授。クールジャパン関連の政府委員会で委員を務め、戦略の立案・推進で政府を支援。
楠本 修二郎 (くすもと しゅうじろう)
カフェ・カンパニー代表取締役社長。早稲田大学政治経済学部卒業。リクルートコスモス、大前研一事務所を経て、2001年、現カフェ・カンパニーを設立。“コミュニティの創造”をテーマに約100店を運営するほか、商業施設などのプロデュースを手掛ける。クールジャパン関連の政府委員を歴任。一般社団法人東の食の会、一般財団法人NEXT WISDOM FOUNDATION、一般社団法人フード&エンターテインメント協会代表理事、東京発の収穫祭「東京ハーヴェスト」実行委員長。
本書の要点
- 要点12020年にオリンピックを控え、あちこちで再開発が進む東京。しかし小ぎれいな複合施設が「金太郎飴」のように街にあふれても、魅力的な都市とはならない。
- 要点2東京の進化の方向性は「クリエイティブシティ」「テックシティ」「フィットネスシティ」という3つのキーワードで表される。
- 要点3これからの都市づくりにおいて重要なのは、きっちりとすべてをコントロールせず、遊べるカオスを残しておくことである。
要約
NEXTOKYOプロジェクトの視座
ポスト2020の持続的進化に向けて

Hanumanloylomfilm/iStock/Thinkstock
21世紀は都市の競争力が国家の優劣を左右する時代だ。魅力的な都市には世界中から企業と人材が集まり、イノベーションが数多く生まれ、さらなる発展を遂げる。
森記念財団都市戦略研究所の調査(2017年版)だと「世界の都市総合力ランキング」で東京は3位、A.T.カーニーの「グローバル都市調査」(2017年版)では4位だった。しかし世界への情報発信力や、人材(とくに外国人材)の層の薄さが弱みだと指摘されている。
いま東京には2020年の五輪・パラリンピック開催を契機とした、新たなチャンスが巡ってきている。訪日外国人の数は毎年過去最高を更新し、東京のあちこちで再開発が進められている状態だ。しかし最新鋭のオフィスビルやこぎれいなレジデンス、キラキラした複合施設が街にあふれたところで、世界中から有望な企業、卓越した人材を呼び寄せることができるのだろうか。
「ポスト2020」を見すえ、東京の持続的発展をめざすのであれば、産業や文化の政策と都市づくりを表裏一体で進めるような、大きなビジョンを描かなければならない。
「NEXTOKYO」の方向性

kokoroyuki/iStock/Thinkstock
各界のイノベーターを招いて未来の東京の姿を議論したところ、東京の進化の方向性は「クリエイティブシティ」「テックシティ」「フィットネスシティ」という3つのキーワードにまとまった。
1つ目のキーワードである「クリエイティブシティ」とは、「クリエイティブクラス」(教育・研究、プログラミング、芸術、デザイン、金融、法律などに携わる優秀な人材)が世界中から集まる街という意味だ。実現すれば東京の弱点とされている「世界への発信力」も飛躍的に向上するだろう。そのためには渋谷、新宿、池袋、秋葉原、浅草といった、都心にある街の個性を徹底的に磨き、同種のクリエイティブ人材が集積する「クリエイティブ・クラスター」を形成する必要がある。たとえば渋谷や原宿の場合、ストリートカルチャーの聖地として、若手クリエイターがその才能を存分に発揮できる街づくりをめざすといいだろう。
2つ目の「テックシティ」には、「先端技術を体験できる都市」「先端産業が集まる都市」という2つの意味がある。街なかに無料Wi-Fiスポットや充電コーナーを設置し、スマートフォンを利用した多言語のモバイルガイドを配置。AR(拡張現実)を用いた「ポケモンGO」のような街歩きゲームも、東京の魅力を発見してもらうための有効なツールとなる。さらに東京を自動運転車やロボット警備といった新たな技術の「実験場とショールーム」にすれば、世界中から先進企業が集まってくるのではないだろうか。
3つ目の「フィットネスシティ」とは、水と緑に彩られた健康的なライフスタイルが実現できる街というコンセプトだ。都心を自転車にやさしい街に変え、公園をもっと「開かれた場」としてシャワーやカフェを設置。ランニングやヨガなどを楽しむ人々の拠点とすることも一案である。「インスタ映え」する美しい公園やサイクリングコースは、都市の魅力とも直結する。
改革を加速させる特区戦略
「クリエイティブシティ」「テックシティ」「フィットネスシティ」という3つの方向性を実現するには、規制緩和が欠かせない。とくにクリエイティブ産業の核となる高度人材や専門人材は、いまこそ全力で誘致すべきだ。
これまでレストランのフロアマネージャーやヘアメイクといった分野の場合、外国人に技能ビザが発給されてこなかった。しかしNEXTOKYOチームが内閣府に対して提言を重ねた結果、「クールジャパン・インバウンド外国専門人材の就労促進」として、一定の要件を満たす場合に技能ビザが発行されることとなった。
また道路や公園、水際の使い勝手をよくするための規制緩和も必要だ。オープンスペースを活用したイベントは都市に活気を生み、クリエイティブ人材が能力を発揮する場ともなる。自治体、警察、所管官庁など複数の組織にまたがっているイベントの開催相談窓口を一元化し、開催許可基準を明確化していくことが求められる。
NEXTOKYOがつくる5つのビジネスチャンス
「医療」と「スポーツ」は有望な成長分野
東京の未来をつくる新産業・新サービスで有望なのが、「パーソナルヘルス」「スポーツ・エンターテインメント」「進化型モビリティ」「インテリジェント・セキュリティ」「マーケティング革新」の5つである。
「パーソナルヘルス」は高齢化問題に直面する日本で注目を集めている分野だ。つねに呼吸や脈拍の状態を監視する「常時バイタル監視」、ダイエット支援や血糖値の定期的診断による生活習慣病の「モニタリング」、ロボット義足の実用化などにかかる期待は大きい。
また「スポーツ・エンターテインメント」も、大きな成長が予想される分野である。ICT(情報通信技術)を活用してスタジアムの「体験価値」を向上させることも可能だろうし、VR(仮想現実)技術を用いたスポーツ中継も有望視されている。
「ロボットが守る街」に自動走行タクシーが走る

chombosan/iStock/Thinkstock
「進化形モビリティ」にも期待がかかる。自動運転技術の革新性は言わずもがなだ。人の移動や物流を根本的に変え、産業構造に大変革をもたらす可能性がある。
さらに世界中から人を呼びこむうえで、都市のセキュリティ対策もますますその重要性を増している。これからのセキュリティ対策では高度な映像解析技術やロボット、すなわち「インテリジェント・セキュリティ」が主流になっていくはずだ。すでに海外では日本企業の技術を採用し、街なかのカメラで要注意人物や放置物などを自動的に発見・アラートするシステムが実用化されている。「ロボコップ」のように、不振な人物を発見・追跡・通報するロボットが東京の街なかを守っていれば、「テックシティ」として大きなPR効果も期待できるだろう。
「駅ナカのバーチャルストア」の可能性
新しいモノやサービス、情報などに出合う接点には、常にビジネスチャンスが隠されている。いま技術革新とともに、「マーケティング革新」の動きが出はじめた。
「電子看板」と称されるデジタルサイネージはその代表例だ。画面の大型化や高精細化の実現により、紙のポスターには不可能な「画像の切り替え」や「動き」、「多言語化」などを実現。見ている人の顔などから性別・年代を推定し、「個人最適化」するデジタルサイネージも開発が進められている。
またタッチパネルを搭載することで、看板を「バーチャルストア」にすることもできる。商品を流通ルートに乗せる前に「陳列」できるので、テストマーケティングの場としても有効かもしれない。バーチャルストアが駅のホームに設置されるようになれば、電車の待ち時間が購買行動の時間に変化する可能性もある。
TOKYO成功の要件
「遊び」のある都市デザインを
NEXTOKYOのプロジェクトメンバーには建築家、クリエイティブディレクター、起業家、コンサルタントなど多彩な顔ぶれがならぶ。複数の専門分野を持っている者も多い。
広告やメディアアートを手がけるライゾマティクス代表の齋藤精一氏や、ハーバード大学大学院教授で建築家の森俊子氏が強調するのは、「遊び」をつくることの重要性だ。「おせち料理」のように、建築や機能をギュウギュウ詰めにしてはならないし、なにかを一律で禁止したり強制したりしてもいけない。「こうだったらやってもいいよ」と許容する“お節介なお兄さん”のような街のプロデューサーが、東京には求められているという。
アーティストのスプツニ子!氏は、こうした問題意識を「きっちりとすべてをコントロールせず、遊べるカオスを残しておくことが大事」と端的に表現している。
「モノづくり」から「クリエイティブ」への架け橋
製造業は日本の基幹産業のひとつである。しかし新興国の追い上げもあり、大量生産・低価格化という過去のビジネスモデルが通用しなくなっているのは明らかだ。
アップルやダイソンのようにクリエイティブな製品やサービスを提供する企業を、日本や東京にどう生み出していくのか。ハードウェア製造のスタートアップを支援するABBA Lab(アバラボ)代表の小笠原治氏は、東京にはモノ作りとサービス提供のプロの両方が集まっていることを強調する。ただ「モノのサービス化」にはどうしても「使って試す場」が必要だ。幸いなことに東京には実験や挑戦を許容するキャパシティがあるというのが小笠原氏の考えである。
一方で「デザインエンジニアリング」という観点で新たなモノづくりに挑んでいるTakram代表の田川欣哉氏は、英国のデザイン大学院で教鞭をとっている経験から、「ビジネス」「テクノロジー」「クリエイティブ」の3つが理解できる「BTC型リーダー」の育成が大切だとしている。
訪日外国人の楽しみは「体験」に尽きる

oneinchpunch/iStock/Thinkstock
2020年の東京オリンピック招致の際に用いられ、流行語となった「おもてなし」は、これからの東京に必須の要素だ。ニューヨークやロンドンといった先進都市と比較すると、東京のエンターテインメント産業にはまだまだ改善の余地が多い。
グローバルに展開されているシティガイドの東京版、『タイムアウト東京』を立ち上げた伏谷博之氏は、東京の音楽やファッションのレベルの高さを指摘する。重要なのはそうしたカルチャーをどう世界に発信していくかだ。「訪日外国人の楽しみは『体験』に尽きるのだから、もっと外国人の視線によりそった、すなわち“DO”の提案を行っていくこと」が欠かせないと伏谷氏はいう。
クラブや深夜のエンターテインメントを規制する風営法の改正に尽力した弁護士の齋藤貴弘氏は、ナイトカルチャーのもたらす経済的な価値を訴えている。加えて夜の独特の雰囲気のなかからは新しいものが生まれやすく、文化的にも価値がある。実際に欧州の都市では「夜の市長」がネット投票で選ばれ、行政や地域と連携する役割を担っているという。

この続きを見るには...
残り0/4058文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.05.01
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約