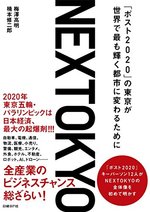ヤマト正伝
小倉昌男が遺したもの
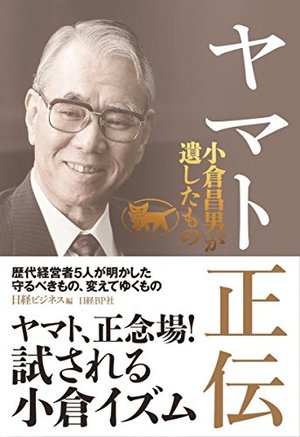
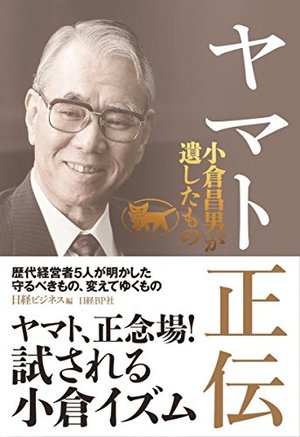
著者
日経ビジネス 編集
「日経ビジネス」は1969年の創刊以来、常に時代の一歩先を見通し、注目すべき企業・人物への直接取材をもとに独自の視点で、実践に役立つ情報"を発信し続けている。
「日経ビジネス」は1969年の創刊以来、常に時代の一歩先を見通し、注目すべき企業・人物への直接取材をもとに独自の視点で、実践に役立つ情報"を発信し続けている。
本書の要点
- 要点1「サービスが先、利益は後」が小倉イズムの原点であり、ヤマトグループの根幹理念である。
- 要点2小倉さんは「鳥の目」で市場を俯瞰し、宅急便の構想を描いた。イノベーションを起こすのは社長の仕事である。
- 要点3現場の第一線で働くセールスドライバーこそがヤマトの要であり、お客様にとって良い社員が高く評価される制度が欠かせない。
- 要点4社員一人一人が経営者の意識を持ち、自らより良いサービスを考え実行することが会社の成長につながる。
要約
脈々と継承される「小倉イズム」
63歳定年制

marchmeena29/iStock/Thinkstock
現在ヤマトホールディングス特別顧問を務める有富慶二さんが、当社に入社したのは1963年のことだ。当時小倉昌男さん(以下、小倉さん)は取締役で、創業者である実父・康臣さんが社長を務めていた。
小倉さんが残したルールに、社長の「63歳定年制」がある。小倉さんは1987年にヤマト運輸社長を退任し、会長になった。そして後任の社長たちもこのルールを守っている。小倉さんはなぜこのルールを作ったのか。
大和運輸(現ヤマト運輸)の創業は1919年。当時馬車や荷車の運送が一般的だったところ、康臣さんはトラックを持ち込み、運輸業を始めた。これが大当たりし、関東一円にネットワークを作り、大成功を収めた。しかし戦後、大阪の電機メーカーから首都圏に家電製品が輸送されるようになると、西濃運輸、福山通運などのトラック運送会社がそれを担うようになった。
小倉さんも康臣さんに参入を促したが、康臣さんは「長距離輸送は鉄道の仕事」という固定観念にとらわれ、それを拒み続けた。結局は参入を果たしたが、この出遅れが影響して、銀座の社屋を売却せざるを得ないほど会社は苦境に陥った。
小倉さんが社長に就いたのは1971年、康臣さんが81歳の時だ。小倉さんはこの経験を通じ、社長の判断ミスで会社を窮地に陥れてはいけないと、63歳定年制を設けた。過去の成功体験にとらわれず、時代に合った判断をするには、これくらいの年齢が妥当だと判断したのだ。
優秀な経営者を生み出すために
2005年、小倉さんが逝去した。同年、ヤマト運輸は持ち株会社制に移行し、「ヤマトホールディングス」が誕生した。有富さんはこの年、優秀な人材をトップに選出するための「指名報酬委員会」を設立した。これは、社内外から集めたメンバーが、第三者的な視点で幹部候補を選ぶシステムである。現在までヤマトグループが生き残れたのは、小倉さん亡き後もイノベーティブな人材が社長を務めてきたからに他ならない。
経営者はこれからの時代を先読みし、革新的な挑戦ができる人材でなければならない。いつまでもカリスマに頼っているようでは、会社の存続は危うい。
人材の多様性を高めるため、社外から幹部候補を招くようになったのもこの年だった。小倉さん以降の経営トップは生え抜き社員ばかりであった。「外の血」を入れることは、プロパー幹部の意識改革を促すことにもなる。イノベーションを起こすには、過去の制度を盲目的に守るのではなく、世の中や環境に合わせて、多様なバトンタッチを模索できるシステムが必要だったのだ。
イノベーションは社長が起こす ~宅急便の誕生~

shironosov/iStock/Thinkstock
長距離輸送事業に乗り出した大和運輸だが、当時の利益率は著しく低かった。その要因は、人件費が高く、運賃単価が他社と比べて低いことだった。当時、運賃は距離と重量に比例しており、輸送距離が長く総重量が重いほど、単価が安くなる仕組みだった。
利益を上げるためには、トラックの積載効率を高めるべきだ。そう、誰もが信じていたところ、小倉さんは個人間の輸送に着目した。当時、個人間の輸送を担っていたのは郵便小包で、取扱量は年間約1億8000万個。このうちの何分の一かを運べれば十分チャンスはある。小倉さんは「鳥の目」で市場を俯瞰し、宅急便の構想を描いた。役員たちは、不特定多数が対象で単価の低い小口輸送事業に対して懐疑的であったため、反対した。しかし小倉さんは諦めず、1976年1月、ついに宅急便をスタートさせた。郵便小包より質の高いサービスを提供することで、小口荷物の市場は爆発的に広がっていった。
社会の変化に合わせ、人々が潜在的に求めている事業を展開し、生活を根底から変える。こうしたイノベーションは経営トップにしかできない仕事なのだ。小倉さんは、宅配便開発を通じてそれを体現したのである。
【必読ポイント!】 「サービスが先、利益は後」
不可能からの出発、クール宅急便の開発
ヤマトグループが最も大切にしている言葉。それは「サービスが先、利益は後」だ。お客様の立場で良いサービスを追求すれば利益は後から付いてくるという意味で、小倉哲学を象徴したフレーズでもある。
2006年にヤマトホールディングス社長に就任した瀬戸薫さんは、クール宅急便の開発などを通じて、若い頃から小倉さんの意思決定を間近で見てきた。
地方の人々は都会の子供や孫に、宅急便で地元の新鮮な海産物を送るようになった。しかし、常温では送れないため、発砲スチロールの箱に氷を入れていた。ところが、受取手が不在の時は氷が溶け、魚が傷んでしまう。「思いを込めて送った新鮮な魚が、最高の状態で届かない」。当時九州の支店長を務めていた瀬戸さんは、この状況を苦々しく思い、クール宅急便の開発を指揮することとなった。宅急便登場から10年経った、1986年のことだった。

この続きを見るには...
残り1847/3837文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.05.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約