渋沢栄一 日本の経営哲学を確立した男
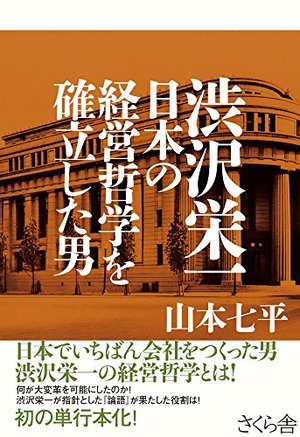
渋沢栄一 日本の経営哲学を確立した男
著者
著者
山本 七平(やまもと しちへい)
1921年、東京都に生まれる。1942年、青山学院高等商業学部を卒業。野砲少尉としてマニラで戦い、捕虜となる。戦後、山本書店を創設し、聖書学関係の出版に携わる。1970年、イザヤ・ベンダサン名で出版した『日本人とユダヤ人』が300万部のベストセラーに。以後、「日本人論」で社会に大きな影響を与えてきた。その日本文化と社会を分析する独自の論考は「山本学」と称される。評論家。山本書店店主。1991年、逝去。
著書には『「空気」の研究』『私の中の日本軍』(以上、文藝春秋)、『日本はなぜ敗れるのか』(角川書店)、『帝王学』(日本経済新聞社)、『論語の読み方』(祥伝社)、『なぜ日本は変われないのか』『日本人には何が欠けているのか』『日本はなぜ外交で負けるのか』『戦争責任と靖国問題』『精神と世間と虚偽』『戦争責任は何処に誰にあるか』『池田大作と日本人の宗教心』(以上、さくら舎)などがある。
1921年、東京都に生まれる。1942年、青山学院高等商業学部を卒業。野砲少尉としてマニラで戦い、捕虜となる。戦後、山本書店を創設し、聖書学関係の出版に携わる。1970年、イザヤ・ベンダサン名で出版した『日本人とユダヤ人』が300万部のベストセラーに。以後、「日本人論」で社会に大きな影響を与えてきた。その日本文化と社会を分析する独自の論考は「山本学」と称される。評論家。山本書店店主。1991年、逝去。
著書には『「空気」の研究』『私の中の日本軍』(以上、文藝春秋)、『日本はなぜ敗れるのか』(角川書店)、『帝王学』(日本経済新聞社)、『論語の読み方』(祥伝社)、『なぜ日本は変われないのか』『日本人には何が欠けているのか』『日本はなぜ外交で負けるのか』『戦争責任と靖国問題』『精神と世間と虚偽』『戦争責任は何処に誰にあるか』『池田大作と日本人の宗教心』(以上、さくら舎)などがある。
本書の要点
- 要点1渋沢栄一は、多くの挫折を経験している。しかしそれらをものともせず、自身の運命を切り開いている。
- 要点2渋沢栄一は、社会とは常に変化していくものだという意識を持っていた。過去にこだわらず、社会に対応していくことをよしとし、労働運動やストライキを支援したこともあった。
- 要点3渋沢栄一は柔軟な考え方をする性質であったが、家族のあり方についてなど、頑として意見を変えない一面もあった。
- 要点4渋沢栄一は、『論語』を基準にして人を判断していた。
要約
【必読ポイント!】 経営者としての渋沢栄一
何度も挫折を経験している

Marjan_Apostolovic/iStock/Thinkstock
渋沢栄一(以下、栄一)の91年間の人生は、挫折の連続であった。まず、尊王攘夷思想を実践すべく高崎城の乗っ取りを計画するが、失敗に終わる。その後、江戸で知己になった家老の平岡円四郎に斡旋されて徳川慶喜に仕えるも、平岡円四郎が暗殺されてしまう。徳川慶喜の弟、徳川昭武に随従してフランスに行けという命を受け、留学のつもりで出国するが、幕府が瓦解してしまう。帰国したときには半ば犯罪人扱いという始末だ。
栄一は明治2年(1869年)には、静岡で「商法会所」という、商社と銀行を合わせたような会社をつくる。会社を設立したものの、今度は、明治政府に無理やりスカウトされ、民部省に勤めざるを得なくなってしまう。政府の中で出世し、大蔵省大丞(事務次官)の地位にまでのぼりつめるが、大蔵卿の大久保利通と衝突し、退官する。
このように、栄一は、何度も挫折を経験している。しかし彼は、その挫折をバネにして運命を切り開いている。彼にとって挫折がマイナスになっていないのが、興味深い点である。
柔軟な考え方をする
栄一は、たいへん合理的なものの考え方をした。自分が持っている情報の中で考えを一つにまとめていたとしても、新たな情報が入ったら、その考えをまったく変えてしまう。考えを変えることに対して、抵抗がなかったのである。
これを裏付ける例として、高崎城乗っ取り計画の中止が挙げられよう。栄一は、血洗島村というところにいたときに、この計画を企てた。しかし、当時最も先進的な地であった京都から戻ってきた尾高長七郎から、乗っ取りをやめるよう進言される。その結果、計画中止を決断したのである。
パリの証券取引所を訪れたときも同様である。京都や大坂で学び、金融知識を持っていた彼は、パリで銀行業務を見ても、それが理解できず驚くということがなかった。むしろ、銀行制度を調べ、吸収するよう努めたのである。新たな情報を貪欲に手に入れて、最新の情報に基づいて物事を判断する点は、彼の特徴だといえる。
偏見がない

MarkUK97/iStock/Thinkstock
栄一は、社会とは常に変化していくものだという意識を持っていた。過去にこだわらず、社会に対応していくことをよしとしていたのである。
大正元年、「友愛会」が創立され、過激な労働運動である「大正労働運動」が起こる。そのとき栄一は、友愛会の創立者である鈴木文治と親しくし、相談相手になっていただけでなく、労働者側に同調した主張をしていた。さらに大正14、15年頃には、長野県の製糸工場で起こった女工のストライキに対して援助している。資本家であった彼にしては、不思議な態度だといえる。
彼の偏見のない態度は、労働運動にとどまらない。彼がフランスに行ったときに書いた日記『航西日記』には、バターを塗ったパンについて「味(あじわい)甚(はなはだ)美なり」と記されている。当時の日本人は、バターのにおいを非常に嫌ったものだ。しかし、栄一はまったくそんなふうに感じていない。コーヒーについても、彼は「すこぶる胸中を爽(すこやか)にす」と評している。
一般的に、食物においては偏見が先に立つものだ。しかし彼には、偏見というものがまったくない。これも、彼のおもしろい点である。
頑として変えない面を持っている
前項で紹介したように、栄一は、柔軟性を持っていた。しかし同時に、「徳川時代人」としての考え方を頑として変えない面もあった。その一面について、家族のあり方と会社のあり方という視点からみてみよう。
まず、栄一の家族に対する態度である。徳川時代においては、親権はあるが、家長権というものは存在しない。本家、分家とは名前だけであって、それぞれ独立した核家族であり、経済的水準が高ければどんどん分家していくものであった。さらに、隠居して経営権を相続人に渡すと、相続人には隠居を扶養する義務が生じる。もし相続人が隠居を扶養しなければ、相続を剥奪することができた。実際に栄一は、当然のように親権を行使し、勘当していた。
次に、会社に対する態度である。徳川時代においては、血縁がない人たちであっても、利害さえ一致すれば、一揆という集団が結成されたものだった。たとえば寺を建立するときなどに一揆が結成され、みんなが協力し合っていたのである。
栄一がつくった日本最初の会社「商法会所」は、一揆と同じような設立方法であった。実際に「商法会所」の定款を見ると、確かに彼がヨーロッパで学んだ知識も活かされているものの、一揆のような日本の伝統的な方法も取り入れている。このように、栄一は徳川時代を生きた人間としての考え方も残しており、変える必要がないと考えたものに関しては、これまでの方法を貫くという面もあった。
論語を基準にして人を見る
栄一は、晩年、教育事業や社会事業に尽力した。一橋大学の前身である東京高商をつくり、二松学舎を援助して、漢学的な伝統を日本に残そうとしたのである。
加えて彼は、『論語講義』を著している。日本の伝統を守ると同時に、西欧的な教育も重要であると考えていたのだった。
彼は人を見るとき、『論語』を基準にして評価していた。人材の採用においても同様である。なぜなら、日本における組織の上下秩序はヨーロッパ的ではなく、儒教的だからだ。ヨーロッパの組織と日本の組織の違いを、彼ははっきり認識していた。
23歳から33歳までの渋沢栄一の11年間
この11年間を切り取る理由

BrianAJackson/iStock/Thinkstock
栄一の人生の11年間を切り取って見てみよう。この11年間とは、高崎城の乗っ取りを計画したときから、第一国立銀行を設立して総監役に就任したときまでを指す。彼の年齢でいうと、23歳から33歳まで、日本の年代でいうと文久3年から明治6年までの間である。

この続きを見るには...
残り2148/4494文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.05.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











