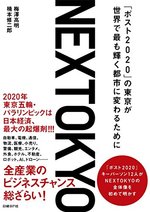『週刊文春』と『週刊新潮』の作り方
テレビ局が週刊誌スクープに群がる理由

近年、『週刊文春』が衝撃的なスクープを連発し、数あるメディアの中でも際立った存在感を示している。そのスクープは影響力の大きさから「文春砲」と呼ばれるほどだ。『週刊文春』が何を報じるかが、テレビのワイドショーの重大な関心事となり、そのスクープがタダで勝手にパクられていた。
そこで、現在編集長を務める新谷学氏は、『週刊文春』の記事をテレビで使うときは、記事使用料を支払うことをシステム化した。この動きに『週刊新潮』も続いている。
テレビ局が週刊誌のスクープに群がるのには理由がある。それは、自前で取材班を出すよりも、週刊誌が撮った映像や音声を買った方が安価であり、クオリティーの高いネタが入手できるからである。
『週刊新潮』と『週刊文春』のはじまり
『週刊新潮』が創刊されたのは1956年のことだ。同誌は、結論をあえて書かなくてもいいというスタンスで、関係者の証言などから事件全体を描いてみせる「藪の中スタイル」を作り上げた。週刊誌の取材記者は、自分の目と耳をフルに使って、取材対象そのものを全部描いていく。これは、新しいジャーナリズムの礎を築いたといえる。
また、新聞が翌日、翌々日に何を書くかを想像し、別の視点で事件を捉えることによって独自性を出した。たとえば全日空下田沖墜落事故が起きた際、新聞各紙は亡くなった人たちについて報道した。一方『週刊新潮』は、乗客のキャンセル名簿を入手して、生き延びた人の視点から「私は死神から逃れた――7時35分をめぐる運命の人々」という記事を書いた。花田氏は、それが読者の嗜好に合っていたのだと語る。
『週刊文春』は、常に『週刊新潮』を参考にして、部数を伸ばしていった。草創期は連載小説で読者を増やしていった。最初に多くの読者を掴んだのは、司馬遼太郎氏の小説『燃えよ剣』だったといわれている。
アンカーマン・データマンシステム
『週刊新潮』の強みは、「アンカーマン・データマンシステム」にある。デスクに指示された対象者を徹底的に取材して、データ原稿を書く記者を、データマンと呼ぶ。そして、それを原稿にまとめるデスクのことをアンカーマンと呼ぶ。新卒の記者に取材記事(データ原稿)を書かせて、どのように取材すべきか、どういう視点を持つべきかを、何年にも渡って学ばせる。そして、文章力や分析力に長けた、選ばれしデータマンのみをアンカーマン(デスク)にさせる。
このように役割分担し、教育制度を作ってきた。データマンに校了ギリギリまで取材を粘らせることによって、原稿がより充実したものになる。結果として、誌面全体の内容・文章が一定水準の高さを保てるため、週刊誌としての質が担保されるというわけだ。
一方、『週刊文春』にはそのような明確な役割分担や教育制度がない。あまり経験のない記者でも、いきなり原稿を書かされる。逆に言えば、若手であっても、ネタを見つけて来た人が、特集記事を担当することもある。そのネタに対する強い思い入れが、『週刊文春』自体の勢いにもつながるという考えのもとだ。しかも、社員編集者は2年ほどで異動になっていく。よって、現場ではフリーの記者たちの力が物を言う。
また、スクープがとれるかどうかは編集長の資質にかかっているところが大きいというのが、花田氏の見解である。門田氏によると、『週刊文春』の現編集長、新谷学氏は、デスク、取材記者のモチベーションを上げるのがうまいという。