外国人が熱狂するクールな田舎の作り方
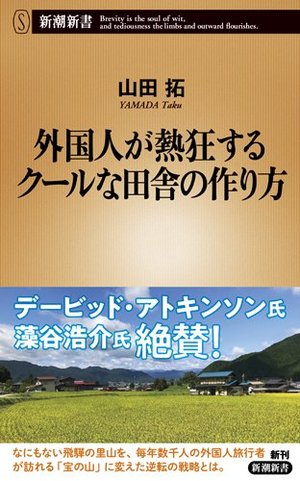
外国人が熱狂するクールな田舎の作り方
著者
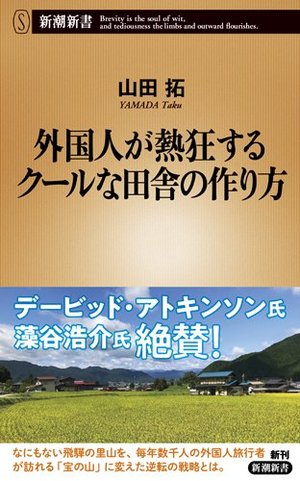
著者
山田 拓 (やまだ たく)
1975年奈良県生まれ。株式会社「美ら地球」代表取締役。横浜国立大学大学院工学研究科修了。コンサルティング会社勤務の後、525日間の世界旅行を経験。2007年、「美ら地球」を創設。
1975年奈良県生まれ。株式会社「美ら地球」代表取締役。横浜国立大学大学院工学研究科修了。コンサルティング会社勤務の後、525日間の世界旅行を経験。2007年、「美ら地球」を創設。
本書の要点
- 要点1地方では、仕事の進め方や意思決定の基準が都会とは異なる。コミュニティが小さいだけに、人間関係が重要なファクターとなる。
- 要点2地元の人にとっては見慣れた日常風景であっても、外国人観光客や都市生活者は非日常であるため、観光資源となりえる。
- 要点3著者が目指すツーリズムとは、「ゲストのhappy」「地元企業のhappy」「ひだびとのhappy」「ワカモノのhappy」の4つのhappyを実現するものだ。事業と「飛騨の暮らし」は密接に結びついているので、 特に地元企業とひだびとのhappy」に注力している。
要約
著者の考えを形づくったもの
アメリカで働いて気づいたこと
グローバルカンパニーに就職し、アメリカでコンサルタントとして社会人のスタートを切った著者。現地の自由な気風を楽しみつつも、アメリカ社会の資源の浪費ぶりなどが目につくようになり、「こんなライフスタイルがいつまでも持続可能なのだろうか」と思うようになった。
勤務3年目になり転職を決めたころ、米同時多発テロ事件が起こった。事件を通して、世界にはさまざまなカルチャーや思想を持つ人々がいることを眼前に突きつけられた気がした。先進国しか知らない自分に気づき、世界の多様な部分に触れた上で自分の考えや行動を決めなければならないと感じたという。
自然とともに生きるということ

paulafrench/iStock/Thinkstock
30歳という節目を迎えるタイミングで、日本とアメリカ以外の国をもっと知りたいという気持ちが再燃した。いろいろな選択肢を検討した結果、南米やアフリカを中心とした放浪の旅に出ることになった。旅のテーマは「持続可能性(サステナビリティ)」に設定した。
アフリカに立ち寄った際、ライオンを観察する機会を得た。意外だったのが、「百獣の王」ライオンの生態から、威張ったような様子が微塵も感じられなかったということだ。人間である自分たちの方こそが、地球環境に負荷をかけていると感じた。
同様のことは発展途上国の暮らしからも感じられた。現地では、人々は日の出とともに活動を始める。そして日が暮れるのと同時に一日が終わるのだ。自然とともにあるライフスタイルの美しさに感銘を受けた。
日本にいると見えない日本の姿
世界遺産マチュピチュは、旅の目的地の一つだった。舗装されていないインカ帝国時代の石畳の上を歩き、遺跡を目指した。インカ帝国というと古代文明の一つのように感じてしまいがちだが、その歴史は13〜16世紀なのだという。日本ではちょうど戦国時代にあたる。他国の歴史と自国の歴史を照らし合わせてみると、自分で思っている以上に日本の歴史はずっと長く、文化の蓄積があるのだと気づいた。それを知らず、異国の世界遺産ばかりに目を向けていた自分が恥ずかしく思えた。
ウガンダでは、現地の青年の言葉にハッと目が覚める思いがした。「君たちがとても羨ましい。君は僕の国ウガンダに来ることが出来るけど、僕たちは絶対に君の国日本に行くことは出来ないだろう」と何気なく言われたのだ。さらに現地では、日本企業を賞賛する声も聞かれた。日本という整えられた環境で努力して成果を出した気になっていたが、もしウガンダに生まれていたらどうだっただろう。日本に生まれたというだけで、自分たちは恵まれていると言えるのかもしれないと痛感した。
自然と共生するライフスタイルを求めて
難航した飛騨への移住

Lucas Allen/DigitalVision/Thinkstock
525日間にも及んだ旅を通じて、日本が実はパワフルな、可能性を秘めた国だということに気づかされた。日本各地で継承されてきた原風景やそこでの営みの一部となって生活したい、そうしたエリアで循環型の持続可能なライフスタイルを実践したいという思いから、帰国後は「田舎ぐらし」をすることに決めた。
ところが、日本の田舎に移住するというのは想像以上に難しかった。古民家や町家などを中心に各地を訪れたが、空き家はあっても先祖代々の家を譲ってくれる人は誰もいなかったのだ。当時はまだ、行政の移住・定住政策が広まっていなかった時期である。
その後、ツテを頼って出会ったのが、飛騨古川の男性だった。この男性も移住には反対だったのだが、あるとき、チャンスが巡ってきた。
実はこの男性、市長から観光協会の会長就任を打診されていた。ずっと断り続けていたのだが、著者が外国人観光客向けのガイドブック制作を提案したことで、著者を戦略アドバイザーとして迎えることを条件にオファーを受けようという気になったのだ。
借家に住むつもりが町家を高値で購入することになるなど、なんとも言えない思いも経験したが、こうして著者の移住はめでたく実現する運びとなった。そして「世界に通じる飛騨市」をスローガンに掲げる観光協会とともに歩んでいくことになった。
都会とは違う地方での仕事の進め方
東京の企業では通常、仕事の役割分担が決められる。基本的には各自がそのミッションをクリアすることに専念すればよく、それによってプロジェクトが計画通りに進行していく。だがこのやり方は地方では機能しなかった。地方のメンバーは、自らのミッションを与えられるだけではどう動けばよいかわからず、こちらが想像する以上に精神的負担を感じてしまったのだ。
また、地方の人間関係は都会とは比べものにならないほど密接なものである。

この続きを見るには...
残り2592/4483文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.05.26
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











