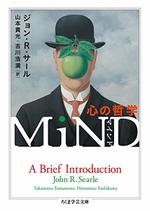14歳からの資本主義
君たちが大人になるころの未来を変えるために

著者
丸山 俊一 (まるやま しゅんいち)
1962年長野県松本市生まれ。近代経済学からマルクス経済学まで、社会思想から現代思想まで幅広く学び、慶應義塾大学経済学部を卒業後、NHK入局。ディレクターとして、NHKスペシャル「日本再建」でフランスの道路建設の実情を、NHKスペシャル「英語が会社にやってきた」では社内英語化を推進する日産自動車、ルノー本社などを取材。その後プロデューサーとして「英語でしゃべらナイト」「爆笑問題のニッポンの教養」「ソクラテスの人事」「仕事ハッケン伝」「ニッポン戦後サブカルチャー史」などを企画開発。現在も「欲望の資本主義」「人間ってナンだ? 超AI入門」「地球タクシー」「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」「ニッポンのジレンマ」他、時代の潮流を捉えた異色の教養番組を企画、制作し続ける。現在NHKエンタープライズ番組開発エグゼクティブ・プロデューサー。
著書に『結論は出さなくていい』(光文社新書)、『すべての仕事は「肯定」から始まる』(大和書房)、制作班との共著に『欲望の資本主義』『欲望の資本主義2』(ともに東洋経済新報社)、『哲学の民主主義』(幻冬舎新書)、『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』(NHK出版新書など)。早稲田大学、東京藝術大学で非常勤講師も務める。
1962年長野県松本市生まれ。近代経済学からマルクス経済学まで、社会思想から現代思想まで幅広く学び、慶應義塾大学経済学部を卒業後、NHK入局。ディレクターとして、NHKスペシャル「日本再建」でフランスの道路建設の実情を、NHKスペシャル「英語が会社にやってきた」では社内英語化を推進する日産自動車、ルノー本社などを取材。その後プロデューサーとして「英語でしゃべらナイト」「爆笑問題のニッポンの教養」「ソクラテスの人事」「仕事ハッケン伝」「ニッポン戦後サブカルチャー史」などを企画開発。現在も「欲望の資本主義」「人間ってナンだ? 超AI入門」「地球タクシー」「ネコメンタリー 猫も、杓子も。」「ニッポンのジレンマ」他、時代の潮流を捉えた異色の教養番組を企画、制作し続ける。現在NHKエンタープライズ番組開発エグゼクティブ・プロデューサー。
著書に『結論は出さなくていい』(光文社新書)、『すべての仕事は「肯定」から始まる』(大和書房)、制作班との共著に『欲望の資本主義』『欲望の資本主義2』(ともに東洋経済新報社)、『哲学の民主主義』(幻冬舎新書)、『マルクス・ガブリエル 欲望の時代を哲学する』(NHK出版新書など)。早稲田大学、東京藝術大学で非常勤講師も務める。
本書の要点
- 要点1資本主義ではいつも「増える」ことが望まれているが、現代では世界の総需要の不足が問題視されている。しかしそもそも成長は「手段」であって、「目的」ではないのではないか。
- 要点2ポスト産業社会では、差異化された感情も商品となりうるが、その商品価値は不確かで危ういものである。
- 要点3技術革新によるデジタル化は格差を拡大させ、社会の分断を生み出す。
- 要点4これまで経済学は「欲望」を科学的に分析してきたが、これからは欲望の背景にあるさまざまな思いについても考慮しなければならない。
- 要点5おカネさえあれば誰もが参加できる場という意味で、市場には大きな価値がある。
要約
「資本主義」とはそもそもなんなのか
資本主義と市場

arthobbit/gettyimages
「資本主義ってなんですか?」と問われると、大人でもシドロモドロになってしまうのではないだろうか。「資本主義」というものを定義し、本質的なところを理解するのはじつのところ難しい。
資本主義は「資本」から価値を生み出すことを原動力としている。また「時間」も大事な要素で、より早く、より多くつくれるほうが「価値」があるとされている。価値とはそれを「買いたい」という人が現れることだ。たとえば1個100円のパンを「買いたい」というのは、そのパンが「100円を出すだけの価値がある」ということを意味している。もし値段が高すぎれば、売れ残ってしまうかもしれない。売る側の思いと、買う側の思いがちょうど一致するところで値段が決まり、それがそのものの価値となる。「市場」とは、この値段と価値を決める場所のことだ。
「経済学の父」とも呼ばれるイギリスの思想家アダム・スミスは、市場における売り手と買い手が利益の最大化を目指すと「見えざる手」が働き、「需要」と「供給」が交わる点で、社会全体にとって最適な「価格」が実現するとした。
ただしスミスが「見えざる手」という言葉を唱えたのは、著書『国富論』のなかでは一度だけだ。加えてもう1冊の著書『道徳感情論』で、他者への「共感」の重要性を強調していることも忘れてはならない。スミスの真意は、自らの欲望を最大化することの言い訳として、「見えざる手」という言葉を用いることではなかったはずである。
資本主義のなにが問題なのか

phototechno/gettyimages
ひとたび利益を増やす「競争」が始まれば、資本の「自己増殖」が終わることなく続いていく。資本主義とは資本の「自己増殖」を原動力とする運動であり、欲望が欲望を生む、果てしない過程だと定義できるだろう。
現在の資本主義のなにが問題なのか。アメリカの経済学者ジョゼフ・スティグリッツは、世界の総需要の不足こそが問題だとしている。スティグリッツによれば、「不平等の増大」によって貧困層から富裕層へと富が吸い上げられる一方で、富裕層が貧困層ほどおカネを使わないことが、成長のブレーキとなっているという。「テクノロジー」、「インフラ」、「教育」に政府がもっと投資し、気候変動に適応するための新エネルギーへの移行や都市構造の変革を行えば、巨大な需要を見つけられるというのが、スティグリッツの提示する対策だ。
一方でチェコの経済学者トーマス・セドラチェクは、そもそも資本主義において市場は「手段」であり、市場の「成長」は「目的」ではないと主張する。そして現代の資本主義が“成長”資本主義になっていることに疑問を呈する。資本主義において成長が重視されるようになったのは、かつてはほとんどの宗教で禁じられていた「利子」の誕生による。「時はカネを生む」というしくみこそが資本主義の最大の発明であり、同時にもうあと戻りのできない「禁断の果実」だったのだ。「成長」が必要条件となると、本来「自由」なはずの資本主義は「不自由」なものとなってしまう。セドラチェクは成長なしでも維持できる資本主義のスタイルはあると主張するものの、「成長」か「安定」かという問題は依然として現代の経済学者の多くを悩ませている。
【必読ポイント】 デジタル革命、ポスト産業社会の資本主義
「共感」という商品
市場で商品をより高く売るには、商品に「付加価値」をつけ「差別化」することが重要となる。その考え方の先にあるのは、「差異さえあれば商品になる」という発想だ。しかしそれはともすると、どんなものでも「商品」になるということに結びつきかねない。
とくに「共感」などの心の領域が商品化している点には注目すべきだろう。こうした商品は従来の商品と違った特殊性があり、価格の決定が主観に大きく依存している。
「価値」には大きく分けて、おカネで交換できる「交換価値」と、買い手が商品を「使用」するときに感じる「使用価値」という2つの種類がある。たとえば10万円の交換価値があるコンサートのチケットでも、関心がない人にとって使用価値は低い。だがネットで「あのコンサートはスゴイ!」と騒がれているのを目にしたら、心が揺れて使用価値は上がるのではないだろうか。するといつの間にか、「すばらしいコンサートだから○万の価値」という論理が、「○万もするからすばらしいコンサート」という感覚にすり替わってくる。
私たちの生きているポスト産業社会において,「共感」「泣ける」「すっきり」などの「商品」の価格は、人々の揺れる心が生む「言い値」となりやすい。本来なら「かけがえのないもの」であるはずの感情も、いつの間にか「交換可能」なものに置き換わってしまいかねないのだ。
「デジタル革命」が生み出すもの

hyejin kang/gettyimages
「デジタル革命」によって、多くの先進国でデジタル化がどんどん進んでいる。しかしそれに応じた経済成長が見られずにいることが、いま重大な問題となっている。
フランスの社会経済学者ダニエル・コーエンは、「上位10パーセントが新しいテクノロジーの恩恵を独占し、残りの90パーセントを圧迫してきた」と述べた。産業革命以後の技術革新の際は、世界の農業人口は激減したものの、生産性が向上したので食糧は安くなった。しかも農村を離れた人たちが、労働力の不足していた都市部へと移動して労働者となったので、経済成長はさらに大きくなった。
ところがデジタル革命では、技術革新によって生産性が上がり職を失う人が増えても、それにかわる受け皿となる仕事が少ないので、賃金は低いままになっている。パターン化された仕事がAIに取って代わられつつあるように、「テクノロジーのほうが人間の労働力より市場価値がある」という事態が生まれつつあるのだ。
インターネットは生産者と消費者のマッチングを効率化させ、あたかも「見えざる手」のように、非常にすぐれた市場として機能している。逆に企業がこれまで果たしていた媒介としての役割は徐々に消えていき、社内の仕事は他社や個人にアウトソーシングされるようになった。「会社という場所がいらない世界」が生まれつつあるなかで、個人間の競争はより厳しいものになっている。インターネット技術は市場原理を加速させる一方で、格差を拡大させ、社会の「分断」を生み出す一因になっているのだ。
資本主義は自ら壊れる
資本主義の拡大を止めるのは難しい。「競争」には一人ひとりの規範意識と政治によるコントロールが必要だが、なかなか舵取りできていないのが現状だ。
20世紀経済学の巨人ヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは、「資本主義は、成功する。だが、その成功ゆえに、自ら壊れる」と主張した。人々は資本主義社会において、イノベーションを目指し、「創造のための破壊」を繰り返して、変化を求める。だが同時に安定を求めるのも人間の性だ。競争の果てに安定を求めるようになれば、大企業のような競争の勝者は地位を維持するため、ルールの変更を望むようになる。すると社会階級が硬直し、資本主義の停滞が生じてしまう。
資本主義と欲望
「欲望」を分析してきた経済学
「資本主義は『モノの生産をともなう組織的な活動全体』と定義できる。しかし『モノを生産する』(produce)という言葉の語源は、『前面に導く』ことだ。『モノを生産する』とは『前に導く、見せる』ということを意味する。つまり生産は、ある意味でショー(show)なのだ」と言い切ったのは哲学者マルクス・ガブリエルだ。機能だけでなくデザインやイメージなど、「なにか」から「新しさ」が感じられれば、それは立派な「新商品」として成り立つ。「共感」が商品になる時代では、なおさら「ショー」の中にいるような感覚になるだろう。
「近代経済学」は、自らの利益の最大化を行動原理とする「合理的経済人」というモデルによって、「欲望」という人間の性を科学的に分析しようとしてきた。科学のちからが重視された近代において、近代経済学は社会「科学」として自立することに憧れ、物理学や数学を模倣し成立した体系である。しかしあまりにも「科学」としての完全性にこだわることで、視野が狭まってしまったのではないか。
近代経済学が打ち立てた「近代的価値観」という前提が怪しくなりかけているいま、「合理的経済人」とはかけ離れた人間の性質を分析する「行動経済学」のような学問も、ますます重要になってくると思われる。
市場の魅力とは
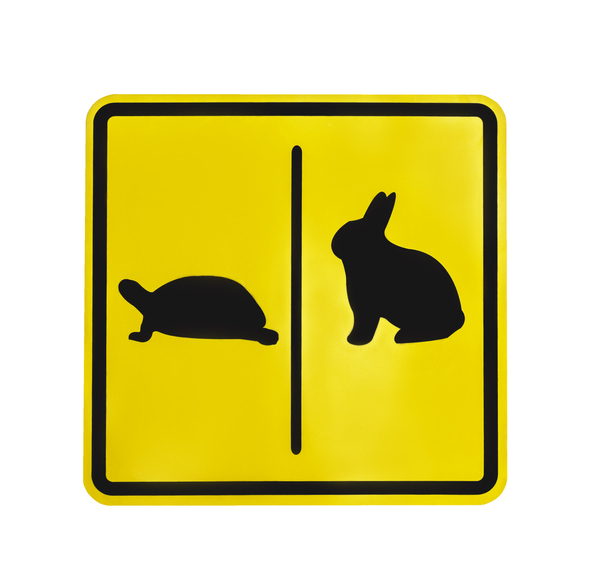
manus1550/gettyimages
「ウサギとカメ」というおとぎ話を思い出してほしい。結局あのカメは競争に「勝利」した。だがそもそもカメに「競争に参加している」という意識があったのだろうか。「勝者」「敗者」という考え方をもつこと自体が、物事の見方をゆがめてしまっている可能性もある。いまの私たちには、ただ単に歩むことを楽しむ、カメのようなセンスが必要なのかもしれない。
とはいえ市場そのものが悪というわけではない。市場は金銭の取引にしか縛られず、人間関係や感情などが強く支配する共同体とは正反対の場所だ。おカネさえあれば、誰もが排除されることなくプレーヤーになれるし、同じ金額を出せば誰もが同じものを買える。このドライさこそが市場の意義であり、すばらしさなのではないか。
いずれにせよ原点に返り、もう一度「市場」とはそもそも何だったのかを考えるときが来ているといえよう。

この続きを見るには...
残り0/3800文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.04.05
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約