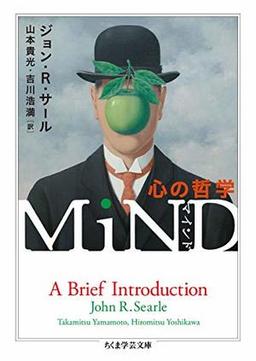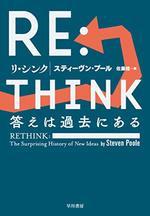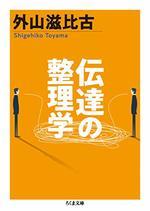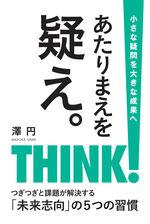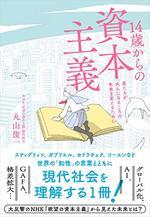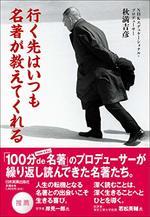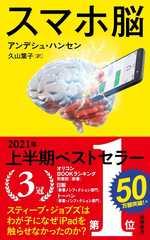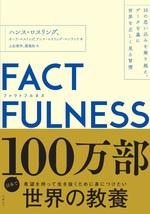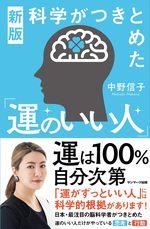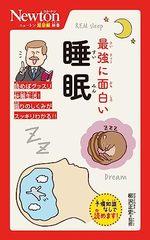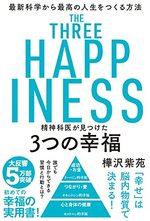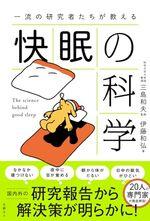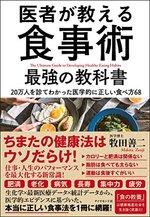心の哲学とは何か
これまでの心の哲学の理論は全部誤っている?
心の哲学は、現代哲学における最も重要なテーマのひとつである。それにもかかわらず、有名で影響力のある理論がすべて誤っているという点で、哲学のなかでも類を見ないテーマだ。
二元論と唯物論を中心として、行動主義、機能主義、計算主義、消去主義、随伴現象主義など、心の哲学にはさまざまな理論がある。だが著者サールによると、これらすべての理論が誤っているという。
サールは誤った理論へ向かおうとする欲求から真実を救い出すため、現代におけるさまざまな理論の問題と議論、歴史的背景を整理し解説したうえで、自身が正しいと考えるアプローチを提示する。
デカルトの実体二元論
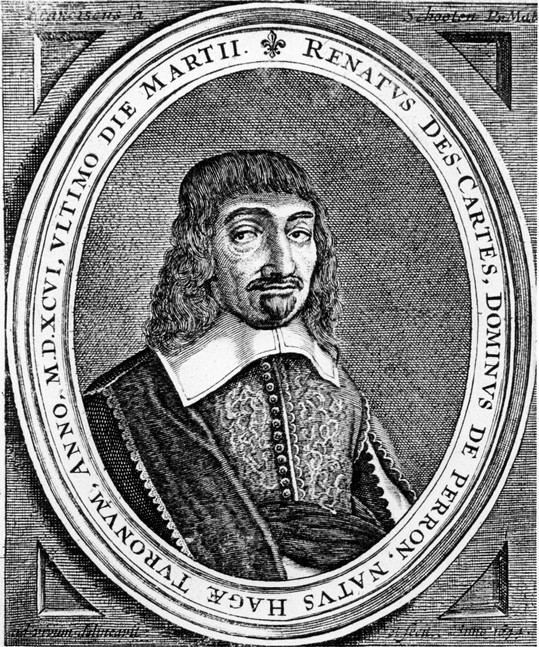
心の哲学は、17世紀の哲学者デカルトによって始まった。心についてのデカルトの考えは、有名な「われ思う、故にわれ在り」という文章に要約されている。
デカルトによると、世界は心的な実体と物理的な実体という二種類の存在者に分けられる。また心の本質は意識であり、心が意識的な状態にあることで私たちは存在している。一方で物理的実体としての身体は、物理法則に制約されている。
このように心と身体という二種類の実体が存在すると考えるのが、デカルトの「実体二元論」だ。だがデカルトのこの見解は、問題を解決するのではなく、むしろ多くの問題を残した。
デカルトが残した問題
デカルトが正しければ、心と身体は完全に別の領域として区別されるはずだ。だが実際は、腕を動かそうと意識すれば腕は動くし、身体に衝撃を受ければ意識に痛みが生じる。
このような心と身体の因果関係の問題は「心身問題」と呼ばれる。私たちは自分の心を直接知ることができるので、私の意識がある限り、私の存在は確実である。ところが意識を持っていることがわかるのは自分の心だけであり、他人の心を自分の心と同じように知ることはできない。
ではどうやって他人に心があると知ることができるのか。これを突き詰めて考えると、確実に心を持っているといえるのは世界で自分一人であるから、世界には自分一人しか存在しないとする「独我論」に行き着くこととなる。
人が確実に得られる知識は、心が直接知覚しているものだけだ。たとえば私が見ている山や川は、心の中に山や川の「観念」として知覚されたものである。心の外の世界に、心が知覚したありのままの姿で山や川が存在しているかどうかは定かではない。では知覚が外部世界を正しく表象しているということを、私たちはどのようにして確信できるようになるのか。あるいはそもそも外部世界は本当に存在しているのか。
こうした問題意識は、哲学の歴史において「人は本当の対象を知覚している」とする見解から、「人は対象の観念を知覚しているにすぎない」とする決定的かつ重要な移行をもたらした。だがサールはこれを「過去4世紀間の哲学史における最大の災い」だと述べている。
【必読ポイント!】 本当に心は存在しないのか?
唯物論の問題

現代の心の哲学において、最大の影響力をもっている学説は唯物論である。唯物論とは、二元論は誤りであり、心的現象は存在せず、物質的もしくは物理的なものだけが唯一存在するとする一元論だ。