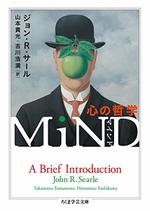サンデル教授、中国哲学に出会う

サンデル教授、中国哲学に出会う

著者
マイケル・サンデル
1953年生まれ。ハーバード大学教授。専門は政治哲学。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。2002年から2005年にかけて大統領生命倫理評議会委員。1980年代のリベラル=コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズムの代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、中でもハーバード大学の学部科目“Justice(正義)” は、延べ14,000人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義をテレビ番組として一般公開することを決定。日本ではNHK教育テレビ(現Eテレ)で「ハーバード白熱教室」(全12回)として放送された。著書『これからの「正義」の話をしよう』は日本をはじめとする世界各国で大ベストセラーとなった。ほかに『それをお金で買いますか』『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業』(以上早川書房刊)などの著作がある。2018年10月、スペインの皇太子が主宰するアストゥリアス皇太子賞の社会科学部門を受賞した。
ポール・ダンブロージョ
華東師範大学准教授。専門は中国哲学。同大学の修士・博士課程英語使用コースのプログラム・コーディネーター、異文化センター主任。儒教、道教、新道教、現代比較哲学についての論文を多数執筆、現代中国語で書かれた文献の英訳も手がける。
鬼澤 忍
翻訳家。1963年生まれ。成城大学経済学部経営学科卒。埼玉大学大学院文化科学研究科修士課程修了。主な訳書にサンデル『これからの「正義」の話をしよう』『それをお金で買いますか』、アセモグル&ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか』、ワイズマン『人類が消えた世界』『滅亡へのカウントダウン』(以上ハヤカワ・ノンフィクション文庫)など多数。
1953年生まれ。ハーバード大学教授。専門は政治哲学。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。2002年から2005年にかけて大統領生命倫理評議会委員。1980年代のリベラル=コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズムの代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、中でもハーバード大学の学部科目“Justice(正義)” は、延べ14,000人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義をテレビ番組として一般公開することを決定。日本ではNHK教育テレビ(現Eテレ)で「ハーバード白熱教室」(全12回)として放送された。著書『これからの「正義」の話をしよう』は日本をはじめとする世界各国で大ベストセラーとなった。ほかに『それをお金で買いますか』『ハーバード白熱教室講義録+東大特別授業』(以上早川書房刊)などの著作がある。2018年10月、スペインの皇太子が主宰するアストゥリアス皇太子賞の社会科学部門を受賞した。
ポール・ダンブロージョ
華東師範大学准教授。専門は中国哲学。同大学の修士・博士課程英語使用コースのプログラム・コーディネーター、異文化センター主任。儒教、道教、新道教、現代比較哲学についての論文を多数執筆、現代中国語で書かれた文献の英訳も手がける。
鬼澤 忍
翻訳家。1963年生まれ。成城大学経済学部経営学科卒。埼玉大学大学院文化科学研究科修士課程修了。主な訳書にサンデル『これからの「正義」の話をしよう』『それをお金で買いますか』、アセモグル&ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか』、ワイズマン『人類が消えた世界』『滅亡へのカウントダウン』(以上ハヤカワ・ノンフィクション文庫)など多数。
本書の要点
- 要点1サンデルの思想は共同体における善や道徳を重視する点で儒教思想と共通する点が多い。西洋ではサンデルの主張は道徳的要求が「厚い」と見なされるが、儒教から見ると不十分でさえあり、より多くの善を公共に対して求めるべきだという。
- 要点2中国哲学はジェンダーに相互依存や補完という概念を示す。西洋の伝統が当たり前とみなす構造に対して、中国哲学は新たな観点を提示する。
- 要点3中国はいま、経済発展とは異なる、市場では得られない幸福の源として、公共哲学を探し求めている。
要約
【必読ポイント!】 儒教とサンデルの共同体主義、共和主義
共同体における善の重視

wildpixel/iStock/gettyimages
マイケル・サンデルは、『リベラリズムと正義の限界』などの著作において、ジョン・ロールズが『正義論』で示したリベラリズムを批判したことで知られている。現実世界では対立する複数の価値があるが、ロールズは全ての人が合意できる「正義」の原理を導くために、私たちが実際に抱いている価値を忘れた状態の自我という観点から議論を構築した。
それに対してサンデルは、実際に私たちが共同体で生まれ育っていく過程で抱くようになった「善」の観点を重視する。このようなサンデルの立場は、共同体主義(コミュニタリアニズム)、もしくは共和主義として知られている。
儒教思想にとっての善き社会とは
社会や国家の問題を考える際、共同体における善や道徳を重視するという点で、サンデルの主張は儒教の考えと重複する部分が多い。その上で、李晨阳は、儒学の観点からすれば、サンデルのリベラリズム批判の多くを支持できるものの、健全な共同体主義の社会を築くにはサンデル版の共同体主義では物足りないと主張する。
ロールズにとって、正義は数ある美徳のうちの一つではなく、ほかのあらゆる価値がそれを基準にして測られるべき最も重要な価値であった。サンデルは、正義はある条件下で社会制度の第一の美徳になるにすぎず、絶対的なものではないとしている。たとえば、理想的な家族関係においては自然発生的な愛情によって統制されるため、正義が中心的役割を果たすことはない。
古典的な儒教思想家にとって善き社会とは、ロールズ的な意味の正義に近い「法」によって律されている社会ではなく、「礼」や「仁」が広く実践されることで「法」に依存しない社会、正義が最も重要でなくてもかまわない社会である。「礼」や「仁」という美徳の実践によって、人びとは共同体の強い連帯意識と、最も価値の高い美徳としての調和を育むことができるようになる。サンデルの共同体の概念には、この調和という概念が含まれていない点に大きな欠落がある。
個人の権利を根拠とするリベラル派にとって、アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)をどのように正当化するのかということは大きな問題となる。サンデルは、自分自身を個別の主体ではなく、共同体における共通のアイデンティティへの参画者としてみなすことで正当化できるとした。
だが、儒者の観点からすると、サンデルの解決策は不十分である。儒者にとって、社会的調和は善き生に欠かせないどころか、善き生そのものである。調和とは、単に対立のない状態のことではなく、それぞれが潜在能力を発揮し、ほかの要素と一緒になって各要素の最善の部分を引き出す統一体を形成することである。人種的多数派が少数派と調和的な関係を築き共同体の構築に積極的に関わっていれば、人種的平等の必要性を感じ、共通の強い目的意識を社会と分かち合う可能性が高くなるだろう。調和が進む社会は、一時的に人種的多数派に犠牲を強いることがあっても、長い目でみれば恩恵をもたらす。
儒教の徳理論と共和主義

mj0007/iStock /gettyimages
『民主政の不満』という著作において、サンデルはアメリカの政治史を、道徳的・宗教的意見に対する政府の中立性を重視するリベラリズムの観点ではなく、共通善に関して市民間で話し合い自己統治を行うとする共和主義の観点を支持している。

この続きを見るには...
残り2667/4051文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.04.25
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約