宇宙はなぜブラックホールを造ったのか

宇宙はなぜブラックホールを造ったのか
著者
著者
谷口 義明 (たにぐち よしあき)
1954年北海道生まれ。東北大学理学部卒業。同大学院理学研究科天文学専攻博士課程修了。理学博士。東京大学東京天文台助手などを経て、現在、放送大学教授。専門は銀河天文学、観測的宇宙論。すばる望遠鏡を用いた深宇宙探査で、128億光年彼方にある銀河の発見で当時の世界記録を樹立。ハッブル宇宙望遠鏡の基幹プログラム「宇宙進化サーベイ」では宇宙の暗黒物質(ダークマター)の3次元地図を作成し、ダークマターによる銀河形成論を初めて観測的に立証した。主な著書に『宇宙進化の謎』『新・天文学事典』(以上、講談社)、『天の川が消える日』(日本評論社)など多数。
1954年北海道生まれ。東北大学理学部卒業。同大学院理学研究科天文学専攻博士課程修了。理学博士。東京大学東京天文台助手などを経て、現在、放送大学教授。専門は銀河天文学、観測的宇宙論。すばる望遠鏡を用いた深宇宙探査で、128億光年彼方にある銀河の発見で当時の世界記録を樹立。ハッブル宇宙望遠鏡の基幹プログラム「宇宙進化サーベイ」では宇宙の暗黒物質(ダークマター)の3次元地図を作成し、ダークマターによる銀河形成論を初めて観測的に立証した。主な著書に『宇宙進化の謎』『新・天文学事典』(以上、講談社)、『天の川が消える日』(日本評論社)など多数。
本書の要点
- 要点1アインシュタインによる特殊相対性理論や一般相対性理論の確立を契機に、ドイツの物理学者シュバルツシルトによって、ブラックホール解が導かれた。
- 要点2「ブラックホールは観測できない」と考えられていたが、強い電波源の調査や恒星と連星系をなす天体の調査から、いまは次々と新たなブラックホールが発見されている。
- 要点3銀河の中心にはブラックホールがあり、ブラックホールと銀河が共に進化するという「共進化(co-evolution)」という概念も生まれた。
- 要点4ブラックホールも物質としての性質を持っており、寿命がある。
要約
ブラックホールという概念が誕生するまで
光が脱出できない黒い星
ブラックホールという概念は、研究室のなかから生まれた。18世紀後半は、「光は波ではなく粒子である」という考え方が主流であった。ならば光は重力に引き寄せられるため、光が出てこられないほどの重力を持つ“黒い星”があるのではないか。これが、英国の物理学者ジョン・ミッチェルが1783年に発表した論文に登場した“dark star(暗い星)”であり、ブラックホールという概念の萌芽であった。
たしかに星の重力に打ち勝つために必要とされる「脱出速度」が光の速さを上回ることは、理論上あり得る。たとえば太陽と同じ密度の星が太陽の500倍の大きさだったとすると、光の速度ではこの星の重力に打ち勝つことはできない。観察する側に光が届かないため、その星は暗く、当然観測することもできなくなる。
時空は質量分布に応じて歪む
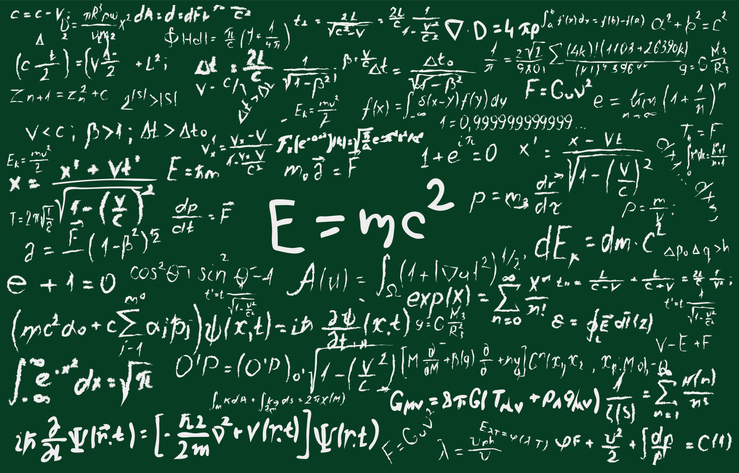
i000pixels/gettyimages
ミッチェルが指摘した“黒い星”には理論上の限界があった。光は質量がないため、重力の観点で脱出速度を論じることは無理があるのだ。古典的なニュートン力学の限界といえるだろう。
ブラックホールという概念の誕生は、ドイツ生まれの物理学者アルベルト・アインシュタインと無関係ではない。E=mc2という式に代表される特殊相対性理論で、アインシュタインは3次元の空間座標に対して時間が相互に関係していることを見出し、「時空」という概念を生み出した。また特殊相対性理論に重力を取り込んだ一般相対性理論では、重力の効果が時空の曲がりとしてあらわれるとした。これに従えば、重力波は時空への歪みを伴いながら、光速度cで伝播することになる。こうして「重量を持つ物体がある = その場所の時空は質量分布に応じて歪む」という一般相対性理論が確立した。
そして導いたブラックホール解
星などの天体が自分自身の重さに耐えきれず重力によって縮んでいく、重量崩壊と呼ばれる現象がある。このとき一般相対性理論では、星を形作る物質が星の中心に落ち込むとは考えない。時空が落ち込むと考えるのだ。
それでは時空が縮んでいく速度が、光の速度を超えたらどうなるのか。当然ながらその光が観測者のもとに届くことはない。これこそがいまに続くブラックホールの概念で、ドイツの物理学者カール・シュバルツシルトが導いたブラックホール解だ。彼の名前をとって、光が脱出できなくなる速度が実現する半径は「シュバルツシルト半径」と呼ばれる。
一般相対性理論のもとでは、3次元の空間と1次元の時間を足し合わせ、4次元の世界で物事を考えなければならない。重力が強くなると時空の歪みが大きくなり、時間の進みが遅くなる。つまりブラックホールに近づくにつれ、時間の進みは弱くなり、「シュバルツシルト半径」に達するとついに時間が止まる。光でさえも止まってしまうので、光はそこから出てくることもできなくなるというわけだ。
【必読ポイント!】ブラックホールの発見
超大質量ブラックホールの発見

scyther5/gettyimages
ブラックホールという概念が成り立つことは、ブラックホール解として示された。しかしそれでもなお、長らくブラックホールは存在しないと思われていた。重力崩壊が原因で密度無限大の特異点を持つとするブラックホールは、安定的に存在できないと思われたからだ。だが天文学の領域において、見えないはずのブラックホールにつながる発見が相次いだ。

この続きを見るには...
残り2583/3972文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.05.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











