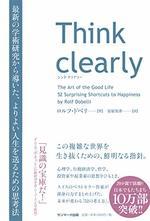本当の自分とは?
パーソナル・プロジェクトから導かれる行動

あなたはレストランにいて、隣のテーブルには男性2人組が座っている。2人組のうち1人が、運ばれたステーキに対して「焼き方がよくない」と言い、ウェイターに突き返す。このやりとりが3回行われた場合、彼に対してどのような印象をいだくだろうか。
人の行動は、遺伝的動機、社会的動機、個人的動機から導かれる。
遺伝的動機は、生まれ持った気質から生じる。生まれ持った、ある程度固定的なパーソナリティ特性を理解しようとするには、「誠実性」「協調性」「情緒安定性」「開放性」「外向性」の五つの因子を用いる「主要五因子(ビッグファイブ)モデル」というものがある。現代のパーソナリティの科学における研究分野の中でもっとも影響力があるモデルだ。五つのタイプには、たとえばオキシトシンという神経ペプチドの高い人は協調性が高いなど、それぞれ生物学的な要因が影響しており、遺伝的要素の高いものもあるという。
社会的動機は社会・文化的な規範からもたらされ、個人的動機はその人固有の目的から生じる。そうしたことから、遺伝的動機や社会的動機と異なり、個人的動機は傍目には解釈しにくい一面がある。
個人的な計画や目標は、パーソナル・プロジェクトと呼ばれる。犬の散歩をするといった些細な計画から、人生最大の夢まで、さまざまなことがパーソナル・プロジェクトになりうる。そして、それに取り組むことによって、普段とは違った行動をとることがある。つまり、ステーキを突き返した男性は、「肉の焼き加減にこだわる」以上に、同席する上司を感心させるというパーソナル・プロジェクトがあったため、普段のパーソナリティ特性から離れた行動をとった、とも考えられるのだ。こうした行動を導くのが、「自由特性」と著者が呼ぶ、パーソナリティ特性の中の変化できる一面である。
違う自分を演じるストレス

「自由特性」に導かれて本来の性格と異なる自分を演じることは、自分を偽ることではない。遺伝的、社会的、個人的な動機に従って行動することは、「自然」なことである。しかしながら、長期間にわたって本来の自分と異なるキャラクターを装うことは、心身に負担をかける。
著者の心理学のクラスを受講していたピーターという学生の例を紹介しよう。彼のパーソナリティ検査の結果には、外向的な特性が強く出ていた。しかしながら、彼は人里離れた修道院で修道士として、沈黙を重んじる暮らしをしていた。彼にとって、修道院という環境は、次第にストレスとなっていたようだ。実際、ピーターは修道士としての人生に疲れ、大学に進学し、学者としての道を歩んだ。教育学の教授となった彼は、本来の特性を活かして、大きな成功を収めている。このように、遺伝的な気質と社会的な環境が一致していれば、よりよい結果につながるのだ。
また、「白クマについて考えないようにすると、ますます白クマについて考えてしまう」という、ダン・ウェグナーによる有名な研究がある。思考を抑制することで白クマのことが頭から離れなくなるという、「皮肉なプロセス」が生じるというものだ。このことは、「自由特性」にも当てはまるだろう。つまり、本来の自分を無理に抑制することで、かえって本来の自分が漏れ出てしまう場合さえあるのだ。
本来の自分に戻れる「回復のための場所」
異なる自分を演じるストレスから逃れるには、どのようにすればいいのだろうか。また、仕事で普段と違う行動を強いられる場合、パフォーマンスを維持するには何が必要なのだろうか。こうした問題を解決するのは、ありのままに過ごせる休憩所のような「回復のための場所」を見つけることである。