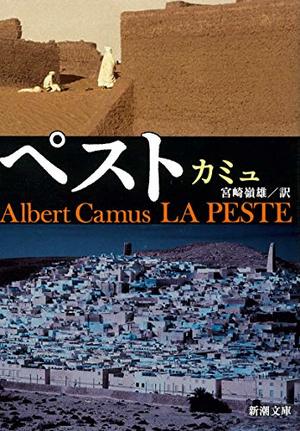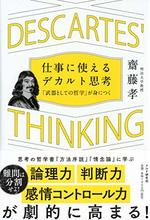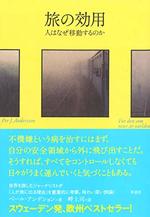ペスト
著者
カミュ
Albert Camus
(1913-1960)
アルジェリア生れ。フランス人入植者の父が幼時に戦死、不自由な子供時代を送る。高等中学(リセ)の師の影響で文学に目覚める。アルジェ大学卒業後、新聞記者となり、第2次大戦時は反戦記事を書き活躍。またアマチュア劇団の活動に情熱を注ぐ。1942年『異邦人』が絶賛され、『ペスト』『カリギュラ』等で地位を固めるが、‘51年『反抗的人間』を巡りサルトルと論争し、次第に孤立。以後、持病の肺病と闘いつつ、『転落』等を発表。‘57年ノーベル文学賞受賞。‘60年1月パリ近郊において交通事故で死亡。
Albert Camus
(1913-1960)
アルジェリア生れ。フランス人入植者の父が幼時に戦死、不自由な子供時代を送る。高等中学(リセ)の師の影響で文学に目覚める。アルジェ大学卒業後、新聞記者となり、第2次大戦時は反戦記事を書き活躍。またアマチュア劇団の活動に情熱を注ぐ。1942年『異邦人』が絶賛され、『ペスト』『カリギュラ』等で地位を固めるが、‘51年『反抗的人間』を巡りサルトルと論争し、次第に孤立。以後、持病の肺病と闘いつつ、『転落』等を発表。‘57年ノーベル文学賞受賞。‘60年1月パリ近郊において交通事故で死亡。
本書の要点
- 要点14月のある日から、街に大量のネズミが発生し次々と死んでいくのが発見される。やがて、ペストが流行り始め、市の門は閉ざされる。
- 要点2そこから、翌年の2月まで封鎖が続く。街の人々は、当初は楽観的に構えるが、次第に疫病にさいなまれていく。やがて絶望にも慣れ、不幸と苦痛の痛みさえ感じなくなる。
- 要点3その中で、医師リウーをはじめとする保健隊の人々は、献身的に活動を続け街を支える。それは際限なく続く敗北とも言える活動であるが、やがて疫病の勢いが衰えていき解放の日が近づいてくる。
要約
市の門が閉ざされるまで
次々とネズミが死んでいく
物語は、4月16日に医師リウーが、診察室のある建物でネズミの死骸を見つけるところから始まる。やがて市街全域で同様の死骸が見つかり、28日にはその数は8000体にもなったことが報じられる。不安にかられた人々は、当局の対応に非難のほこさきを向けた。ところが、この現象は突然終息する。
そうしたある日、リウーは高熱を出して倒れた門番を診察し、リンパ腺の異常を所見する。翌日、門番は死亡してしまった。はじめ、それは流行り病ではないと考えられていた。しかしリウーと同業の老医師は、かつてパリで治療に当たった経験を踏まえ、その症状は20年以上前に温和な気候の地域からは姿を消していたはずのペストだと指摘する。そうかもしれないと思いながらリウーは、無用な不安を断ち切り、目の前で苦しむ患者への処置に注力しようとする。
あたかもペストであるかのごとく

DamianKuzdak/gettyimages
リウーは県の医師会長に依頼し、保健委員会を招集してもらった。ペストかどうかはさておき、この病を放置すれば市民の半分は死んでしまうとして、その場で警戒措置を講じることを進言する。医師会長は、法律によって規定された重大な対策を取るには、ペストであることを医師が公に認めることが必要になるとして、慎重論を主張した。また、検査結果が明白になるまでは決定は保留すべきだとも強調した。
ペスト同等の措置をすべきかと問う県知事に対し、医師会長はあくまでペストとは認めずに、ペストのようにふるまう病への対処として責任をもとう、との玉虫色の結論を出す。
若干の予防措置を
市民の間で、熱病のことが話題に上るようになった。当局は、会議の2日後に市内の目立たないところに小さなビラを貼りだした。その内容は、世論を不安にさせまいとする配慮から次のような微温的なものであった。「悪性の熱病の若干例が発生した。これらの症例は、実際に不安を感じさせるほどには顕著な特徴を示していないし、市民が冷静を保ちうるであろうことは疑いをいれない」。それにもかかわらず、市民に対して極度の清潔さを奨励するなど、いくつかの予防的措置が講じられた。
そして、熱病のさらなるまん延が観察されたある日、植民地総督府より街の閉鎖を求める公電が、突然知事のもとに送られてきた。市の門は閉じられ、人々の出入りは一切禁じられた。食糧と生活必需品のみが、陸路と空路で届けられることになった。
ペストに囚われて生きる
要するに一時的なもの

filadendron/gettyimages
ここに至って、ペストはすべての市民の事件となった。
突然の閉鎖で通常の交通手段は止められ、媒介になることを防ぐために外部との手紙のやりとりも禁止された。商業も死んだ。いつ終わるともしれない追放、極度の孤独の状態に、市民は戸惑い苦しんだ。しかし正確な知識がないこともあって、これは確かに憂慮すべき出来事には違いないが、一時的なものだという印象を持ち続けた。
人々は相変わらずカフェのテラスで愚痴より冗談を多く言い合い、努めて冷静さをよそおおうとしていた。病気に罹っていないことの証明書を医師に発行してもらおうとする人も現れた。
閉鎖後第3週には死者は300名を超えていた。死によって家族と切り離された人々にとって、その悲痛は現実的なものにほかならなかった。突然の閉鎖によって、外部の大切な人との接触が断たれてしまった人々にとっても、同様であった。食糧の補給は制限され、ガソリンは割当制になり、電気の節約も決められた。
このような状況にあっても、なすことのなくなった人々は、失業をしているというより、まだ休暇をとっている気分だったのである。どこかに心痛を抱えながらも、そうした大勢の人々が街頭や映画館に群がっていた。
暑さの訪れとともに
ある人々は、自分たちは何か知らない罪を犯した罰として、想像を絶する監禁状態に服せられているのだという観念を次第に持つようになった。
ペストは神の審判のしるしとして、「皆さん、あなたがたは禍いのなかにいます。皆さん、それは当然の報いなのです」という説教によって、カトリック神父は回心を迫る。そうした意識は広まり、人々はいっそう消沈した。
6月の終わりになって夏が始まった。暑さの訪れとともに、死者の数が週に700名近くと鰻のぼりに上昇した。街には沈痛な空気がますますみなぎるようになった。ペストから身を守るつもりか、あるいは日光からか、すべてのよろい戸は閉ざされた。建物の中からは、時折うめき声がもれてきた。
保健隊が結成される
ラジオは、もう週に何百人と死亡数を数えるのをやめ、日に92名、107名、120名というように報じるようになった。100は900に比べて大きな数ではないというわけである。人々が不測の感染を予防するものとして買い求めたため、ハッカのドロップが薬屋から姿を消した。
そのような折、志願の市民による「保健隊」が結成され、医師リウーは協力の申し出を受ける。この保健隊の結成は、疫病が現に目の前にある以上は、それと戦うためになすべきことはなさねばならないという覚醒と勇気を、一部の人々の間にもたらした。
【必読ポイント!】 ペストが街をひれふせさせる
感染地域が広がった

chrispecoraro/gettyimages
8月半ばに、ペストは頂点を迎えた。人々は自分自身の苦痛を集団的な不幸と同一視するようになり、集団的なさまざまな感情に流されるばかりであった。それは、恐怖と反抗、別離と追放からなっていた。
ペストは人口密度の極めて高い街の外苑から、中心のオフィス街にまで進出し、特に被害のひどい地区が区域ごと隔離された。そこの住民は、弱い者いじめをされているような気持ちを抑えることができなかった。他の地区の居住者は、自分たちよりもさらに自由を奪われている人々がいるのだということに、一つの慰めを見出していた。
ついにすべての声を沈黙させた
火事も頻発した。家族を亡くした哀しみと不幸に半狂乱になった人々が、ペストを焼き殺すような幻想に駆られて、自宅に火を放つのだった。街とその外部をつなぐ門も、夜に何度となく襲撃された。
そして、火災を被った家屋や、閉鎖された家屋に対する略奪が起こり、それに追随する者も現れた。そこで当局はやむなくペスト令を戒厳令と同等に扱うに至る。これにより2人の窃盗犯が射殺されたが、ペストで多くの死亡者が出る厄災の中では何のインパクトも与えなかった。
さらに消燈時刻が11時に制定され、この時刻を境に街は完全な闇に没してしまった。ペストと暗夜が、ついにすべての声を沈黙させてしまったのである。
記憶もなく希望もなく
市民は、致し方なく事の成行きに適応していったようだった。彼らは、まだ不幸と苦痛の態度をとっていたが、実はその痛みはもう感じられなくなっていた。絶望に慣れてしまったのである。街角で見られる彼らの姿は、平静でかつ放心したようであり、実にうんざりした目つきをしていた。
過去の記憶を思い出すことも、未来への希望もない。ペストはすべての人たちから、恋愛と、さらに友情の能力さえも奪ってしまった。というのも、恋人や友人への愛情は未来への気持ちをいくらか必要とするものであるし、かれら自身がもはや、いまここの瞬間を生きざるを得なかったからである。
人々はただ、食糧品店へと続く長蛇の列に辛抱強く並んでいた。あらゆる物の値段が上がり、生活必需品が欠乏していた。
あらんかぎりの力で死と戦う
医師リウーと保健隊の人々はどうしていただろうか。かれらは、こなしきれない疲労を実感していた。治療法がない以上、かれらの仕事は治療することではなく、診察することだった。ペストの判定をして、病人を家族から強制的に引き離して病院に移し、残された家族も他への感染を防ぐため、ホテルなどを改造した市内の隔離施設に移動させる。これは救済ではなく、したがって医療従事者の本望ではなかった。病人はだいたい2日以内に死亡していった。
それでも彼らは、力の限りこの仕事に従事していた。どうしてそこまで献身的に働くのかと問われたリウーは、ペストとの戦いは「際限なく続く敗北」であると認める。しかしだからといって、死との戦いを決して諦めることはなかった。
人々は待つのをやめる
11月、残暑が終わり、冷気が訪れた。この頃になると疫病は「頂上平坦線」と呼ばれる状態に到達したと思われた。死亡者数の増加が見られなくなったのである。これは、10月末に最初の血清が試された成果だと考えられた。
医師の中には、今後はペストは衰退するばかりだという見方をする者も現れた。しかし、そうした楽観的な医師でも、その衰退がいつ始まるかは予見できなかったし、彼もまたペストで命を落とした。
ペストは寒冷の気候の中でも結局おさまる気配を見せなかった。人間は、あんまり待っていると、もう待たなくなるものである。人々は未来のない生活を続けていた。
解放に向かう日々
ほほえみが戻ってきた

AleksandarGeorgiev/gettyimages
ペストの最初の退潮の兆しは、12月の末になって現れた。亡くなるばかりと思われたリウーの患者の1人が、奇跡的に回復したのである。やがて、その週のうちに同じような症例がいくつか出てきた。やがて、当局の統計は明らかに疫病の衰退を示唆するようになった。
しかし人々は、あわてて喜ぼうとはしなかった。積み重なった月日は、かれらの解放の願いを増大させる一方、用心深さも教えていた。疫病が近いうちに終息することなど、ますます当てにしないように習慣づいていたのである。
それでも1月の3週間にわたり、ペストの患者数は連続的に下降を続けた。当局も最初は遠慮がちであったが、やがて勝利が確認されたことを伝えるようになった。
街角では、人々の顔つきがゆるみ、時にはほほえんでいることが観察できた。その時人々は、これまで誰もほほえんでいる者はいなかったということに改めて気づいたのである。
市の門は開かれた
1月25日、ついに当局はペストの終息を宣言した。ただし、市の門はなお2週間閉鎖されたままとし、各種の予防措置は1カ月続行される旨も付け加えられた。
この日の夜から、11時の消燈も解除され、灯のともされた街頭に、人々は賑やかに笑いさざめき、群れをなして繰り出した。
もちろん、その時も息を引き取ろうとした患者はいたし、隔離施設で解放されるまではまだ待たなければいけない境遇の者もいた。その傍らで、リウーとともにペストと闘った友は、ペストによってその命を落としていた。しかし、街に溢れる集団的な喜びは空気の色を一変させていた。
そして、2月のある晴れた朝の明けがた、ついに市の門は開かれたのである。
ペストと戦う唯一の方法
人々は街に立ち込める集団的な感情を共有していたが、行動は必ずしも一様ではない。投獄を覚悟で街からの脱出を試みる者もいれば、享楽に走る者もいる。疫病にひざを屈して、諦めを説く者もいる。その中で、オランの街を支えた医師リウーとはどのような人物なのか。
彼は、キリスト教の説く神を信じていない。子どもたちが病などによって責めさいなまれるように作られたこの世界を、愛してさえいない。保健隊として人のために自らを犠牲にすることを「ヒロイズム」と呼び、疑う人にはこう答えている。これはヒロイズムの問題ではない、ペストと戦う唯一の方法は誠実さなのだ、それはつまり、自分の職務を果たすことなのだ、と。
そして最後に彼は、ペストの恐怖を忘れたかのように歓喜する人々を見ながら、ペストという災厄に教えられたことをつづる。人間のなかには軽蔑すべきものよりも賛美すべきもののほうが多くある、ということを。

この続きを見るには...
残り0/4699文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.04.24
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約