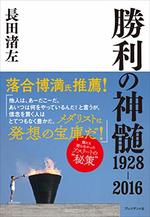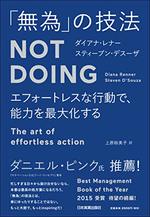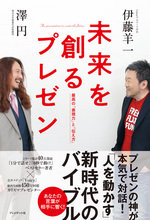QRコードの奇跡
モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ
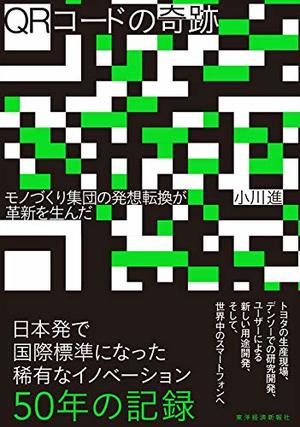
著者
小川進 (おがわ すすむ)
神戸大学大学院経営学研究科教授、MITリサーチ・アフィリエイト。1964年兵庫県生まれ。87年神戸大学経営学部卒業、98年マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院にてPh.D.取得。2003年より現職。研究領域は、イノベーション、経営戦略、マーケティング。主な著作に『イノベーションの発生論理』『はじめてのマーケティング』(ともに千倉書房)、『競争的共創論』(白桃書房)、『ユーザーイノベーション』(東洋経済新報社)がある。英語論文では、フランク・ピラーとの共著“Reducing the Risks of New Product Development”やエリック・フォン・ヒッペルらとの共著“The Age of the Consumer-Innovator”(ともにMIT Sloan Management Review掲載)などがあり、ユーザーイノベーション研究では世界的な評価を得ている。組織学会高宮賞(2001年)、吉田秀雄賞(2011年、準賞)、高橋亀吉記念賞(2012年、優秀作)などを受賞。
神戸大学大学院経営学研究科教授、MITリサーチ・アフィリエイト。1964年兵庫県生まれ。87年神戸大学経営学部卒業、98年マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院にてPh.D.取得。2003年より現職。研究領域は、イノベーション、経営戦略、マーケティング。主な著作に『イノベーションの発生論理』『はじめてのマーケティング』(ともに千倉書房)、『競争的共創論』(白桃書房)、『ユーザーイノベーション』(東洋経済新報社)がある。英語論文では、フランク・ピラーとの共著“Reducing the Risks of New Product Development”やエリック・フォン・ヒッペルらとの共著“The Age of the Consumer-Innovator”(ともにMIT Sloan Management Review掲載)などがあり、ユーザーイノベーション研究では世界的な評価を得ている。組織学会高宮賞(2001年)、吉田秀雄賞(2011年、準賞)、高橋亀吉記念賞(2012年、優秀作)などを受賞。
本書の要点
- 要点1QRコードは、トヨタの発注先であるデンソーが開発した。トヨタの生産方式である「かんばん」を電子化しようとしたことが、そのはじまりであった。
- 要点2より大容量の情報を短時間で簡単に、ミスなく処理できるものとして、当時アメリカで開発が進んでいた二次元シンボルを独自アレンジして生まれた。
- 要点3パブリックドメイン化し、入念な準備によって国内外で規格が標準化されたことで、一般生活でも広く利用されるものとなった。
要約
QRコードの発端
すべては「かんばん」から始まった
すべての始まりは、デンソーがトヨタに部品を納入していた関係で、トヨタの生産方式である「かんばん」を導入したことにある。「かんばん」とは、何をどこから仕入れ、どこに置いておくかをわかるようにした標識のようなもので、「必要な時に必要なものを必要な量だけ」生産することを目的としている。
だがデンソーでは、多頻度納品による検品や伝票の起票作業などで、時間と人手がかかってしまうという課題が生じていた。そこで「かんばん」をコンピュータで読めるようにすれば、製品のチェックと伝票の自動作成を行えるようになると考えたのだ。
独自のコードとリーダーの開発

Eetum/gettyimages
しかし、ことはそう単純にはいかなかった。自動車部品工場の現場は油汚れが多く、ひどい状態の「かんばん」でも読み取れるようにしなくてはならなかったからだ。しかも「かんばん」に含まれる製品の情報を収納するために、少なくとも60桁以上のデータを格納できる必要があった。それを満たす既製品のバーコードとそのリーダーは、まだ市場になかった。
そこでデンソーは取引のあった神崎製紙の自動写植機をもとに、印刷にも強い「NDコード」を開発するとともに、当時普及していたものより読み取り性能が高く、安価なバーコードリーダーを発明した。
コンビニでの採用
それだけでは終わらない。このバーコード技術の保守・修理・管理を担当する会社として設立されたSKKは、小売企業への導入に乗り出した。
最初に手を挙げたのはセブンイレブンだ。POSレジを導入したばかりだったセブンイレブンは、販売情報を迅速に管理するだけでなく、頻繁に入れ替わる大量の商品の納品と検品を手早く正確に行うために、このバーコード技術を自分たちで応用した。すると売り逃がしロスが減り、売上も飛躍的に向上。結果、他のコンビニエンスストアでも導入されるようになった。
こうして得られた売上を原資としながら、デンソーはQRコード開発へと踏み出していく。
【必読ポイント!】 QRコードの誕生
「かんばん」の限界
QRコードの父と言われているのが、当時デンソーで技術者をしていた原昌宏であった。
1980年代に入り、モノ不足の時代からモノ余りの時代に突入したことで、自動車にも多様性が求められるようになった。部品工場でも多種多様なものを管理する必要に迫られ、NDコードの「かんばん」に限界が見られはじめた。NDコードのような一次元シンボルでは、取り扱える情報量が少ないためである。
そこで、アメリカで盛んに開発されていた二次元コードを独自にアレンジし、新しいコードの開発に着手することになった。より大容量の情報を短時間で簡単に、ミスなく処理できるようにする挑戦の始まりである。
マトリックス型の採用
新しい二次元コードには、少なくとも200桁以上の情報を「かんばん」に表示し、ワンタッチで油などの汚れにも強く、伝票処理に必要な情報を盛り込めるといった条件が求められた。

この続きを見るには...
残り3108/4338文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約