どこからが病気なの?

どこからが病気なの?
著者
著者
市原真(いちはら しん)
1978年生まれ。2003年北海道大学医学部卒。国立がんセンター中央病院研修後、札幌厚生病院病理診断科へ。現在同科主任部長。医学博士。インターネットでは「病理医ヤンデル」として有名。著書に『症状を知り、病気を探る 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る』(照林社)、『病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと 常識をくつがえす“病院・医者・医療”のリアルな話』(大和書房)、『いち病理医の「リアル」』『Dr.ヤンデルの病院選び ヤムリエの作法』(共に丸善出版)など。
1978年生まれ。2003年北海道大学医学部卒。国立がんセンター中央病院研修後、札幌厚生病院病理診断科へ。現在同科主任部長。医学博士。インターネットでは「病理医ヤンデル」として有名。著書に『症状を知り、病気を探る 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る』(照林社)、『病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと 常識をくつがえす“病院・医者・医療”のリアルな話』(大和書房)、『いち病理医の「リアル」』『Dr.ヤンデルの病院選び ヤムリエの作法』(共に丸善出版)など。
本書の要点
- 要点1病気のなかには、すぐには病名を確定できないものもある。「様子をみる」というのは、時間軸を活用した医者の戦略だ。一度医者が出した薬が効かなかったからといって、別の医者に行くのは正しい選択ではない。
- 要点2病気と人体の関係は、人体を都市にたとえるとわかりやすい。かぜの諸症状は、忍び込んだウイルスと防御部隊のバトルだ。血管はライフラインであり、これに負荷をかけるのが高血圧である。
- 要点3複雑系である人体において、体調を崩す最大の原因は、ひとつの何かに偏りすぎてしまうことだ。
要約
【必読ポイント!】 病気ってどうやって決めるの?
病気だと決めるのは誰?
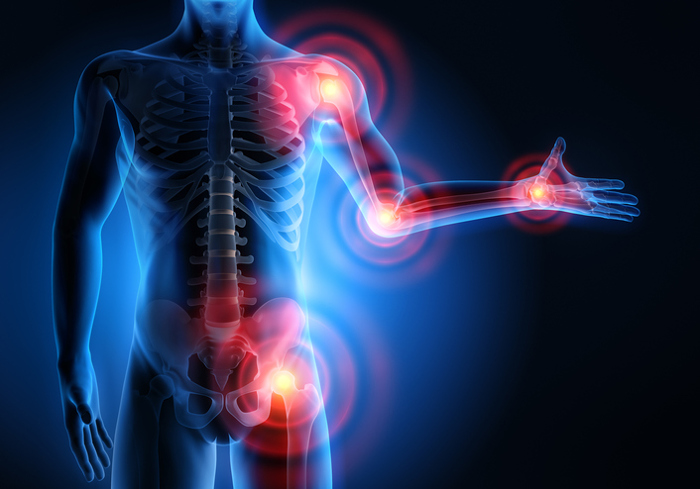
http://peterschreiber.media//gettyimages
あなたや私を病気だと決めるのは、本人、医師、そして社会だ。
私たちは、具合が悪いと感じると、これまでの経験に照らし合わせて、しばらく様子をみれば治まりそうかどうかを判断する。子どもが成長するにつれ、腹痛で泣かなくなるのは、「これくらいの痛みだったら、もう少ししたら波が引いて、治るはず」「痛み止めを飲んで寝ていたら、明日には治っているはず……」などと未来予測し、判断できるようになるからだ。そしてたいていの場合、その痛みは治る。
自分の未来を自分自身で予測し、それが当たり続けている限り、医者に会いに行く必要はない。だから「病気を決めているのは自分自身」ということになる。
病院の門をくぐることになるのは、これまでに経験したことのない痛みがあるときや、症状がどんどん悪化するのを自覚したときだ。経験したことがなければ、すでに経験が蓄積されているプロに、自分の体の未来予想図を描いてもらわなければならない。病院は、患者が自分で未来を予測できないときに行く場所であり、医者は、患者に代わって患者の未来を精度高く予測する人だ。
患者と医者以外の全てである「社会」もまた、病気かどうかを決めるファクターだ。「患者」が病気であるかどうかは、必ずしも「患者」だけの問題ではない。「患者」は病気だと感じていなくても、社会的な生活が困難になると予想された場合に、周囲にいる人々が「患者」を「患者」として対処するケースがある。
病院に行くべきかを決めるには?
具合が悪くなったときにまず大切なことは、「すぐに病院に行くべきか、あるいは家でじっくり様子をみてもいいのか」を判断することだ。この判断において、自分の経験だけをよりどころにするには限界がある。そこで著者は、総務省消防庁のアプリ「Q助」を活用することを勧めている。
Q助を開くと、ざっくりしたものから徐々に小さなものへと、次々に質問が表示される。この質問に答えることで、救急車を呼ぶべきだ、少し待って翌日に病院にかかれ、などといった指示を受け取れる仕組みだ。
Q助は、病名を絞り込むためのアプリではない。しかし、今どう行動すればいいかは確実に指示してくれる。まるで名医の問診を受けているように、最初の行動までにかかる時間をぐっと短縮できるのだ。
医者はどのように病名を確定させている?

byryo/gettyimages
名医と呼ばれる人たちは、患者を診察するにあたり、そもそも思考をしていないことがある。

この続きを見るには...
残り2879/3909文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.17
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約












