勝利の神髄1928-2016
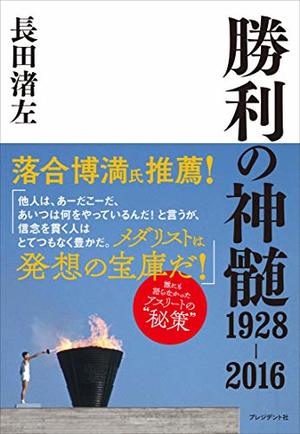
勝利の神髄1928-2016
著者
著者
長田渚左(おさだ なぎさ)
東京生まれ。桐朋学園大学演劇専攻科卒業後、スポーツライター&キャスターとして活躍。日本スポーツ学会代表理事。NPO法人スポーツネットワークジャパン理事長。無料スポーツ総合誌『スポーツゴジラ』編集長。主な著書に『復活の力』(新潮新書)、『桜色の魂 チャスラフスカはなぜ日本人を50年も愛したのか』(集英社)など。
東京生まれ。桐朋学園大学演劇専攻科卒業後、スポーツライター&キャスターとして活躍。日本スポーツ学会代表理事。NPO法人スポーツネットワークジャパン理事長。無料スポーツ総合誌『スポーツゴジラ』編集長。主な著書に『復活の力』(新潮新書)、『桜色の魂 チャスラフスカはなぜ日本人を50年も愛したのか』(集英社)など。
本書の要点
- 要点1シドニーのマラソン競技で金メダルを獲得した高橋尚子は、非常識の延長線上にしか金メダルはないと考え、過酷な環境に自分を追い込んだ。
- 要点2日本人初の金メダリストである織田幹雄は、外国人から失笑が漏れるほど小さかったが、日々研究を重ね、三段跳びで躍動した。
- 要点3長らく女子の試合が禁止されていた女子柔道界において、山口香は小内刈りを武器に、日本のみならず世界の頂点に立った。
要約
【必読ポイント!】 記憶に新しいメダリストたち
難コースを天国に変える力
オリンピックという決戦の舞台で闘うのがたった一人の生身の人間であることは、今も昔も変わらない。かれらは、一世一代の大勝負で何をしたのか。
『史上最大の難コース』といわれた2000年シドニーオリンピックのマラソンコースで、高橋尚子はオリンピック最高記録をたたき出し、マラソンで日本女子史上初の金メダルを獲得した。
この快挙を成し遂げるために、高橋は毎日40km程度走り込み、365日休むことはなかった。高橋は、さらに自らを過酷な環境に置くことを決断する。標高3500メートルから3600メートルの高地トレーニングである。非常識なことの延長線上にしか金メダルはないと考えたのだ。
高橋は、「練習はハードでいつも疲労困憊だったが、試合の1週間前からは体が楽で天国にいるみたいだった」という。史上最大の難コースを、自分の力で「天国」に変えてみせたといえるだろう。
足のほんの1点を見つける

TwentySeven/gettyimages
2004年アテネ・オリンピックの柔道最終日。ロシアの白熊の異名を持つトメノフを、鈴木桂治は見事な小外刈りで一本勝ちした。技を出す気配もなく、左足を相手の左足首あたりに軽く当てただけのような足さばきで、鈴木はなぜ巨漢のトメノフを仕留めることができたのか。
鈴木の足技に対する意識が変わったのは、国士舘大学時代の監督だった斎藤仁に「足を磨け」と言われてからだという。以来、鈴木の頭の中は2本の足でいっぱいになり、信号を待っている間も、脇に立つ標識や電柱に足技をかけて研究するほどだった。あるとき、サッカーボールを使った独自の練習の最中に、左足の親指の付け根と、くるぶし、足の内側の三角地帯の1点にボールを当てると思い通りにボールを蹴ることができることを発見する。以来、この1点の精度を研ぎ続ければ世界の扉を開くことができると思うようになる。オリンピックの決勝では、左足の黄金の1点の感覚は冴えに冴え、トメノフのわずかな重心の移動も逃さなかった。柔道は相手の重心移動さえつかめれば技を自在にかけられる、ということを証明した瞬間だった。
体の硬さを逆手にとる

gertfrik/gettyimages
2004年アテネと2008年北京において、100メートルと200メートルの平泳ぎで2冠を達成した北島康介だが、それぞれ異なる泳法で2大会の頂点に立ったことはあまり知られていない。
もともと北島は、体の硬さから将来を有望視されていなかった。しかし、平井伯昌コーチのもと、体の硬さを武器に推進力を生みだす泳法を身に着け、徐々にタイムを伸ばしていく。それは、100メートル、200メートルで世界新をたたき出すほど研ぎ澄まされ、アテネでも両種目で金メダルを獲得するまでに進化する。
4年後の北京を見据えて北島が取り組んだのは、上半身の改造計画だった。天性のキックが生み出す推進力と、決まった軌道でバネ仕掛けのように元に戻る手のかき。北島は、自分にしかできない四輪駆動の泳ぎを完成させることになる。
そして迎えた北京オリンピック、100メートル平泳ぎ決勝。世界記録保持者のハンセンに、長身の新鋭ダーレオーエンなど競合がひしめくこの種目で、北島は見事に世界記録を更新し、金メダルを獲得する。3日後に行われた200メートル決勝は、北島の圧勝だった。デメリットを最大の武器に転化する発想力と分析力、そして有言実行の強靱な意志が成し遂げた快挙である。
礎となった日本人選手たち
小さな体で遠くに跳ぶ
21世紀に活躍している選手の下支えとなったのは、過去に奮闘し、めざましい成果を残した先人たちであった。何人か紹介しよう。
外国人から失笑が漏れるほどその男は小さかった。しかし、大型の外国人に囲まれて陸上の三段跳びに出場した織田幹雄は、委縮するどころか飄々と遠くへ跳び、日本人初の金メダルを獲得する。
織田には剣術を極めようとする者のような雰囲気があった。勝敗よりもいかに理想に近づくかに主眼を置いていた。毎日の記録を丹念にノートに取り、理想の跳躍を追い求めて、天井や柱、街路樹にまで飛びつく日々。メイン種目は三段跳びだが、新たな走法や跳躍を求めてあらゆる陸上競技にも挑んだ。そして、競技で平常心を保つために、一流選手たちの記録を調べ上げ、部屋に顔写真を貼って慣れるようにした。
理想の跳躍を追い続けた織田は、1928年のアムステルダムオリンピックから3年後に世界新記録を打ち立て、ひとつの完成をみることになった。
絹のようにきれいな手で
世界新記録を樹立し、重量挙げフェザー級で金メダルを獲得した三宅義信は、1日に平均約50トンもの重量を長い間持ち上げ続けてきたという。しかし、その手のひらにはマメひとつなかった。バーベルの微妙な動きを感知するためには、手のひらをバーに密着させる必要がある。三宅は、鉄と向き合うため、その唯一の接点である手のひらのケアを欠かさなかったのだ。そして、心身ともに最高の状態の時、三宅は手のひらがピンクに染まることを発見する。そのコンディションを維持するために食事にも気をつかい、必要な栄養素をとれるよう、給料のすべてを食費に注ぎ込んだ。
1964年東京オリンピックで金メダルを獲得し表彰台に上がった三宅の手のひらは、絹のようにしなやかで鮮やかなピンク色に染まっていた。
ハンデを心眼で乗り越える

microgen/gettyimages
蒲池猛夫の両目は、顔面神経まひで同時に閉じない。強度の乱視ですべてのものがかすんで見える。おまけに右耳は難聴で、金属音が常に響いたままである。怪我のため右手の握力は女性並みしかなく、普通に曲がるのは親指だけだ。しかし、蒲池は、もろもろのハンディを全く感じさせないまま、1984年ロサンゼルスオリンピックのラピッドファイア・ピストル競技で金メダルを獲得した。蒲池の強さの秘密は、尋常ならざる集中力にあった。
ある日、瞼の裏に動き回る赤い玉が見えることに気づいた蒲池は、神経を集中しこれを止めることを試みる。そしてついに、意のままにこれを操ることができるようになった。それにより、雑念を振り払うことができるようになったのだ。蒲池はこの赤い玉を「心眼」だと信じた。眼を閉じたままでも10点満点の命中を狙えるようになった。
指先を眼にする
オリンピックを前にして、鈴木大地は背泳ぎでシーズン世界3位というタイムを記録した。トップとの差は、0.16秒で距離にして約29センチ、手のひらを縦に2つ並べたほどだった。オリンピックの本番では、勝負は紙一重になるはずだ。そこで、鈴木は、ゴールを目視できない背泳ぎでは特に重要となるゴールタッチを、手の指のなかで最も長く強い中指の腹でジャスト・ミートする練習に励んだ。
そして迎えた1988年ソウルオリンピック、鈴木の狙い通り、ゴール直前で混戦模様となった。鈴木の差し出したゴールタッチはまさしくジャスト・ミート。金メダルを獲得した鈴木の右手中指の腹は、眼に変わっていたのであろう。
じっとできなくても勝つ
子どものころから飽きっぽく、あわただしい振る舞いだった惠本裕子は、その「せわしなく落ち着きのないリズム」こそが、自分にやすらぎを与えることに気がついた。そこで、めまぐるしいリモコン操作のように自分を入れ替え、飽きないリズムのままにオフ・タイムを過ごすようにもなった。そうすることで別人のように調子がよくなるからだ。
迎えた1996年アトランタオリンピックの本番でも、惠本は片時もじっとしていなかった。控室を出たり入ったり、コーチとしゃべり続けたりした。
準決勝では、せわしなく隣の畳の戦況を分析しながら、目前の敵からポイントを奪い勝利。なんと、2つの畳の上での自分を切り替えつつ闘っていたのである。そして、決勝では見事な一本勝ちをおさめた。それは、日本女子柔道が初めて金メダルを獲得した瞬間だった。
女子選手が成し遂げた革命
武骨な武道への挑戦
第1回アテネ・オリンピック以来、傑出したスターはごくまれに生まれていたものの、全体的に見れば女性の活躍は極めて限られたものだった。だから、何代にもわたって男性選手が磨き上げてきた技を、女性はたった一代でカタチに変え、自らが歴史になるチャンスをつかもうとしてきたのだ。本書では、何人か画期的となった女性選手を紹介している。
東京オリンピック後、世界各国で柔道が普及したが、日本では1世紀以上、1978年まで女子の国内試合が禁じられた。理由は「母体保護」。柔道はあくまで武骨な男たちの武道だったのだ。そんななか、色白で着物が似合う可憐な容姿の山口香は、これまでの常識を覆す。13歳のとき第1回女子全日本選手権で優勝し、以来10連覇を達成する。
畳に立つと、まるでダンス・ミュージックを流しているかのように機敏なステップを踏み、得意の「小内刈り」を繰り出す。見た目は地味だが、体への負担が小さく、けがのリスクが少ないこの技を山口は極めたのだ。こうして山口は、1984年には世界の頂点に立ち、1988年のソウルでは銅メダルを獲得した。パワーが優先される柔道界で、世界に通用したのは山口の「小内刈り」だけだった。
日本人体型を武器にジャンプで魅了する

Ryan McVay/gettyimages
優雅さや華麗さなど、見た目の美しさが重視されたフィギュアスケートにおいて、伊藤みどりは大きなハンディを抱えていたといえるだろう。胴長、短足に小柄な肉体は、「見栄え」の点で極めて不利であるといわざるを得ない。しかし、伊藤はあきらめなかった。技で魅了するという方針のもと、女子で誰ひとり成功させたことのない3回転半ジャンプ、トリプルアクセルへの挑戦を決意したのだ。
3回転ジャンプの成功は、パワー、スピード、ジャンプの高さという3つの要素が完璧に揃うことが条件となる。さらに、トリプルアクセルにはプラスアルファの回転が必要だった。そこで伊藤は周囲の空気を利用することを思いつく。ジャンプの瞬間、両腕で思い切り空気を巻き上げ、滞空時間を延ばしたのだ。その甲斐あって伊藤は、日本人体型を最大の武器として軽業師のようにトリプルアクセルを決め、世界選手権やオリンピックで活躍した。
笑わないシンクロ
バルセロナのシンクロ競技で銅メダルを獲得した奥野史子だったが、壁にぶち当たる。芸術性に重きを置くようになった世界の潮流に乗り遅れたのだ。そこで奥野が挑戦したのが、笑わないシンクロ。笑顔が当たり前のシンクロ界において、タブーへの挑戦だった。
鏡の前で目をむき、口をゆがめ、歯をむき出す。毎夜、狂女が生肉を食らうパントマイムを続けた。そして、審査員に強烈な印象を与えるには、両目が重要であることに気づく。観客をねっとりとなめるように見るファッションモデルの目の運びを観察したり、白目の面積を増やす工夫をしたりした。
こうして奥野は、1994年の世界選手権のソロ演技で、審査員全員から芸術点で満点を獲得する。笑顔のシンクロの常識を覆した瞬間だった。
正確無比な集中力を生む技術
身長158センチの樋口久子が、世界進出のために生み出したゴルフのケンカ打法が、体全体を大胆に揺らして豪快に飛ばすスウェー打法だった。大きな体重移動で正確無比な弾道を可能としたのは、筋力トレーニングでもイメージトレーニングでもない。たったひとつのボールを使ったトレーニングだった。ゴルフボールをズボンのベルトと、ヘソの間に挟んでスイングする。フォームが崩れるとボールは下に落ちるが、腹筋に力が集中するとボールは前に飛び出す。樋口はこのトレーニングを繰り返したのだ。
そして、メンタルコントロールも完璧だった。大きなタイトルのかかった試合では、夜になると手芸やレース編みに精を出した。ボールはクラブで打つのではなく、神経が打つという信念があったからだ。1977年、樋口は全米プロ選手権で優勝を飾った。機械のような正確なプレーで観客を魅了した。

この続きを見るには...
残り0/4825文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.16
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











