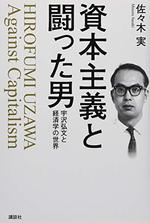EU離脱
イギリスとヨーロッパの地殻変動

著者
鶴岡路人 (つるおか みちと)
1975年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部准教授。専門は現代欧州政治、国際安全保障。慶應義塾大学法学部卒業後、同大学院などを経てロンドン大学キングス・カレッジで博士号取得。在ベルギー日本大使館専門調査員、防衛研究所主任研究官、英王立防衛・安全保障研究所(RUSL)訪問研究員などを歴任。東京財団政策研究所主任研究員を兼務。共編著に『EUの国際政治』(慶應義塾大学出版会)などがある。
1975年生まれ。慶應義塾大学総合政策学部准教授。専門は現代欧州政治、国際安全保障。慶應義塾大学法学部卒業後、同大学院などを経てロンドン大学キングス・カレッジで博士号取得。在ベルギー日本大使館専門調査員、防衛研究所主任研究官、英王立防衛・安全保障研究所(RUSL)訪問研究員などを歴任。東京財団政策研究所主任研究員を兼務。共編著に『EUの国際政治』(慶應義塾大学出版会)などがある。
本書の要点
- 要点12016年の国民投票では、EU離脱派が残留派をわずかに上回り、僅差で勝利した。
- 要点2EUへの無理解や、EU離脱の目的にコンセンサスが取れなかったことが、イギリス政治混迷の要因となった。
- 要点3メイ政権では離脱協定の議会承認を得られず、「合意なき離脱」回避のために最長2019年10月31日まで期日延期が決定した。その後、ジョンソン政権で再交渉の道が開け、同年10月17日に新たな離脱協定が合意され、EU離脱が確定した。
- 要点4北アイルランド国境問題は、EU離脱交渉の重大な論点であった。
要約
EU離脱問題を考えるにあたって
なぜ「EU離脱」に世界が驚いたのか

Delpixart/gettyimages
2016年、EU残留の是非をめぐってイギリスが実施した国民投票。離脱派と残留派の割合は大差なく、どちらに転んでも不思議ではなかった。結果は離脱が51.9パーセント、残留が48.1パーセントで、僅差で離脱派が勝利した。
世界がこの結果に衝撃を受けたのは、ヨーロッパ統合に対するイギリスの長年の基本的姿勢と相反していたからだ。イギリスがヨーロッパ統合(当時のEEC・欧州経済共同体)に参加したのは1973年。ヨーロッパ単一市場の一部になることで、経済的利益を追求するのが目的だった。そして1980年代半ば以降、イギリスは市場統合において中心的役割を果たし、その恩恵を受けてきた。だからこそ経済的損失をもたらすのが必至なEU離脱を、実用主義的なイギリス国民が選択するはずがないと誰もが考えていた。
ところが蓋を開けてみれば、EU離脱が残留を上回った。世界をはじめ、EUから加盟国が抜けるなど想像だにしていなかったイギリス以外のEU諸国およびEU諸機関を驚愕させたのも無理からぬことだ。
なぜ「EU離脱」でイギリスが迷走したのか
EU離脱がいかに複雑であったかは、イギリス政治の混迷ぶりを見れば想像に難くない。それを当のイギリスが理解していなかったことが、イギリスが迷走した第一の要因だ。EUから離脱したからといって、イギリスとEUとの関係がゼロになるわけではない。半世紀近くもEU加盟国として過ごしてきたのだから、互いに折り合いのつく着地点を見つけていくのは容易ではなかった。
第二に、離脱交渉の目標がイギリス政権内でも一致していなかったことが挙げられる。国民投票キャンペーンにおいて、残留派は経済的利益、離脱派は主権に焦点を当てており、国内のコンセンサスが取れていたとは言えない。それは2018年7月にメイ政権がまとめた離脱方針「チェッカーズ提案」にも表れている。どっちつかずの中途半端な離脱協定案は、議会で過半数の支持を得るには至らなかった。
第三の要因が、メイ政権が定めたレッドライン(絶対的条件)である。これは離脱交渉で譲歩できない一線を定めたもので、きわめてハードな内容であり、EUに対して強い姿勢で臨むことを国内に示すためのものだった。だがそれでまともな交渉になるはずもない。イギリスは離脱交渉の当初から、一貫性に欠けていたのだ。
機能不全に陥ったイギリス政治
万策尽きて退陣したメイ政権

Delpixart/gettyimages
2019年1月、離脱協定が史上最悪の票差で否決されて以降、メイ政権は議会の承認を得ることができないでいた。敵は与党である保守党内にもいたのだ。このままでは離脱日である3月29日が到来するや、自動的に「合意なき離脱」となってしまう。それを避けるには期日延期しかなかった。
メイ政権は、3月20日までに離脱協定が可決されなければ大幅延期するとした。これにより残留の可能性をほのめかし、「合意なき離脱」を求める強硬離脱派に脅しをかけたのだ。しかし二度も大差で否決されたものを可決させるのには無理があった。結局、離脱協定可決の目処は立たず、EUによって最長で2019年10月31日までの期日延期が決定された。

この続きを見るには...
残り3171/4492文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約