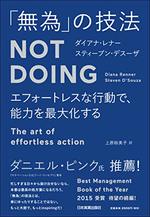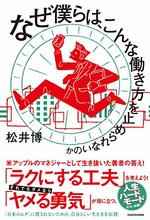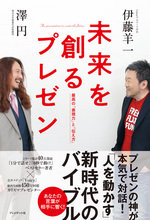免疫力を強くする
最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ
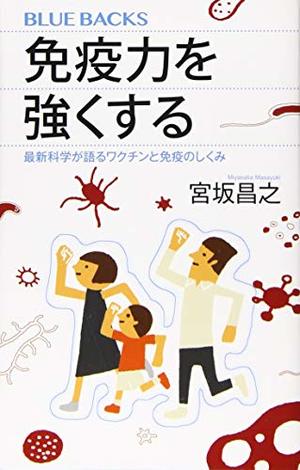
著者
宮坂昌之(みやさか まさゆき)
大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授。1947年長野県生まれ。京都大学医学部卒業、オーストラリア国立大学大学院博士課程修了。金沢医科大学血液免疫内科、スイス・バーゼル免疫学研究所、東京都臨床医学総合研究所等を経て、大阪大学医学部教授、同大学大学院医学系研究科教授等を歴任。医学博士・PhD。著書に『分子生物学・免疫学キーワード辞典』(医学書院、共編著)、『標準免疫学』(医学書院、共編著)、『免疫と「病」の科学 万病のもと「慢性炎症」とは何か』(講談社ブルーバックス、共著)など。
大阪大学免疫学フロンティア研究センター招へい教授。1947年長野県生まれ。京都大学医学部卒業、オーストラリア国立大学大学院博士課程修了。金沢医科大学血液免疫内科、スイス・バーゼル免疫学研究所、東京都臨床医学総合研究所等を経て、大阪大学医学部教授、同大学大学院医学系研究科教授等を歴任。医学博士・PhD。著書に『分子生物学・免疫学キーワード辞典』(医学書院、共編著)、『標準免疫学』(医学書院、共編著)、『免疫と「病」の科学 万病のもと「慢性炎症」とは何か』(講談社ブルーバックス、共著)など。
本書の要点
- 要点1人間のからだには、「自然免疫機構」と「獲得免疫機構」という2種類の免疫のしくみが備わっている。それでも体内に侵入してくる病原体による感染を防ぐため、免疫系を刺激するのがワクチンだ。
- 要点2科学的な免疫力増強法は、ワクチン接種だ。ワクチンは、インフルエンザや子宮頸がんなど、引き起こされる感染症ごとに異なるものを接種する必要がある。
- 要点3血管系やリンパ系における細胞の往来をすみやかにすれば、免疫力が高まる。
要約
感染症と免疫力
感染症を防ぐからだのしくみ

Francisco Solipa/gettyimages
感染症について科学的な側面から理解を深めるために、まずは感染症とそれを防ぐからだのしくみについて説明する。
感染症を引き起こす病原体が体内に侵入するのを防ぐために、人間のからだには2種類の免疫のしくみが存在する。それは「自然免疫機構」と「獲得免疫機構」だ。自然免疫機構は、生まれつきからだに備わっており、粘液や唾液などのバリアーや白血球が、病原体の働きを弱めたり病原体そのものを殺したりする。これに対し、獲得免疫機構は、生後に獲得されてくる免疫で、自然免疫機構を突破した病原体への対抗策だ。獲得免疫機構には学習効果がある。リンパ球が、以前に侵入した病原体を覚えていて、抗体などを用いてこれを撃退する。
代表的な病原体は、細菌・真菌・ウイルスの3種類に大別される。このうち細菌は、1個の細胞からなる単細胞生物だ。真菌はいわゆるカビのことで、単細胞で存在するものも多細胞を形成するものもいる。それぞれ抗菌薬(抗生物質)と抗真菌剤が有効となる。
一方で、ウイルスは、0.1マイクロメートル以下と小さく、生命の最小単位とされる細胞を持たない。自分でエネルギーを作ることができないので、宿主細胞の中に入り込み、増殖する。また、ウイルスには、抗菌薬は効かない。一部の抗ウイルス剤が効果を示すものの限定的である。よって自分の免疫力で排除する必要があるのだ。
非常に小さなウイルスは、10マイクロメートル以上の網目をもつ通常のマスクで防ぐことは難しい。また、むやみに抗菌グッズや空気清浄機を使うと、からだの表面や内腔に住み着いているよい細菌を殺してしまうことになるためお勧めできない。
ワクチンとは何か
私たちの体には、病原体を追い出すための巧妙な仕組みが備わっている。だが、それでも、病原体は体内に侵入し、感染症を引き起こす。1875年には、麻しん(はしか)がフィジー島で蔓延し、わずか10日間で約4万人が亡くなったという。
病原体に対して、人間はワクチンで対抗してきた。ワクチンとは、病原体の力を弱めたり、なくしたりして、人工的に作り出した製剤のことだ。感染症ごとに異なるワクチンが存在する。
ワクチンは、自然免疫系と獲得免疫系の両方を刺激する。そのうえで、獲得免疫系に対し免疫記憶を与えることで、特定の病原体に対し「出動待機状態」を作り出すことができるのだ。病原体による感染を防ぐために、あらかじめワクチンを接種することを「予防接種」と呼ぶ。
日本脳炎やはしかなど数多くの感染症に対するワクチンの開発が進み、その有効性が確立された。その一方で、ワクチンにはデメリットもある。たとえば、生きた病原体を使った生ワクチンの場合だと、病原体の感染力が少しは残っている。そのため、可能性は低いものの、その影響が出ることがある。ワクチンの種類によっては、アジュバントと呼ばれる免疫補助物質を一緒に投与することがあるが、これが腫れや発熱を引き起こすこともあるのだ。
ワクチンは、健康な人に投与・接種し、「病気にならない」という目に見えない効果をもたらすため、副作用があると批判にさらされやすい。しかし、感染症を防ぐうえでは極めて有効であることを忘れてはならない。
ワクチンを接種する前に知っておきたいこと

Daniel Chetroni/gettyimages
ここからはワクチン接種の前に知っておきたい内容の一部を紹介する。
まずワクチンには、定期接種と任意接種とがある。定期接種は、予防接種法で接種の対象や回数が定められているものだ。感染力が強い、あるいは致死率の高い感染症に対するA類と、インフルエンザや成人の肺炎球菌感染症に対するB類に分けられる。定期接種であれば、費用の全額あるいは一部を自治体が負担し、重い副反応が起きた場合の補償も厚い。一方、任意接種は、原則として自己負担であり、副反応が起きた場合の補償の給付額も低い。
ワクチン接種が広く勧められる理由は、個人が免疫記憶を獲得するだけにとどまらない。ワクチンを接種する人が増えると、コミュニティの中で感染しない人が増えるため、その集団全体が感染症にかかりにくくなる。つまり、個人だけでなく集団(社会)も守られるのだ。
一般的な治療薬の場合、主な薬理作用以外の好ましくない作用のことを副作用という。好ましくない作用である局所の赤み、腫れ、発熱などは、からだの免疫反応を利用したものなので、副作用のかわりに副反応とよばれている。免疫反応の個人差は大きく、ワクチンに副反応というリスクがある以上、それを補償する制度が求められる。しかし、日本ではワクチンの副反応に対する補償制度は十分ではなく、改善の余地があるといわざるを得ないのが実情だ。
感染症別ワクチンの現状と問題点
インフルエンザ
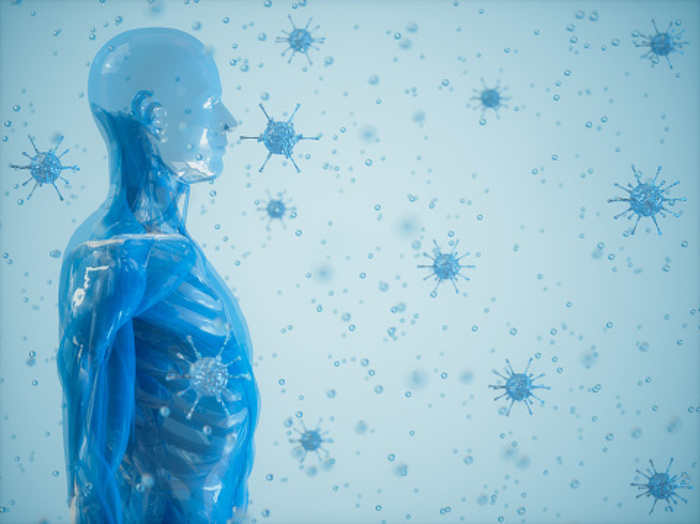
onurdongel/gettyimages
つづいて、ワクチンで防げる可能性の高い感染症として、インフルエンザと子宮頸がんそれぞれのワクチンの現状と問題点について簡単に説明する。
まずは、インフルエンザウイルスが引き起こす病気、インフルエンザについてだ。なお、風邪は、ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルスなどが原因となるため、インフルエンザとは根本的に異なることに注意したい。
インフルエンザには、季節性インフルエンザと新型インフルエンザとがある。季節性インフルエンザは、A型あるいはB型のインフルエンザウイルスが引き起こすが、その抗原性は毎年少しずつ変化していく。そのためワクチンの効きが悪くなり、流行るのだ。この変化は「抗原ドリフト」と呼ぶ。
世界的な脅威になるのが新型インフルエンザだ。「抗原シフト」と呼ばれるウイルスの表面抗原での大きな変異により、ほとんどの人が免疫を持たないウイルスが誕生する。そして、世界的な規模で流行するパンデミックを引き起こす。新型インフルエンザが世界で猛威を振るった例として、1918年のスペイン風邪で数千万人、1957年のアジア風邪では約200万人、1968年の香港風邪では約100万人がそれぞれ亡くなっている。

この続きを見るには...
残り1966/4406文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.05.23
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 宮坂昌之 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は宮坂昌之、株式会社フライヤーに帰属し、事前に宮坂昌之、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 宮坂昌之 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は宮坂昌之、株式会社フライヤーに帰属し、事前に宮坂昌之、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約