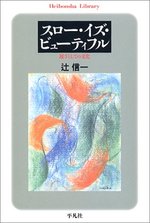高瀬舟
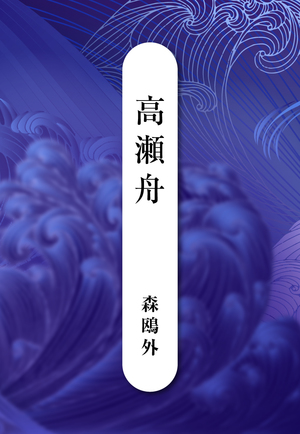
高瀬舟
著者
本の購入はこちら
こちらの書籍は書店にて
お買い求めください。
お買い求めください。
書籍情報を見る
本の購入はこちら
こちらの書籍は書店にて
お買い求めください。
お買い求めください。
著者
森鴎外
1862年生まれ。軍医としての仕事のかたわら、『舞姫』や『雁』などを執筆。
1862年生まれ。軍医としての仕事のかたわら、『舞姫』や『雁』などを執筆。
本書の要点
- 要点1高瀬舟は京都の高瀬川をゆく小舟だ。島流しを命じられた京都の罪人は、高瀬舟で護送される決まりになっていた。
- 要点2ある日、高瀬舟に乗せられたのは、弟殺しの罪を犯した喜助という人物だ。護送人は、嫌がるどころか、今にも鼻歌を歌い出しそうな喜助の態度を不思議に思い、そのわけを尋ねた。
- 要点3喜助が罪を犯したのは、重病に苦しむ弟から懇願されたためであった。護送人はそのいきさつを聞き、喜助の罪は本当に罪といえるのか、答えを出せないでいる。
要約
珍しい罪人
高瀬舟と罪人
高瀬舟は京都の高瀬川をゆく小舟である。徳川時代に京都の罪人が流罪を申し渡されると、親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで別れの挨拶をすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて、大阪へまわされる。罪人の親類のうち、たった一人だけが、罪人とともに大阪まで同船することが黙認されていた。それを護送するのは、京都町奉行の配下にいる下級役人だ。
罪人を乗せて、日の暮れ方の鐘の鳴る頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、加茂川を横切って下るのであった。
舟の中で、罪人と親類の者は夜どおし身の上を語り合う。護送人はそばでそれを聞いて、罪人を出した親類たちの悲惨な境遇を細かに知ることができた。
護送人の疑問

知恩院の桜が日の暮れ方の鐘に散る春の夕に、世にも珍しい罪人が高瀬舟に乗りこんだ。
その罪人は喜助という。30歳ばかりになる、住所不定の男だ。身寄りがないため、同船者はいない。
護送を命ぜられた羽田庄兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。様子を見ていると、彼はいかにも神妙でおとなしく、自分にこびへつらうことも、逆らってくることもないようだ。不思議に思って、絶えず喜助の挙動に注意を払っていた。
日の暮れるころには風がやんだ。空一面を覆った薄い雲が月の輪郭をかすませ、近寄ってくる夏のあたたかさが、両岸の土からも、川床の土からも、もやになって立ち昇るような夜だった。下京の町を離れて加茂川を横切った頃からは、あたりがひっそりとして、ただ船首に割かれる水のささやきだけが聞こえてくる。
喜助は横になろうとせず、雲の濃淡とともに光が増えたり減ったりする月を見上げてただ黙っている。その様子は晴れやかで、目にはかがやきさえ宿っているようだ。
庄兵衛はどうしても喜助の顔から目が離せない。彼はなんとも楽しそうだ。今にも口笛を吹きはじめたり、鼻歌を歌い出したりしそうなほどである。
これまでこの高瀬舟には何度も乗ってきた。しかし罪人たちは誰もが、見ていられないほど気の毒な様子だったものだ。それなのにこの男は遊山船にでも乗ったような顔をしている。ひょっとして気でも狂っているのではあるまいか……。考えれば考えるほど、喜助の楽しげな態度の理由がわからない。

この続きを見るには...
残り2789/3736文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.08.31
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約