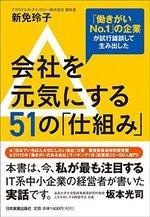「顧客志向」の落とし穴
顧客の声から破壊的イノベーションは生まれない

「顧客第一」、「顧客志向」。企業が業績回復を狙う際の方針として、よく使われる言葉である。一見、至極まっとうで真摯な態度であるが、その経営効果はいかほどであろうか。
ビジネスにおける「顧客第一主義」の重要性を最初に提唱したのは、ピーター・ドラッカーである。彼の著書によると、世界で初めて近代的マーケティングを実行したのは、江戸時代に創業した日本の越後屋であるという。「お客様は神様」という接客精神に象徴されるように、店側は顧客の要望や注文を徹底的に聞き、顧客は店員に甘える。しかし、こうした受動的な態度を取るだけの企業は、変化していく顧客の心理を汲み取ることができない。
一方、「従業員第一主義」を掲げる企業もある。従業員にとっての幸せを追求することで、従業員のパフォーマンスが上がり、顧客や企業に恩恵がもたらされるという考え方だ。企業と顧客の間に立つ従業員がうまく機能すれば、顧客の声を上手く活かして既存の商品やサービスを育てていくことができる。
しかし、これが通用するのは、既存製品の改善・改良という「持続的イノベーション」だけである。「破壊的イノベーション」を生み出すときには、意味を成さないだろう。アップル社のスティーブ・ジョブズがマッキントッシュを発売する際も、顧客の声は聞かなかったという。顧客の声というのは、常に顧客の想像できる範囲内であるため、革新的な製品を生み出すときには必要ないのだ。結局のところ、顧客の声を聞きすぎることで、企業は自らの可能性を狭めてしまっているということになる。企業はもっと、「自分の心の声(直感)」を聞いたほうがよい。
「プライシング」の落とし穴
企業の体力を奪う「値下げ競争」
2001年から10年以上にわたって、牛丼のチェーン店がこぞって値下げ競争を繰り広げた。業界第2位だった「松屋」、第3位の「すき家」が、それぞれ牛丼の値段を100円以上値下げした。その後、業界第1位だった「吉野家」がこの値下げ競争に参戦したことにより、競争は長期化し、牛丼の慢性的な低価格化の一途をたどることになった。
「吉野家」は価格を下げずに牛丼のブランドを守ることもできたのに、なぜこうした決断を下したのか? 当時の「吉野家」はBSE問題のさなか、米国産牛肉にこだわり牛丼の販売を停止していたこともあり、企業体力を大きく削られてしまっていた。安部社長は、過去の倒産という失敗経験に基づいて意思決定をする「パターン認識」と、敬愛した先代の価値観への絶対的信奉によって、経営判断のミスを犯したといえる。業界トップを走っていたにも関わらずフォロワー企業に合わせて値下げをし、一方で肉の品質にはこだわり続けるという矛盾した戦略となってしまった。
「価値」と「価格」のつりあい

当時はデフレの影響で、牛丼に限らず各業界において値下げ競争は激しくなり、長期化し、それが常態化していた。