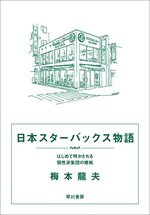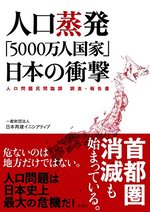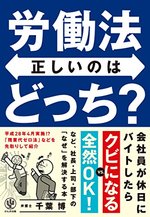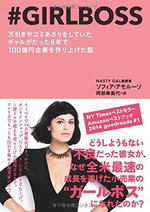なぜ気づいたらドトールを選んでしまうのか?
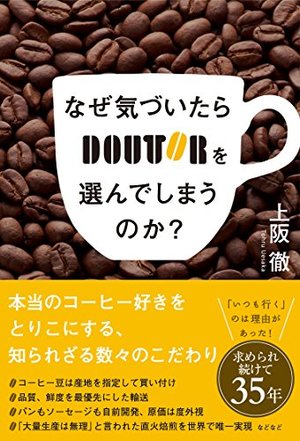
なぜ気づいたらドトールを選んでしまうのか?
著者
著者
上阪 徹(うえさか・とおる)
1966年、兵庫県生まれ。89年、早稲田大学商学部卒。アパレルメーカーのワールド、リクルート・グループを経て、95年よりフリーランスのライターとして独立。雑誌や書籍などで執筆。
著書に『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか?』(あさ出版)、『「胸キュン」で100億円』(KADOKAWA)、『弁護士ドットコム、困っている人を救う僕たちの挑戦』(共著・日経BP社)、『僕がグーグルで成長できた理由 挑戦し続ける現場で学んだ大切なルール』(日本経済新聞出版社)、『成功者3000人の言葉 人生をひらく99の基本』(飛鳥新社)など。インタビューで書き上げるブックライター作品も60冊以上を数える。
1966年、兵庫県生まれ。89年、早稲田大学商学部卒。アパレルメーカーのワールド、リクルート・グループを経て、95年よりフリーランスのライターとして独立。雑誌や書籍などで執筆。
著書に『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか?』(あさ出版)、『「胸キュン」で100億円』(KADOKAWA)、『弁護士ドットコム、困っている人を救う僕たちの挑戦』(共著・日経BP社)、『僕がグーグルで成長できた理由 挑戦し続ける現場で学んだ大切なルール』(日本経済新聞出版社)、『成功者3000人の言葉 人生をひらく99の基本』(飛鳥新社)など。インタビューで書き上げるブックライター作品も60冊以上を数える。
本書の要点
- 要点1ドトールの創業者は、「コーヒーで人に喜んでほしい」という思いを起点に、「一杯150円で成り立つ店づくり」を考えていった。コーヒーやフード、食器、すべてにおける本物へのこだわりが、顧客が殺到する店づくりにつながった。
- 要点2ドトールは、おいしいコーヒーの三要件、コーヒー豆、焙煎、抽出の全プロセスを徹底的に改革していった。
- 要点3ドトールは、タバコのイメージを払しょくするために、独自の空調システムを生み出し、外装を白くした「白ドトール」を登場させ、イメージを刷新した。
要約
【必読ポイント!】 ドトールの「こだわる」理由は創業にあり
ブラジルに渡った若者の一大決心
ドトールが全国に広がっていった背景には、創業者である鳥羽博道氏の強烈な理念と、それを支える数々のドラマがあった。
昭和30年代、当時20歳でコーヒーの卸売会社に勤めていた博道氏は、ブラジルの農園を手伝うという一大決心をした。ブラジル人とのつながりを育てた3年間を経て、理想の会社は自分でつくるしかないと考えた博道氏は、帰国の翌年に有限会社ドトールコーヒーを設立した。
コーヒー豆の焙煎卸業はなかなか軌道に乗らず、毎朝のように「倒産」の文字が博道氏の頭をよぎったという。そんな中、驚くような回転率を誇る京都の喫茶店にめぐり会った。そのことがきっかけとなって、博道氏は、当時の喫茶店が持つ退廃的で不健康なイメージを払しょくし、老若男女が気軽に集まる新しい喫茶業を生み出したいと思い始めたのである。こうして、ドトールの前身となるコーヒー専門店「カフェ・コロラド」が、1972年、東京・三軒茶屋に誕生し、驚くほどの繁盛ぶりを見せた。本格的なコーヒーと、他にはない軽食、そして創業者のブラジルでの経験やセンスが活きた内装デザイン。これらが評判を呼び、コロラドは10年かけて250店舗にまで拡大していったのである。
一杯150円で成り立つ店づくり
博道氏は、ヨーロッパの焙煎業や喫茶業の視察ツアーに参加し、パリのコーヒー文化や、ドイツの有名コーヒーショップにあった挽き売りコーナー、スイスの焙煎工場のクリーンさにふれ、大きな感動と気づきを得る。「安い値段で、さっとコーヒーを飲んで会社に向かえる」。ヨーロッパで見た構想を、日本で実現するときが来たと直感した。それが形になったのが、1980年、東京・原宿に誕生したドトール一号店である。
世間を驚かせたのは、コーヒー一杯150円という革命的な価格設定だった。喫茶店で飲めば、300円、400円が当たり前の時代である。博道氏は「コーヒーで人に喜んでほしい」という思いを起点に、そこから逆算してフードメニューの充実や、全自動で抽出する機械の導入など、「一杯150円で成り立つ店づくり」を考えていった。
極限までこだわるドトールの流儀

©iStock.com/milosljubicic
ドトール一号店には、本格的なコーヒー、そして一客2300円という高級カップが用意されていた。業界から見ても「クレイジー」に映る本物へのこだわりが、顧客にもきちんと伝わっていたからこそ、顧客が殺到したのだろう。「今までにないものをつくり上げていく」という創業者の思いは、ミリ単位で計算し尽くされた形のオリジナルカップにも現れている。

この続きを見るには...
残り3136/4221文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.09.30
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約