労働法 正しいのはどっち?
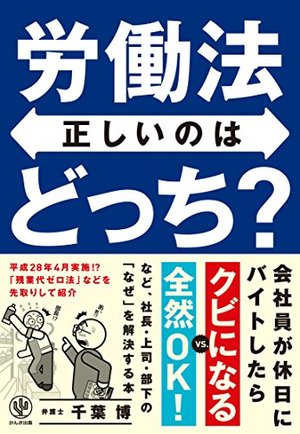
労働法 正しいのはどっち?
著者
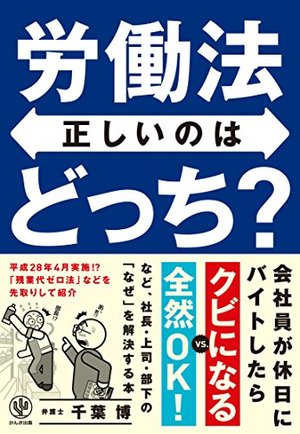
著者
千葉 博
千葉総合法律事務所代表。弁護士。大手資格試験予備校LEC専任講師。司法試験専任講師として21年間教鞭をとり続け、「カリスマ講師」の異名をとる。
平成2年に東京大学法学部を卒業し、平成3年に司法試験合格。平成6年に弁護士登録をして以来、これまでに扱った事件は5000件以上。労働・企業法務・保険等を専門とし、現在も年間数百回法廷に立つ。
司法試験専任講師として磨き上げた「わかりやすい教え方」には定評があり、関東学院大学・神奈川大学で講師を務めたほか、日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールの講師として、これまでに「1日でわかる! 労働基準法のすべて」「人事担当者のための採用から退職までの労働法の基礎とQ&A」「セクハラ・パワハラ防止と問題社員対応のための労働法講座」などを担当してきた。その他、SMBCコンサルティングやみずほ総合研究所が主催する金融系ビジネスセミナーを中心に、年間の登壇回数は100回を超える。
著書に、『人事担当者のための労働法の基本』『労働法実務相談シリーズ② 労働時間・休日・休暇Q&A』(以上、労務行政)、『改正法対応 会社法の基本がわかる事典』(三修社)、『従業員の自動車事故と企業対応』(清文社)、『スランプに負けない勉強法』(フォレスト出版)、『千葉式オーガナイザーシートなら! 最短で資格試験に合格できる本』(明日香出版社)など多数。
千葉総合法律事務所代表。弁護士。大手資格試験予備校LEC専任講師。司法試験専任講師として21年間教鞭をとり続け、「カリスマ講師」の異名をとる。
平成2年に東京大学法学部を卒業し、平成3年に司法試験合格。平成6年に弁護士登録をして以来、これまでに扱った事件は5000件以上。労働・企業法務・保険等を専門とし、現在も年間数百回法廷に立つ。
司法試験専任講師として磨き上げた「わかりやすい教え方」には定評があり、関東学院大学・神奈川大学で講師を務めたほか、日本経済新聞社が主催する日経ビジネススクールの講師として、これまでに「1日でわかる! 労働基準法のすべて」「人事担当者のための採用から退職までの労働法の基礎とQ&A」「セクハラ・パワハラ防止と問題社員対応のための労働法講座」などを担当してきた。その他、SMBCコンサルティングやみずほ総合研究所が主催する金融系ビジネスセミナーを中心に、年間の登壇回数は100回を超える。
著書に、『人事担当者のための労働法の基本』『労働法実務相談シリーズ② 労働時間・休日・休暇Q&A』(以上、労務行政)、『改正法対応 会社法の基本がわかる事典』(三修社)、『従業員の自動車事故と企業対応』(清文社)、『スランプに負けない勉強法』(フォレスト出版)、『千葉式オーガナイザーシートなら! 最短で資格試験に合格できる本』(明日香出版社)など多数。
本書の要点
- 要点1労働法は個人と法人の間の問題を解決するための法律である。弱い立場になりがちな労働者を保護するため、労働者に有利な考え方が含まれている。
- 要点2一方で、行きすぎた労働者保護を見直すために経営側からも提案がされており、労働法は何度も改正されてきた。
- 要点3平成27年の通常国会で審議されている労働基準法の改正案で注目すべき点は、「残業代ゼロ制度」と呼ばれる「特定高度専門業務・成果型労働制」の導入可否である。労使双方にメリットがある方向性を目指しているが、実現を懸念する声も多い。
要約
労働者を保護する労働法
民法だけでは、労働者は守れない
もともと、労働者と企業の関係は、労働基準法の制定前から民法で定められていた。なぜ新たに労働法が必要になったのだろうか? それは「民法の規定が使いものにならなかったから」だと著者は言う。
「国民はみな平等」という世界観をもつ民法には、法の介入なく、各自が自由にやってもよいという「私的自治の原則」がある。雇用契約の分野でも、会社はいつでも労働者を解雇することができる「解雇自由の原則」が規定されている。しかし実際には、労働者の立場は弱くなりがちであるため、労働者を保護し、使用者側を抑止するための法律が別途必要となった。それが労働基準法や労働契約法などの労働法である。
解雇には十分な正当性が必要!

Ljupco/iStock/Thinkstock
労働契約法では「解雇権濫用法理」が定められている。労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由がなくてはならず、社会通念上相当、すなわち解雇が重すぎないといえる場合でなければならないとされている。たとえば、あまりに仕事ができない社員であっても、その事実を客観的に証明できるか(企業側の立証責任)、研修や教育の機会が十分にあったか(解雇回避努力義務)といった点をクリアしなければ解雇は認められないというわけだ。
アナウンサーの内定取消問題でも、この「解雇権濫用法理」が最大のハードルとなった。企業側は「アナウンサーには高度な清廉性が必要」と主張したが、実際には世論の批判も後押しとなり、内定取消は取り下げられた。「社会通念上相当」とは言えないという判断がなされた一例だといえる。
整理解雇の注意点
不況のあおりを受けて行う整理解雇の場合、会社都合の側面が強いため、その実施はいっそう困難となる。整理解雇の4要件である「人員整理の必要性」、「解雇回避の努力を尽くしたこと」、「対象者の選定基準の公正さ」、「労使間の協議手続が取られていること」を満たしたうえで、整理解雇が妥当かどうかを判断しなくてはならないからだ。
近年ではJALの整理解雇が認められたケースが話題となったが、企業側の勝利は珍しく、整理解雇が争われて訴訟になった場合、会社の敗訴率は8割程度とも言われている。
企業としては本人の意思による退職という形を取ることが望ましいが、退職を強要したと取られないよう、進め方には注意が必要だ。声を荒げて退職を迫るような行為は当然NGである。一方で、

この続きを見るには...
残り2659/3651文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.10.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











