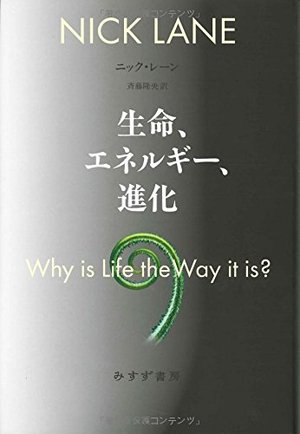生命、エネルギー、進化
著者
ニック・レーン
Nick Lane
ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)遺伝・進化・環境部門、UCL Origins of Lifeプログラムリーダー。2015年、Biochemical Society Award(英国生化学会賞)を受賞。著書に、The Vital Question: Why Is Life the Way It Is?, Profile Books, 2015 (斉藤隆央訳『生命、エネルギー、進化』みすず書房、2016)、Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution, Profile Books/W. W. Norton, 2009 (斉藤隆央訳『生命の跳躍』みすず書房、2010)、Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Meaning of Life, Oxford University Press, 2005 (斉藤隆央訳『ミトコンドリアが進化を決めた』みすず書房、2007)、Oxygen: The Molecule that made the World, Oxford University Press, 2002 (西田睦監訳、遠藤圭子訳『生と死の自然史――進化を統べる酸素』東海大学出版会、2006)、共著書にLife in the Frozen State, CRC Press, 2004がある。科学書作家としても高い評価を得ており、Life Ascendingは王立協会による2010年の科学書賞を受賞。
Nick Lane
ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)遺伝・進化・環境部門、UCL Origins of Lifeプログラムリーダー。2015年、Biochemical Society Award(英国生化学会賞)を受賞。著書に、The Vital Question: Why Is Life the Way It Is?, Profile Books, 2015 (斉藤隆央訳『生命、エネルギー、進化』みすず書房、2016)、Life Ascending: The Ten Great Inventions of Evolution, Profile Books/W. W. Norton, 2009 (斉藤隆央訳『生命の跳躍』みすず書房、2010)、Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Meaning of Life, Oxford University Press, 2005 (斉藤隆央訳『ミトコンドリアが進化を決めた』みすず書房、2007)、Oxygen: The Molecule that made the World, Oxford University Press, 2002 (西田睦監訳、遠藤圭子訳『生と死の自然史――進化を統べる酸素』東海大学出版会、2006)、共著書にLife in the Frozen State, CRC Press, 2004がある。科学書作家としても高い評価を得ており、Life Ascendingは王立協会による2010年の科学書賞を受賞。
本書の要点
- 要点1著者は「エネルギーを方程式に持ち込んで初めて生命の特質がわかる」こと、そして「生命の根本的な特質は、惑星に生じた不均衡から必然的に現れた」ことを提示する。
- 要点2生命の誕生は、1個の細菌が1個の古細菌の中に入った内部共生(細胞内共生)という、実にまれな出来事が引き起こしたものである。
- 要点3生命の起源は、アルカリ熱水噴出孔であり、薄い半導体の壁をはさんだ天然のプロトン勾配を利用して、「化学反応が起きづらい」という制約を打ち破った。
要約
【必読ポイント!】 なぜ生命が誕生したのか
生物学の中心には、ブラックホールがある
あらゆる植物、動物、菌類、藻類、そしてアメーバのような単細胞の原生生物は、15~20億年ほど前、たった一つの祖先から誕生した。この祖先は、細菌にはなかった数千の新しい遺伝子がコードする高度なナノマシン(ナノメートルサイズの「機械」)を原動力としている。形態が単純な細菌と、複雑なあらゆる生物の間に、進化の中間体として残っているものは一つとしてない。著者の言葉を借りれば、「生物学の中心には、ブラックホールがある」のだ。
なぜ細胞が現在のような仕組みになっているのか。このテーマに真っ向から取り組む生物学者はわずかしかない。もちろん、自然選択とゲノムをつくり上げる過程については解明が進んでいるが、生命がなぜこんな特異な道筋を辿ったのかは未知の領域とされてきた。
生命観を覆す三大革命
細菌と生命との関係のルーツは、1670年代のオランダの顕微鏡学者レーウェンフックによる微生物の発見に見出すことができる。彼はあらゆる複雑な細胞が持つ、遺伝子の貯蔵庫と呼べる「細胞核」を目にしていた。そこから進化論者のヘッケルが細菌をほかの微生物と分けた。
そこから過去半世紀に、これまでの生命観を覆す三大革命が起きた。第一の革命は1967年、リン・マーギュリスによる「連続細胞内共生説」である。連続細胞内共生説とは、真核生物が細菌の集合体であり、酸素濃度が上昇した24億年前の大酸化事変後に数億年かけて共同の営みの中でつくり上げられたとする説である。
第二の革命は、遺伝子の祖先を把握する「系統学的革命」だ。生物のタンパク質のアミノ酸配列に、進化にまつわる莫大な量の情報が書き込まれているとフランシス・クリックは予想していたが、実際にそれは正しかった。また、カール・ウーズはある遺伝子を選んで、大腸菌などの細菌から酵母、ヒトに至るまで、さまざまな種間でその差異を比較し、生命の大系統樹を解明しようとした。彼が目を向けたのは、すべての細胞の基本的特性である、タンパク質の合成能力だ。ウーズは植物と動物と菌類との差がわずかであり、生命の「第三のドメイン(超生物界)」の存在を発見した。「3ドメイン」の生命の系統樹では、古細菌と真核生物は「姉妹グループ」に属し、共通の祖先を持つという。
そして現在、私たちは第三の革命の真っただ中にある。ミトコンドリアと葉緑体は細菌の内部共生に由来するが、いつ、どんな細胞がミトコンドリアを獲得したのかはいまだわからない。しかしこの数年で、宿主細胞は古細菌(古細菌ドメインの細胞)だと判明した。つまり、核や性、食作用といった、複雑な生命ならではの特徴が存在しなかったのだ。
40億年の進化において、あるとき突然、複雑な生命が、古細菌という宿主細胞とミトコンドリアになる細菌とのたった一度の内部共生によって誕生した。進化論学者マーティンは、1998年の時点でこの事実をすでに予測しており、後のゲノム研究によってその正しさが実証されたのである。
類まれなる内部共生の発生
なぜ生命は、こんな不可解なプロセスで進化を遂げたのか。著者は本書を通じて、「エネルギーを方程式に持ち込んで初めて生命の特質がわかる」こと、そして「生命の根本的な特質は、惑星に生じた不均衡から必然的に現れた」ことを提示しようとする。さらには、プロトン勾配が細胞出現のキーであり、その利用が細菌と古細菌の構造に制約を課し、永久に単純な形態にとどめさせていることを立証していく。
また、この制約を打ち破ったのは、1個の細菌が1個の古細菌の中に入った内部共生(細胞内共生)という、実にまれな出来事が起きたためだという。

この続きを見るには...
残り2807/4332文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.03.28
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約