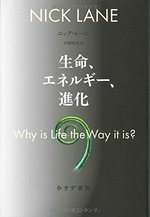N女の研究

N女の研究
著者

著者
中村 安希(なかむら あき)
ノンフィクション作家。1979年京都府生まれ、三重県育ち。カリフォルニア大学アーバイン校芸術学部演劇科卒。日米での3年間の社会人生活を経て、684日(47カ国)に及ぶ取材旅行を敢行する。2009年その旅をもとに書いた『インパラの朝』(集英社)で開高健ノンフィクション賞を受賞。その後も世界各地の生活を取材し、現在までに訪れた国は約90カ国。 著書に、若き政治家たちへのインタビューを試みた『Beフラット』(亜紀書房)、世界の食と文化を取材した『食べる。』『愛と憎しみの豚』(共に集英社)、またLGBTをテーマに執筆した『リオとタケル』(集英社インターナショナル)がある。
ノンフィクション作家。1979年京都府生まれ、三重県育ち。カリフォルニア大学アーバイン校芸術学部演劇科卒。日米での3年間の社会人生活を経て、684日(47カ国)に及ぶ取材旅行を敢行する。2009年その旅をもとに書いた『インパラの朝』(集英社)で開高健ノンフィクション賞を受賞。その後も世界各地の生活を取材し、現在までに訪れた国は約90カ国。 著書に、若き政治家たちへのインタビューを試みた『Beフラット』(亜紀書房)、世界の食と文化を取材した『食べる。』『愛と憎しみの豚』(共に集英社)、またLGBTをテーマに執筆した『リオとタケル』(集英社インターナショナル)がある。
本書の要点
- 要点1高い能力や職歴を持ちながら、ソーシャルセクターを就職先に選ぶ「N女」たちは、自律的に力を発揮し、自由に社会をクリエイトできる新たな活躍の場としてNPOをとらえている。
- 要点2NPOは慢性的な資金不足と低賃金という課題を抱えている。一方、ボランティアに下支えされた「手弁当型」から、専門性ある職員を雇って成長していく「ベンチャー型」へと変化しつつある。
- 要点3N女たちは自己犠牲を良しとせず、圧倒的な当事者性を背負い、適切な自己主張によって問題の社会化を図っている。
要約
はじめに
N女とはいったい何なのか?
現在、ソーシャルセクターの必要性が増す一方である。ソーシャルセクターとは、従来の行政サービスや市場経済の枠組みでは対応しきれない社会問題に取り組むNPO法人や社会的企業を指す。
大企業に就職できる高学歴、優秀な職歴、事業運営のノウハウを持っていながら、あえてソーシャルセクターを就職先に選ぶ女性たち。自分の興味に正直で、自主自律的な彼女たちを「N女」と呼ぶ。彼女たちが自分の力を発揮し、自由に社会をクリエイトできる新たな活躍の場として、NPOが選ばれているのではないか。そんな仮説のもと、著者はN女たちにインタビューを行い、その生態を探っていく。なぜソーシャルセクターにたどり着いたのか。日々何を考え、どこをめざしているのか。彼女たちの視点から女性の働き方や、社会の実情が浮かび上がっていく。
「難民支援協会」広報部チームリーダー 田中志穂
「支援したいから」ではない関わり方

Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock
ここからは著者が取材したN女のストーリーの一部を紹介していく。「難民支援協会」広報部に属する田中さんは、子どもの頃から海外への憧れを抱いていた。しかし高校時代のアメリカへの交換留学では、生徒が肌の色ごとにグループをつくるという、居場所のない日々を経験した。また、アメリカ社会に溶け込めないもどかしさを解消しようと飛び込んだゴスペル部では、自分の中にも偏見や差別意識があることを認識させられたという。この偏見を乗り越えたいという思いが、「難民支援協会」へと足を向ける萌芽となった。
大手飲料メーカーに就職して5年半が経ったところで、彼女は夫についていくために渡米し、大学院で異文化コミュニケーションを学んで、大いに刺激を受けた。帰国後、国際社会学の修士課程で学ぶさなか、難民支援協会の代表理事に出会った。就職の決め手は、活気ある現場や、一緒に働きたいと思える職業意識の高い仲間だった。
田中さんのスタンスは、支援ありきではなく、自分の経験とスキルを活かせるなら活かしていくというものだ。もちろん広報担当として人々に「支援」を訴え、資金を集めなければならない。しかし、「かわいそうな弱者に支援を」という訴えが一人歩きすると、それは支援対象者の尊厳を奪い、人々の間に上下関係のような意識を生み出しかねない。そんな葛藤と田中さんは闘っている。
NPOが抱える低賃金という課題
NPOは慢性的な資金不足と低賃金という課題を抱えている。N女の出現の背景には、収入の安定した夫の支えがあるという事実が、N女の存在自体を危ういものにしている、と著者は語る。本来なら民間企業かNPOかにかかわらず、提供した価値や能力に見合った報酬が必要なはずだ。
しかし実際には、社会のあらゆる局面で進む「アウトソーシング化」に伴い、N女たちは、一部の正社員や行政職員と同一労働でありながら、賃金はその半分である。階級社会の「便利な下請け」として扱われていることも少なくない。NPO職員が「都合よく買い叩かれる現実」に著者は懸念を抱く。
NPOサポートセンター 事業部プロデューサー 杉原志保
組織としてのマネジメント能力の重要性

RomoloTavani/iStock/Thinkstock
NPO業界の運営は、かつての市民運動のような、ボランティアに下支えされた「手弁当型」から、専門性ある職員を雇って成長していく「ベンチャー型」へと変化しつつある。しかし、多くのNPOは資金集めや人材育成などの多くの課題を抱えている。こうしたNPOを支え、あらゆるセクターの架け橋として、「NPOサポートセンター」のような中間支援組織の必要性が増している。
同センターで事業部プロデューサーを務める杉原さんは、ジェンダーの研究をしていた流れで、市役所の男女共同参画の仕事に就いた。そこで「良い活動だから予算を増額してほしい」という一方的な主張に終始するDVシェルターのNPOと出会ってきた。役所の政策には優先順位があり、予算をつけたいのはやまやまである。
このとき彼女は「役所を叩いても意味はない。民間から浅く広く集金するシステムをつくらないといけない」と痛感したという。NPO自体が組織としてのマネジメント能力を磨き、発展するのをサポートしたい。そんな思いから杉原さんは、助成金を配分する側である財団を経て、NPOサポートセンターへと転職した。
官・民・ソーシャルの「つなぎ役」
DVシェルターや生活困窮者支援といった、人権や社会福祉分野のNPOでは、資金調達、広報活動、人材確保において三重苦を抱えている。つまり、支援対象者が収益源にならないために寄付や助成金に頼らざるを得ないことや、支援対象者のプライバシーを守らなければならないこと、そして支援する側の精神的負担が大きいことが、課題として挙げられる。
だからこそ行政、民間、NPOの「つなぎ役」としてリーチできる中間支援組織は多くの可能性を秘めている。

この続きを見るには...
残り2282/4275文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.03.29
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約