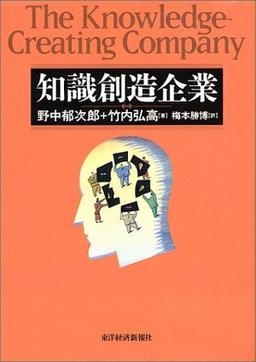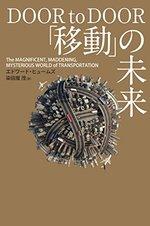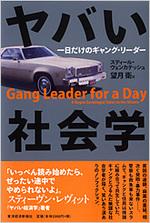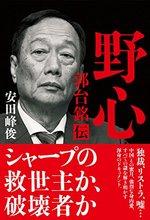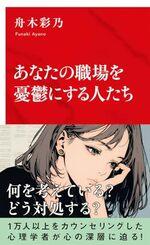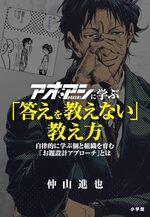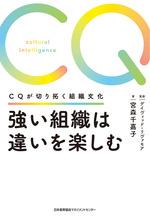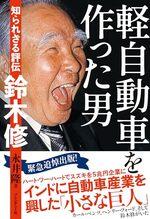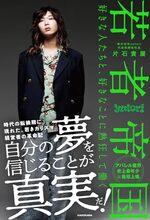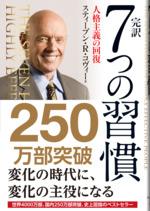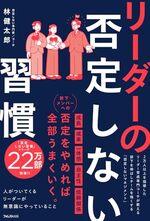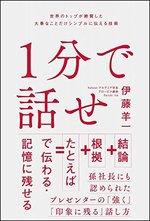【必読ポイント!】 組織的知識創造とは
過去の成功体験にすがってはならない

日本企業が成功した最大の要因は、「組織的知識創造」の技能・技術を持っていたことだ。組織的知識創造とは、組織に属する人々が創りだした知識を、組織全体で製品やサービス、あるいは業務システムというかたちで具現化することである。こうした特徴をもっていたからこそ、日本企業はたえまなくイノベーションを生みだすことができたのだ。
とはいえ、このような見方は、「日本企業は模倣や応用には強いが、あまり創造的ではない」という従来の考えかたに反しているかもしれない。たしかに、日本企業が現在、戦後最長最悪の不況にさらされているのは事実である。だが、この不況を切り抜けることができれば、日本企業はこれまで以上に強くなるだろう。というのも、日本企業はこれまでも多くの危機に直面してきたが、そのたびに過去の成功体験を乗りこえ、新しいビジネス・チャンスを求めて未知の領域に挑戦してきたからである。
暗黙知こそが鍵である
西洋人が、組織的知識創造という発想にいたらないのは、彼らが組織を「情報処理の機械」としてしか見ていないからだ。こうした見方は、ありとあらゆる西洋的経営の伝統に深く根ざしている。彼らにとって、知識は明白なものでなければならず、形式的・体系的なものでなければならない。そうした知識を「形式知」と呼ぶ。
一方、日本企業はそれとはまったく異なった知識観を持っている。言葉や数字で表される知識はしょせん氷山の一角であり、深層部分には表現しがたい暗黙的なものがあると考えているのだ。そのような知識を「暗黙知」と呼ぶ。
この「形式知」と「暗黙知」の区別にこそ、西洋と日本の「知」の方法論の違いを理解する鍵がある。西洋のマネジャーは形式知ばかり注目しているが、彼らにとっても暗黙知の重要性を認識することはきわめて大切だ。なぜならそれはまったく違った組織観をもたらすからである。暗黙知を重視する企業は、組織をたんなる情報処理の機械ではなく、ひとつの有機的生命体としてとらえる。そうした組織観においては、主観的な洞察、直観、勘、理想、価値、情念、イメージ、シンボルなどが重要な意味をもつことになる。
暗黙知を形式知に変えるために
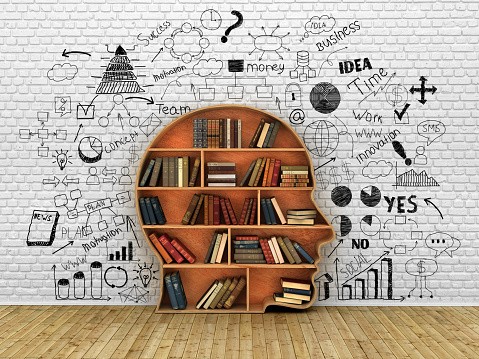
日本企業の知識創造の特徴は、つまるところ暗黙知から形式知への変換にある。日本企業は、とくに製品開発の場面において、この暗黙知から形式知への変換を得意としている。だからこそ、ここまで大きく成長したのだ。
暗黙知から形式知への変換には、次の3つの特徴がある。(1)表現しがたいものを表現するため、メタファーやアナロジーが多用される。(2)個人の知が多くの人に共有され、知識が広まっている状態である。(3)新しい知識はつねに曖昧さと冗長性のなかで生まれてくる。それぞれ順に説明していきたい。
まず、知的創造の初期段階の特徴として、メタファーやアナロジーが多用されていることがあげられる。たとえばホンダは、「クルマ進化論」、「マン・マキシマム、マシン・ミニマム」、「トールボーイ」といったコンセプトからホンダ・シティを生み出し、日本では今や普通になった「高くて短い」新世代車の先駆けとなった。メタファーを用いることで、既知のものを新しく組みあわせ、それまでは表現しにくかったものを創造したのだ。一方のアナロジーはメタファーと比べるとやや論理的な手法である。2つの事物のどこが似ていて違うのかをはっきりさせるという意味で、アナロジーは純粋な想像と論理的な思考を媒介する。ホンダ・シティの場合、シビックとの相違を探るなかから、ブレイクスルーとなるコンセプトが生まれた。これもアナロジーの活用法の1つである。