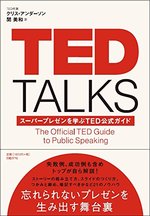見える化
強い企業をつくる「見える」仕組み
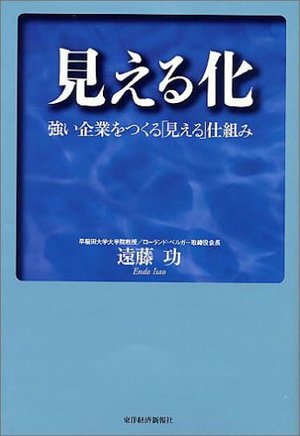
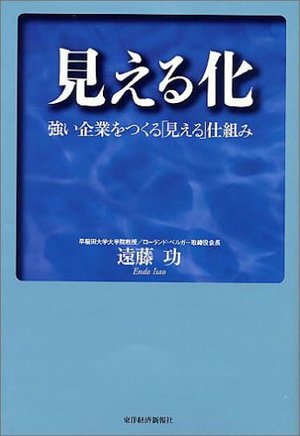
著者
遠藤 功(えんどう いさお)
早稲田大学ビジネススクール教授。
株式会社ローランド・ベルガー会長。
早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。
三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。
早稲田大学ビジネススクールでは、経営戦略論、オペレーション戦略論を担当し、現場力の実践的研究を行っている。また欧州系最大の戦略コンサルティングファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。ローランド・ベルガードイツ本社の経営監査委員でもある。中国・長江商学院客員教授(2008年より)、日新製鋼株式会社経営諮問委員などを兼任。
著書に『現場力を鍛える』『ねばちっこい経営』『プレミアム戦略』(いずれも東洋経済新報社)、『MBAオペレーション戦略』(ダイヤモンド社)、『企業経営入門』(日本経済新聞社)、『ビジネスの“常識”を疑え!』(PHP研究所)などがある。
『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の「2004年読者が選ぶベストブック」の第1位に選ばれた。また本書で2006年(第6回)日経BP・Biz Tech図書賞を受賞。
個人ホームページ:http://www.isaoendo.com
早稲田大学ビジネススクール教授。
株式会社ローランド・ベルガー会長。
早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。
三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。
早稲田大学ビジネススクールでは、経営戦略論、オペレーション戦略論を担当し、現場力の実践的研究を行っている。また欧州系最大の戦略コンサルティングファームであるローランド・ベルガーの日本法人会長として、経営コンサルティングにも従事。ローランド・ベルガードイツ本社の経営監査委員でもある。中国・長江商学院客員教授(2008年より)、日新製鋼株式会社経営諮問委員などを兼任。
著書に『現場力を鍛える』『ねばちっこい経営』『プレミアム戦略』(いずれも東洋経済新報社)、『MBAオペレーション戦略』(ダイヤモンド社)、『企業経営入門』(日本経済新聞社)、『ビジネスの“常識”を疑え!』(PHP研究所)などがある。
『現場力を鍛える』はビジネス書評誌『TOPPOINT』の「2004年読者が選ぶベストブック」の第1位に選ばれた。また本書で2006年(第6回)日経BP・Biz Tech図書賞を受賞。
個人ホームページ:http://www.isaoendo.com
本書の要点
- 要点1「見える化」の真の意味は、「問題を『見える』」ようにすることである。
- 要点2「見える化」の基本は、相手が「見よう」という意思を持っていなくても、自然とさまざまな問題が「目に飛び込んでくる」状態をつくりだすことである。
- 要点3都合の悪い情報ほど、素早く「見える化」することが肝要だ。
- 要点4よい「見える化」は、人に刺激を与え、気付きや思考、対話、実行といった能力を育んでくれる。
要約
【必読ポイント!】 「見える化」とは何か
問題を明らかにするのが「見える化」の本質
現在、「見える化」という言葉はさまざまな意味で用いられている。しかし、オリジナルの意味は、「問題を『見える』ようにする」ことである。
問題解決能力を高めるためには、なによりもまず問題が「見える」状態になっていなければならない。人間が外部から得る情報の8割は、視覚から得ていると言われており、実際、私たちの行動の大半は、目に見える情報にもとづいている。
だからこそ、実態や問題を包み隠さず、タイムリーに「見える」ようにすることが重要になってくる。人間が本来持っている責任感や能動性、やる気を信じ、企業活動上のあらゆる問題を浮き彫りにさせることこそが、「見える化」の本質なのだ。
問題が目に飛び込んでくる状態をつくりだせ

bee32/iStock/Thinkstock
社会には、「見える化」を勘違いしているような取り組みが多数存在している。なかでも、1番多い勘違いは、さまざまな情報をオープンにさえすれば、「見える化」が達成できるというものである。確かに、多くの人たちが情報を共有すること自体は決して悪い取り組みではない。しかしそれは、相手が「見よう」という意思を持っていなければ機能しないものだ。
「見える化」の基本は、相手の意思にかかわらず、さまざまな問題が「目に飛び込んでくる」状態をつくりだすことである。「見る」ではなく、「見える」という言葉が用いられている理由もそこにある。「人間は問題が目に飛び込んでくれば行動を起こす」というのが、「見える化」の基本理念である。
情報の共有という同じ目的をめざしていたとしても、自然と目に飛び込んでくる「見える」状態なのか、それとも相手の「見る」という意思に頼ったものなのかで、その効果は劇的に変わってくる。それにもかかわらず、「見える化」を導入したという事例の大半は、IT(情報技術)を用いて情報をオープンにすることだけで満足してしまっている。
ITは「見える化」のための有用なツールではあるが、その目的によって正しく使い分ける必要がある。実際、ITは「見える化」には向いていないことも多く、むしろITによって「見えない化」を促進してしまう場合すらある。
勘違い企業の共通点

Purestock/Thinkstock
「見えている状態」とは程遠い状態にあるにもかかわらず、「見える化」できていると考えている企業にはいくつかの共通点がある。
まず、自分にとって都合の悪い情報を「見える化」していない。ポジティブな情報を「見える化」するなとは言わないが、そういった情報は工夫しなくても自然と見えてくるものである。重要なのは、本来「見せたくない」情報を明らかにすることだ。悪い情報を早く発見し共有できれば、手遅れになる前に手を打つことができる。
また、当事者や一部の関係者しか問題が見えていないという状況も厄介である。大事なのは、「組織」として、問題が「見える」ようになっていることだ。ここでいう「組織」が何を指すのかは、それぞれの問題の大きさや深刻度に応じて変わってくるが、関与すべき人たち全員に「見える」ようになっていなければ、「見える化」とは到底言えない。
加えて、「見える化」のタイミングが遅かったり、ずれていたりしては意味が無い。

この続きを見るには...
残り3152/4475文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.08.17
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約