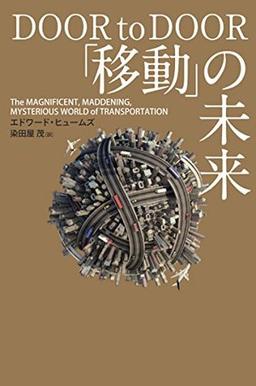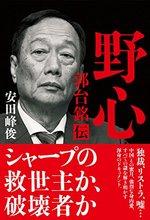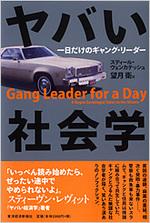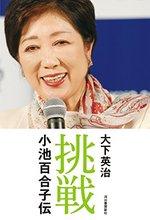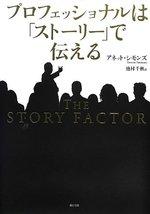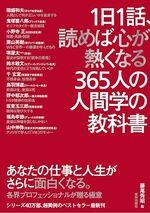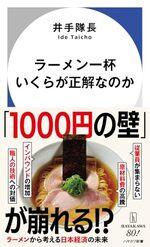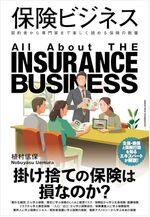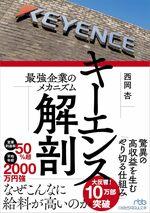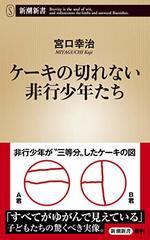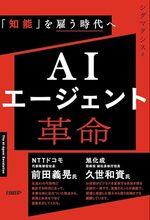車社会がもたらしたもの
スターとしての車
車は1世紀前からスターとして君臨してきた。産業化時代には他の追随を許さない持久力を誇っていたし、シリコンとソフトウェアが優勢になった時代でも、車は個人の自由と結びつけられ、重宝されてきた。いまでも、出産前の母親にベビー用品を贈るパーティ(ベビーシャワー)では、子どもが初めて車に乗るときのためにチャイルドシートが贈られるのが常だし、免許証を得ることは成人の通過儀礼として重要視されている。アメリカでは車に乗って買い物に行き、車に乗って仕事に行くのが普通なのだ。
だがその便利さの代償として、経済や環境、エネルギー、効率性、健康、安全といったさまざまな面で、莫大な社会的・金銭的コストが生まれている。そしてその事実に、多くの人々は目をつぶってしまっているのである。
車のコストは計り知れない

車は燃料を途方もなく浪費する。インフラや日常生活のなかで、現代の自動車以上にエネルギーと金を浪費するものはどこにもない。燃料を燃やし尽くすことで、自動車は毒素と微粒子状の廃棄物を大気中に吐き出し、癌や肺病、喘息の原因となっている。くわえて、燃料用の石油の採掘、輸送、精製にかかる間接的な環境・健康・経済コスト、膨大な国家安全保障上のコストや燃料のかなりの部分を海外からの石油輸入に依存するというリスクがここに加わる。
また、車は最も機会を浪費する投資対象でもある。投資銀行のモルガン・スタンレーは、車を「世界で最も活用されていない資産」と呼んだ。平均的な車は、1日の92%の時間、使われずに放置されている。にもかかわらず、すべてのコストを合計すると、アメリカの平均的な車の所有者は、週に14時間しか使わない車のために年間1万2544ドルを支払っている。
そのうえ、車は気候に対する最大の脅威でもある。ガソリン代や車本体の価格だけが、車のコストではない。車が原因となって地球上に生じたコストと損害を計算にいれた場合、その数字は計り知れないものとなってしまう。そして、それは補助金という目には見えないかたちで人々の負担となっている。
社会は自動車事故を気にかけない

数多くある車のコストのなかでも、最も重いのが命だ。車は命を浪費する。だが不思議なことに、自動車事故に対して注意を払ったり、怒りの声をあげたりする一般市民はごくわずかしかいない。大多数のドライバーにとって道端の事故車は、どこへ行ってもつきまとう苛立ちの種というだけだ。おびただしい数の人間が自動車事故で負傷し、死亡していることを知っているにもかかわらず、である。
これが飛行機の墜落事故であれば、世間の受けとめ方はまったく異なる。飛行機の事故はつねに注目され、費用を惜しまずに調査が行われる。だが、旅客機が死者数で車と肩を並べるためには、毎週4機ずつ墜落しなければならない計算になる。
車には、航空業界なら当然義務づけられている、それぞれの事故の徹底的な検証も、将来おなじ惨劇を起こさないための方策を見つけようとする試みもない。ただ地元の検視官と警察官による形式的な報告書があるだけだ。
むろん、アメリカでも何かが原因で負傷事故や死亡事故が起きたときは訴訟が行われる。だがそれも、保険会社によってひそやかに解決されることがほとんどである。唯一の例外が、運転者ではなく車そのものの安全上の欠陥に関する訴訟が行われた場合だが、それもほんの一部にしかすぎない。
自動車事故は1歳から39歳までのアメリカ人の死因の第1位であり。112人に1人が交通事故で亡くなっていることになる。自動車が原因の死亡および負債から生じる経済コストと社会的影響は年間8360億ドルにも達し、税金や保険料から支払われる医療費や救急隊など緊急時対応要員の費用といった直接的な経済コストだけでも、1人あたり784ドルの負担が強いられている。
それでも、アメリカの人々は、日々大量の死傷者が出るのは現代社会の移動性を確保するための代償としてあきらめ、問題を看過している。死傷者が出るのは、危険運転や車や道路の設計の誤りがもたらした当然の結果にもかかわらず、それを欠陥ではなく、天災などのような「事故」として扱ってきたのだ。
【必読ポイント!】 車社会のこれから
ミレニアル世代の登場
1980年代から2000年代に生まれたミレニアル世代は、それ以前の世代に比べて自動車を所有したり、運転したり、郊外で暮らしたりすることにあまり関心をもっていないと言われている。実際、16歳から34歳までの運転者の走行距離を調べた結果、2009年のほうが01年よりも23%、運転者の走行距離は少なかった。これはほかの年齢層にくらべて大きな落ちこみだ。
車中心の昔の世代にとっては考えられないことだろうが、彼らは輸送手段にこだわらない傾向にある。