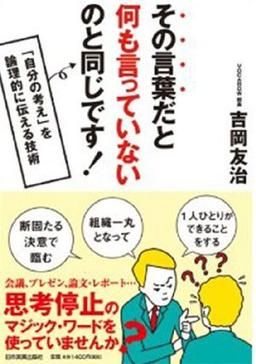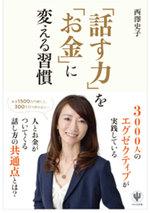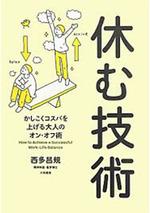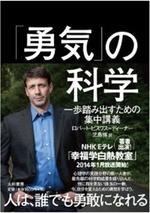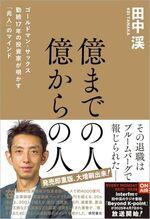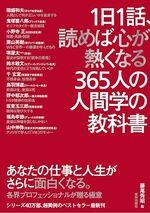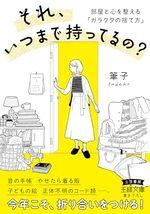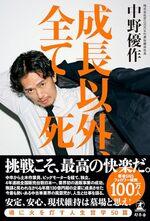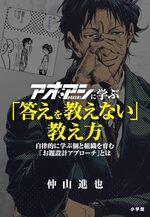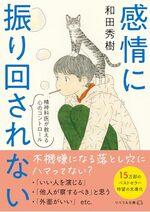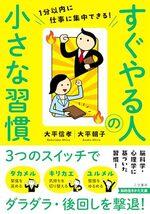【必読ポイント!】便利だけれど、何も言っていない「マジック・ワード」
もっと議論をすべき

これは本書では、「問題解決から遠ざかる系」として紹介されている言葉である。具体的な使用シーンはこのようなものだ。
A「わが社の業績を上げるには、どうすればいいと思う?」
B「もっとみんなで議論するべきだと思います」
A「いや、もう議論は始まっている。それより、問題をどうすればいいか」
B「だからこそ、私は強く主張しているんですよ!」
A「なんて?」
B「もっと議論が必要だと」
あなたも会議でこのようなシーンを見たことはないだろうか。
この「もっと議論するべき」は「頑張れ、もっとやれ」というようなもので、はやしたてたり、やじ馬になったりするのに等しい。
もし、この言葉が意味をなすとしたら、議論が途中で終わりそうなとき、あるいは全然議論が行われないままに終わってしまいそうなときのみである。このような意味で、マスコミがこの言葉を活用することは多少意味があるが、個人においてはその限りではない。
本当に今必要なものでしょうか?
この言葉は、「呪いの協調言葉系」と呼ばれるものだ。
A「どうしても予算編成が腑に落ちないのです」
B「どこが疑問なんだい?」
A「この予算は、本当に今必要なものでしょうか?」
というのが使用シーンだ。
「本当に」「やはり」「とにかく」などは強調する言葉ではあるが、言うと気持ちが入る割には、意味はあまり明確ではない。先の例で言うならば、「この項目はこれだけの金額と述べているが、このデータによれば、それほど必要ではないはずだ」と言う方が建設的である。
「本当に必要か」という言葉は漠とした不安を投げかけるものだ。こう言われると誰でもひるんでしまう。それを利用して相手を黙らせ屈服させる語法なのだ。
そこで、「必要ないという根拠はおありなのか?」と反撃する態勢が重要である。このパターンには即座に言い返すのだ。
主体性を持って取り組め

この言葉は、「理屈よりも力がものをいう系」として紹介されているものである。
上司「プロジェクトが思うように進んでいない。それぞれがもっと主体性を持って取り組んでもらいたい」
部下「みんな頑張っていますよ」