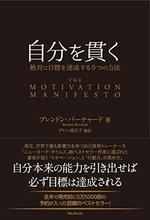教養のための読書
著者の読書経験から
小学校時代、著者はまわりの少年たちと同じように、英雄豪傑の物語を集めた「立川文庫」に夢中になっていた。それは、単純に面白かったからである。それから50年が過ぎても、やはり読書というのは面白い本を読むということであって、面白くない本を読む習慣は持っていないという。
立川文庫を読むことは面白い遊びであって、当時の「心の歯車」と深く噛み合ったものだった。どんな高尚な本でも読者の心の歯車と噛み合わなければ面白くないし、面白くない本が人間の成長を助けることはない。大人でも、子供でも、面白くない本は読まない方がよいのだ。そして、面白い本を読むというのは、自分の生活をドラマティックにすることである。哲学の本などでも、それが読者の心の歯車と噛み合いはじめたとたんに、一種のドラマが生まれてくる。
しかし、著者が夢中になって読んだ立川文庫を手放す日がやってきた。自分で決心し、すべてを友達にあげてしまったのだ。飽きたからである。飽きるということはマイナスに評価されがちだが、飽きることは悪いことではないという。人間の精神の成長は、しばしば、飽きるという形で現れる。それは、心の歯車に変化が生じ、これまで面白かったものが面白くなくなるということだ。そうした瞬間は、精神が成長を遂げる瞬間である。しばらくすると、また新しい面白い本が現れてくる。
人を読書へと駆り立てるもの

著者は、読書の楽しみを知ると、他人には理解できそうもない本を探して読むようになった。虚栄心に駆り立てられ、無理な背伸びをしていたのである。それで得たものは多くないそうだが、著者は虚栄心そのものを否定しない。虚栄心は、自分を実際の自分以上のものに見せようとする傾向であり、人間が現在の自分を乗り越えて行くために欠くことの出来ないものなのだ。虚栄心が人を駆り立て、そこから思わぬ業績が生まれることもある。
また、著者が大きな影響を受けた人物に、社会思想家の大杉栄がいた。大杉は、読書はただその人の個人的思索を進めるために役立てばいいという。研究や思索は、日々の生活で直面するある事実に対する、止むに止まれぬ内的欲求である。自身の内的欲求を、他人の著書、つまり他人の観察と実験と判断によって満足させるのは、他人の思想の奴隷になることである。個人的思索を成就させてこそわれわれは自由な人間になるのだ、というのが大杉の考えなのだ。
教養書とは何か
そもそも、本には3つの種類があると著者はいう。まずは、実用書であり、これはたとえば冠婚葬祭のしきたりに関する本のように、生活の必要を満たす本である。次に娯楽書がある。これは、例えば、エンターテインメント小説のような、生活から連れ出してくれる本である。これら二つについては、読み方は問題とならない。前者は必要があれば読まなければならないし、後者は読みたくなったら読めばいいからである。問題は教養書である。教養書は一言でいえば生活を高める本である。ただし、読むことを強制されず、誘惑されることもない。自分で決意し、努力して読む必要がある本である。ただ生きるため、ただ死ぬためであれば教養書など読む必要はない。立派に生き、立派に死ぬために必要なのである。教養書は、与えられた生命を自分の理想に向かって作り直し、立派に作り上げようとする人たちのためにある。
【必読ポイント!】 本の内容を忘れない工夫
試行錯誤の経験

深い感銘を受けながら読んだ本のはずなのに、その内容を忘れてしまったという経験がある人は多いであろう。後の役に立てるために、知識の保存をどうするべきなのか。