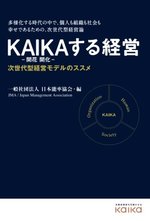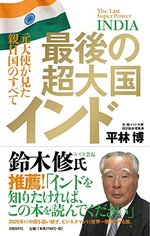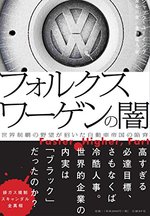大前研一ビジネスジャーナル No.13
デジタル・ディスラプション時代の企業経営
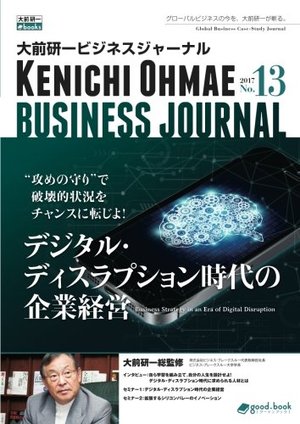
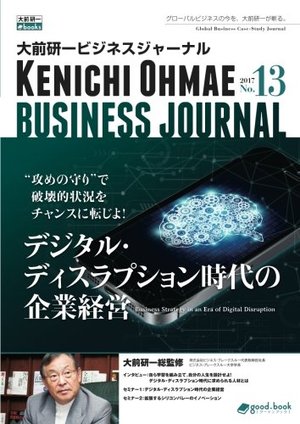
著者
大前 研一(おおまえ けんいち)
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長/ビジネス・ブレークスルー大学学長
1943年福岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、常務会メンバー、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。以後も世界の大企業、国家レベルのアドバイザーとして活躍するかたわら、グローバルな視点と大胆な発想による活発な提言を続けている。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長及びビジネス・ブレークスルー大学大学院学長(2005年4月に本邦初の遠隔教育法によるMBAプログラムとして開講)。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開校、学長に就任。日本の将来を担う人材の育成に力を注いでいる。
株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長/ビジネス・ブレークスルー大学学長
1943年福岡県生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、常務会メンバー、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。以後も世界の大企業、国家レベルのアドバイザーとして活躍するかたわら、グローバルな視点と大胆な発想による活発な提言を続けている。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長及びビジネス・ブレークスルー大学大学院学長(2005年4月に本邦初の遠隔教育法によるMBAプログラムとして開講)。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開校、学長に就任。日本の将来を担う人材の育成に力を注いでいる。
本書の要点
- 要点1ITが加速する世界最適化の動き「デジタル・ディスラプション」は、イノベーションと表裏一体の破壊的な変革である。ほぼ全ての産業に影響を及ぼし、そのインパクトの大きさは市場規模に比例する。
- 要点2ディスラプションはユーザーの利益本位の結果として生じており、売り手の論理で固まっていた業界秩序を破壊していく。
- 要点3日本がイノベーションを創出し、競争力を高めていくには、シリコンバレーの潮流を捉え、日本独自の強みを磨き上げるという発想が必要だ。
要約
【必読ポイント!】 デジタル・ディスラプションの時代
デジタル・ディスラプションとは何か?

Tero Vesalainen/iStock/Thinkstock
スマートフォンが引き起こした破壊的イノベーションにより、人々の生活は大きく変化している。低コストのITツールやテクノロジーを活用して、新たなビジネスモデルを用いてサービスや商品を提供し、旧来型の産業・業界に創造的破壊を起こす。これを「デジタル・ディスラプション」と呼ぶ。
デジタル・ディスラプションの特徴は、世界でほぼ同時に生じ、進行していくことにある。これまでのビジネスでは、国内で成功してから他国へ展開するという戦略をとるのが一般的だった。しかし、今日の世界戦略は、スマートフォンを中心として起業家や出資者、既存企業が結びついたエコシステムを基盤に、多くの国々で同時展開する戦略だ。このため、破壊的変革も同時多発的になってしまう。
このデジタル・ディスラプションが自分たちの業界を襲ってきたらどうすべきか。防御策として一定の効果があるのは、相手のビジネスモデルをパクッてしまうことだ。例えば、「Uber」はライドシェアという新しいビジネスモデルで世界を圧倒した。この動きに対して、中国ではすぐに「滴滴出行」という類似の配車サービスが登場した。今では滴滴出行が、中国シェアの9割を握っている。
今まで業界秩序は、商品やサービスの提供側がつくりだしており、それが市場を支配してきた。例えば、農協が農産物の生産や販売の管理を主導するというように、各業界では、業界団体がサービス提供側の論理で市場を形成してきた。そしてユーザーはその中でのみ選択を強いられていた。
しかし、テクノロジーの進化によって、農家は農産物を直接販売できるようになった。この事例が示すように、従来は受け身だったユーザー主導で、業界秩序を再編できる時代が到来したのだ。テクノロジーによって真に民衆主導の革命が実現できるといってよいだろう。
自動車業界を破壊するディスラプター
デジタル・ディスラプションはあらゆる業界に押し寄せてきており、インパクトの大きさは、その市場規模に比例する。具体的には、小売業が最も大きく影響を受け、金融業、医療福祉、自動車、物流、コンテンツ、農業といった分野が続く。
ディスラプターで最も有名なのはライドシェアのUberで、直接影響を受けるのはタクシー会社だ。ライドシェアにも複数の企業が登場しており、その相乗効果でユーザーの利便性が増していくと、自動車業界全体に影響を及ぼすようになる。ライドシェアやカーシェアという文化が根付いてくると、車を購入する必要がなくなり、社会全体の自動車保有台数が大幅に減少するからだ。
Uberの1日当たりのアクティブユーザー数は2015年時点で800万人といわれる。非上場企業でありながら、ユーザー数、時価総額ともに、Uberはすでに大手自動車メーカーに匹敵する規模に成長している。このライドシェアサービスが、自動車業界を破壊するデジタル・ディスラプションの典型であることは理解しやすいだろう。
Uberは、これと同じ物流サービスをトラックでもやろうとしている。空きトラックと、それを利用したいユーザーとをマッチングさせるサービスだ。さらにUberは、自動運転でのテスト走行もすでに成功させている。このように、Uber経済圏なるものが形成されつつあるのだ。
全世界を襲うデジタル・ディスラプション
金融業界のディスラプター
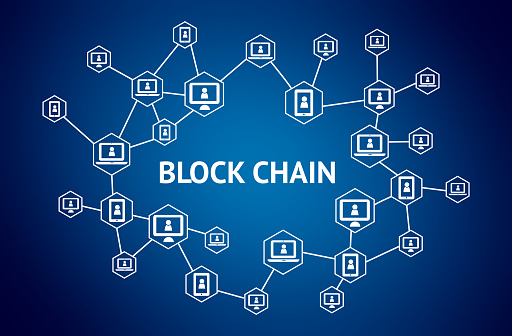
Zapp2Photo/iStock/Thinkstock
金融業界では、数年前からFinTechがディスラプトしている。ビットコインなどの仮想通貨で用いられているブロックチェーン技術においては、国内金融機関がオンライン決済で用いるような大規模インフラは不要となる。なぜなら、不特定多数のコンピュータによる分散共有型システムに代替されるからだ。従来型の金融システムが中央集権的で独占的なシステムだとすると、この分散共有型のシステムは民主的といえる。

この続きを見るには...
残り2853/4456文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.12.11
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約